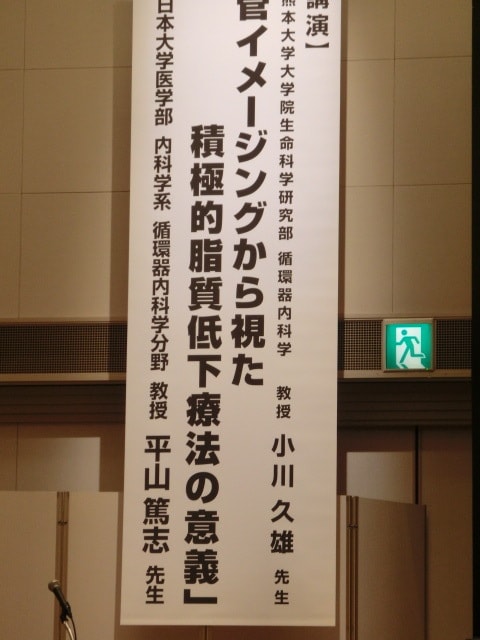昼休みにD社のBという骨粗鬆症の改善薬についての勉強会が、調剤薬局のスタッフも交えて当クリニックの待合室で開かれました。
スライドでプラセボ(偽薬)や他社の薬との比較が示されますが、だまされないように素早くNNTを計算したところ90くらいでした。
つまり、90人がこの薬を飲むことによって、やっと1人が恩恵に浴すことができるレベルなのです。
しかも、この薬を飲むと、150人に1人が深部静脈血栓症を発症するのです。
NNT(Number of Needed Treatment) という考え方の大切さを痛感させられました。
さて、勉強会に饗された糖質制限弁当は秀逸なものでした。
ステーキ、ウナギのかば焼き、塩鮭、ホタテ、プリプリのエビなどで大満足でした。
ところで、最近腹が出てきたような気がしたので体重測定をしたところ、なんと久方ぶりの67Kg台でした。
そこで一週間ほどウィスキーをやめて、糖質ゼロの発泡酒オンリーでいくことにしました。

こいつが最近のお気に入りです。
人工甘味料がゼロで、アルコール度が6%である点が理由です。
カロリーは1本で90くらいです。
胃が膨れるので、一晩に4本飲むのが精いっぱいです。
で、2日間実践したのですが、体重は64.85Kgに落ちていました。
2Kg落とすには一週間かかるだろうと思っていましたが、2日間で達成してしまいました。
そこで、即、ウィスキーを復活させました。
2日ぶりのウィスキーは、当然ながらうまさを増していました。
考察すれば、私の体重は、ただただウィスキー依存性であるということですよね。
人体が真っ先に消費するエネルギーはアルコールだそうです。
2番目がブドウ糖、3番目が脂肪、最後がタンパク質(筋肉)の順番だそうです。
私の場合はウィスキー無しでは、カロリー不足に陥るということですよね。
この飲んだくれた生活を4年間も続けているわけですが、なんだか不安を感じる時もあります。
しかし、血液データは100点ですし、何よりもQOLが高いのでやめられません。
また、2月に半月ほど禁酒した時も禁断症状は全く有りませんでした。
身を挺した人体実験であるということにしておきます。