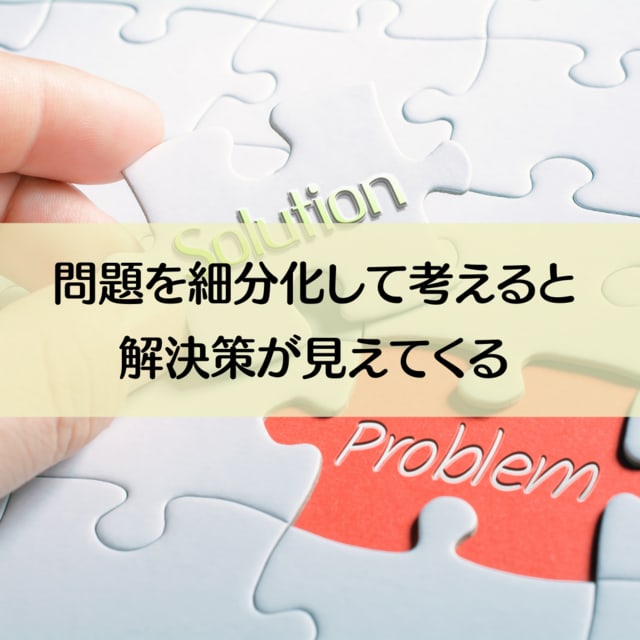
(一社)ハートマッスルトレーニングジム代表
主体的人生を構築する人材育成トレーナー
桑原朱美です。
今日のテーマは
「問題を細分化して考える」です。
質問シリーズその3
ここ2日間、「質問」をテーマにお伝えしています。
昨日は、自分の企画が通らず、落ち込んだAさんの事例を紹介しました。
その中で、Aさんが落ち込んだ理由として次の2点を上げました。
(1)企画が通らなかったという事実が「受け容れてもらえなかった」という解釈に変換されている
→ 昨日の記事で説明
(2)「企画が通らなかった」という大きなくくりで思考している
今日は、この(2)について一緒に考えていきたいと思います。
「大きなくくり」とは?
さて、「大きなくくりで思考している」とはどういうことでしょうか。
言い換えれば、
「抽象度が高いままで頭の中だけで思考している」ということです。
このことが「通らなかったこと」が「受け容れてもらえなかった」と
勝手な妄想変換をしてしまう原因です。
つまり、ここでのキーワード「企画が通らなかった」ということは、
もう少し「具体化」できるのです。
・目的や必要性が整理されていたか
・ポイントがまとめられていたかどうか
・理解しやすい伝え方だったのか
・聞き手が自分の問題としてとらえることができる提案だったか
などなど、いろいろなことが考えられます。
こうした要素を書き出してみると、どうすればよいのかを
考えなおすことができます。
「相手がわかりやすい伝え方をするには?」
「自分事としてとらえてもらえるには?」
「必要性をもっと感じてもらうためには?」
問題を細分化し、そこから新たな自己質問をすることで
次の提案のための改善点が見えてきます。
禅問答や哲学的思考であれば
抽象的な質問は思考を刺激しますが
現場での解決策であれば質問そのものを
具体的にしていくことが必要ですね。
問題は細分化する
デカルトの名言に「困難を分割せよ」ということばがあります。
また、ビルゲイツは「問題を切り分けろ」と言っています。
保健室コーチングの脳科学傾聴も、「問題の細分化」「問題の振り分け」をします。
解決だけに走ろうとすると、こうした視点が抜けてしまいます。
問題を細分化しないままだと、感情だけが残ります。
うまくいかなかったとき、安易に、誰かのせいにしたり
自分にダメ出しをする思考パターンになってしまうのです。
これでは、前に進むことができません。
問題を分解し、的確な答えを発見できる客観性をもつことは
とても大切なことです。
それでは
今日も、素敵な1日を!
p.s.3月のライフストーリーサミットでは主催の芝蘭友先生が
「質問の極意」についてお話されます。
14人の講師からそれぞれの専門分野で
たくさんの刺激を得ることができます。参加は無料です。
※登録後はFacebookグループへの参加の案内が届きます。
ライブの視聴もアーカイブもこのグループ内で視聴できます。
https://withlinkey.com/summit2022/kuwahara
この記事は、メルマガ「可能性をあきらめたくない女性のための時間と思考の使い方」
2022年2月17日号で紹介した内容に加筆修正した内容です。






















