京都観光のガイドブログです。定番の楽しみ方から特別拝観、さらには年に1度の御開帳まで。
京都観光では最も詳しいです!
Amadeusの「京都のおすすめ」 ブログ版(観光)
2013 5/11の拝観報告(その時、歴史が動いた??!!)

写真は、・・・
ハイハイ、ざわつかない。
まずは人の話を聞く(笑)!
この日は朝から仕事で大阪の中ノ島でした。
そのため前日に京阪電車の切符を買いに金券ショップに行きました。
片道460円が380円で行けるのでお得です。
往復2枚で760円のハズが・・・1960円でチケットが3枚?
しかし”気弱でハト派”の僕は何も言えず帰宅・・・。
翌朝から中ノ島。
14:00頃に中ノ島を出たのですが、朝も早かったため車内でうつらうつら。
”慌てて下車”したら、どうやら”おっちょこちょいの僕”は降りる駅を”間違え”ていたよう。
しかも西に歩くところを、”人の流れに流され間違えて”東へ。
人の流れに乗って、”無意識に”写真の場所へ・・・。
そして”偶然”残り1枚のチケットで、そこに入れる状態のよう!
”偶然に偶然が重なった”ので、”しょうがない”から初めて入ってみました・・・
京都国立博物館。
・・・・・・・
ガヤガヤしない!
なんか文句あるか!!
もうええ、
行ったぞ京博!!!
考えたんですよ。
もはや庭園はほとんど行き尽くした。
自分にとって今後の”伸びしろ”がもうほとんどない。
今後さらに自分が発展していくには・・・動産系に手を出すしかない・・・と。
「こりん星の存在を否定した、小倉優子さんの気持ち」
が少し分かったような気がしました(笑)。
ただし僕は飽くまで、
庭園派
ですからね。
さてみなさんお楽しみの感想です!
いきなり全部しっかり観るのは”素人”にはムリと判断し、興味があるものはしっかりそれ以外はさらっと観ることにしました(笑)。
まずは天祥院でデジタル複製を見た「老梅図襖」。
そしてその裏の「群仙図襖」。
50年ぶりに旧に復して良かったのですが、バラバラに海外に流出しているのは実にもったいないですね。
あとコメントでも話題になった「猿猴図」。
あれはそのままキャラクターグッズになりそうですね。
同じような感じだったのが「松梟竹鶏図」の梟。
とぼけた表情がいいですね。
面白かったのは、「秘伝画法書」。
なかなかこのような”舞台裏”を見られることがないので、少し笑えました。
最後に今回僕が1番見入ったものは、
「長恨歌図巻」
でした。
修復されていますが、精緻なタッチが見事。
お話が順に進んで行くので、物語を読んでいるようです。
しかし建物など”神経質”に描いてありますね。
結構早めに観たつもりでしたが、それでも1時間30分かかりました。
図録も買いました。
もちろん初めて(笑)。
今でも”前乗りの興味”とまではいかないですが、勉強してみようとは思っています!
さすがに今までの拝観や京都検定での勉強を通じて”動産系知識の基礎体力”はあったようで、それなりに解説の意味も分かり楽しむことも出来ました。
まあ地味に知識を増やしていこうと思います。
最後にもう1回言っておきます!
僕は庭園派であり、決してB派に屈服はしていませんからね(笑)!!!
さあ、コメントでヤイヤイ言って下さい!
アンケートを実施しています。
左サイドバーにあります。
携帯の方はココ。
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 41 ) | Trackback ( )
2013 4/13 第2回 アマデウス会 総会 がんこ二条苑

写真は、加茂の間。
この日も朝から拝観でしたが、昨夜はなんと
第2回 アマデウス会 総会
でした。
年に2回のアマデウス会員の懇親会です。
参加者は、あんとん, 2級のほう, WAN, hyt, maybe, serimama, super-meteor, tani, toganji, かんじろう, ミッキー, ルーキー, 京極堂, 至誠館, 茶花そしてamadeus(敬称略)の16名でした。
まず前座!?として、18:30から廣誠院の夜間拝観。
ここは任意でしたが、既に12名が参加。
やはり皆さん”お好き”です。
今回は過去とは違いお茶の接待はあるし、公開部分は多いし、自由なので良かったですね。
ただし夜のライトアップはどうなのでしょう・・・。
そして会場の”がんこ 二条苑”に移動。
ここで残る4名と合流し、19:30から宴会の開始です。
テーブルは
(京極堂、 super-meteor、至誠館、かんじろう)
(2級のほう、maybe、serimama、ルーキー)
(WAN、hyt、tani、ミッキー)
(あんとん、茶花、toganji、amadeus)
で1卓ずつでした。
序盤で皆さん軽く自己紹介。
たまに僕がチャチャを入れるがごとく情報追加をさせて頂きました(笑)。
それ以降は各テーブルでお話。
内容は、それぞれ。
最近の拝観話、おすすめ処や展覧会、奈良(とかいうところ!?(笑))の話も。
いやはや盛り上がったのではないでしょうか。
皆さん同じなのでしょう。
身の周りに、自分が拝観した内容や、その感動などを、
・前向きに
・ちゃんと理解して
・面と向かって
聞いてくれる人が、なかなかいないのです。
ここは”そういう人”が集まっているので、安心です(笑)。
お話は尽きず、あっという間に21:45頃になりました。
そして22:00まで上写真の高瀬川源流庭園を堪能し、一旦ココで解散しました。
そして野郎軍団10人(2級のほう、WAN、maybe、super-meteor、toganji、かんじろう、ミッキー、京極堂、至誠館、amadeus)は、さらにからふね屋でお茶をしながら情報交換というか今後の戦略!?を練りました(笑)。
しかしこれだけの皆さんですから、いろいろな情報を持っておられますね。
今後も忙しそうです(笑)。
本当に楽しい時間でした。
少なくとも僕は(笑)。
次回は11月。
また新しい会員さんも迎えて開催出来る日を楽しみにしています。
お忙しい中、参加して頂いた皆様、ありがとうございました!
コメント ( 22 ) | Trackback ( )
2013 3/23の拝観報告3 最終(京都検定1級合格者のつどい)

写真は、円山公園のしだれ桜 2分咲き
そして13:00からの”京都検定1級合格者のつどい”に参加するために、八坂神社に向かいました。
毎年拝観付きで、会場が変わるのですが、今年は八坂神社の本殿と美御前社でした。
先日掲載したように、既に八坂神社の本殿は3/16に拝観しているので、もはや本殿の写真を載せても誰も喜びません(笑)。
そこで13:00より前に訪れた、円山公園のしだれ桜です。
まだ2分咲きぐらいでしたが、園内全体的には咲き始めているので、来週末ぐらいには満開でしょうか。
さて13:00に常盤神殿に集合です。
受付をしていると、サイドから”見つけた”的な視線を感じたのでみるとアマデウス会員で今回1級に合格された”綾目草”さまでした。
今回の試験では140名近い合格者がおられましたが、そのうち100名を超える参加者があったそうです。
脅威的な参加率ですね。
会の流れです。
まずは商工会議所の方の挨拶。
そして八坂神社の神職さんの講話です。
御祭神などの話ですが、聴衆は皆さん1級合格者です。
内容も通常の説明のさらに上のレベルです(笑)。
これらで14:00前。
本殿に移動して、14:00から15分程度で正式参拝です。
そして30分ぐらいで本殿内部の拝観ですが、3/16に来たのと同じことでした(笑)。
もちろん2回とも十一面観音像の御厨子は開けて頂いておりません。
15:00前から交流会です。
いろいろな方とお話しましたが、時間も短かかったので奥がどのぐらい深いのかは計り知れませんでした(笑)。
結構遠方の方もおられたのですが、そういう方々はなかなか拝観に上洛するのもままならないご様子でした。
”早朝桜”とかやっている自分はつくづく恵まれていると思いました。
そうそう、当然その場でもこのブログの宣伝は致しました!
また濃い!?読者の方が増えたかもしれませんね(笑)。
16:00過ぎに中締めとなったので、朝から置き去りの妻子の元へと帰りました。
アンケートを実施しています。
左サイドバーにあります。
携帯の方はココ。
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 8 ) | Trackback ( )
本日から交通ICカードが共通化へ

写真は、ICOCA(上)とSUICA(下)
さて本日から以下の交通カードが共通化されます。
Kitaca(JR北海道)
PASMO(株式会社パスモ)
Suica/モバイルSuica(JR東日本)
manaca(株式会社名古屋交通開発機構/株式会社エムアイシー)
TOICA(JR東海)
PiTaPa(株式会社スルッとKANSAI)
ICOCA(JR西日本)
はやかけん(福岡市交通局)
nimoca(株式会社ニモカ)
SUGOCA(JR九州)
要するにこのブログ的には、これらのカードが京都でも使えるのです。
僕も東京出張などがあるのでSUICAも持っていましたが、無用の長物となりそうです。
し・か・し、これらのいずれかさえあれば、京都で切符要らずかというとそうではなのです。
なんとIC対応になっていない交通機関があるのです。
それは、
市バスなどバス全般
と
叡山電鉄
です。
それ以外(JR、阪急、京阪、近鉄、嵐電、地下鉄)は大丈夫です。
詳細は、
・京都での交通カード
です。
アンケートを実施しています。
左サイドバーにあります。
携帯の方はココ。
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 14 ) | Trackback ( )
京都検定1級の勉強法15 最終(点数を取るための戦略)

写真は、1級の試験結果通知
具体的に今回の僕の点数を分析します。
第9回の京都検定の結果は、135/150(90%)で合格でした(120点、8割以上が合格)。
僕の失点15点の内訳は、
テキスト内の出題での失点:5点
テキスト外の出題での失点:10点
でした。
また全出題のうち、テキスト内の出題と思われるものは130点でした。
これら合わせると、
テキストだけを完璧に覚えれば130点は取れるハズ。
しかし僕はテキスト内の出題で5点を失点している。
なのでテキスト内の出題での得点は125点。
実際には135点を取っているので、
「テキスト外の出題で10点取った」ということになります。
以上より京都検定1級で点数を取るには、
・テキスト内の出題の失点を最小限にする(僕の場合は125/130で正解率96.2%:実はこれだけでも合格点。)
・テキスト外の出題で可能な限り得点する(僕の場合は10/20で正解率50.0%)
という2つの要素があるといえるでしょう。
まずは前者について。
基本的にはテキストの暗記だけでも合格できます。
しかしテキストだけで勝負すると仮定すると、合格点数/テキスト内の出題点数=120/130=92.3%以上の精度で正解しないと不合格という計算になります。
一方で後者で20点満点を取ったと仮定しても(まずムリですが)、テキスト内の出題で100/130=76.9%以上の正解率は最低限必要です。
京都検定1級の合格において、
テキストを完璧に暗記するのは、最低限の条件
と捉えていいでしょう。
”テキストを完璧に暗記する”というのは、巻末の年表もです。
実際第9回でも、この年表の中からも出題されています。
次は後者です。
僕のように普段これだけ拝観をして、初期にあれだけ本を読んでも20点中“10点”です。
いかにテキスト外から意図的に得点するのが困難かが分かります。
正直テキスト外の出題での得点は計算できないです。
しかし正解すればそれだけセーフティーマージンが拡がることは間違いないでので、初期に最大限の対策をしておくのが賢明でしょう。
またその年の時事ネタが必ず1~2問は出題されるので、新聞などをこまめに見ておくと役立ちます。
結論
もっとも堅実な戦法は、
初期にテキスト外の知識を蓄えておき、
中期でテキストを暗記して得点を効率的に増やし、
直前期ではそのテキストの暗記での失点を徹底的に減らす
ことだと思います。
今後京都検定1級にチャレンジされる方は、参考になりそうなところは是非活用して頂いて、難関をクリアしてください。
その暁にはご一報を頂けるとうれしいです(笑)。
その他の索引
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 13 ) | Trackback ( )
京都検定1級の勉強法14 直前期(試験2週間前)

写真は、自分ノート
もう直前期です。
残り2週間。
直前期に大事なのは、テキストの出題からの“失点を減らす勉強”をすることです。
一般的に“勉強”というと、中期の“得点を増やす勉強”を連想すると思いますが、
こと“点数を取る”ということに特化すると、ここからはこの“失点を減らす勉強”が非常に重要です。
3級と2級の際にも書きましたが、“直前期に新しい情報を中途半端に入れるのは害”です。
理由は、事ここに至って「新たな内容から得点できる確率は非常に低い」のみならず、
「今までやってきた分野での取りこぼし」は意外と多いものなのです。
ここからはただただ、失点を減らすことだけを考えます。
まずは問題と解説の中に付けた例の印のうち×、△があるものだけを記述式で解きました。
それなら問題は1/4以下でしたので、1日に1冊をこなせました。
そして残り時間は“自分ノート”で、“思い出しおよび漢字の練習”です。
これらが終わって6日前。
ここから先はもう“自分ノート”を見て“思い出す練習のみ”しました。
もはや漢字も確認しません。
最後の最後は「あれっ、アレなんだっけ」となるのだけを封じにかかりました。
仮に漢字を間違えても半分の1点は貰えるようなので、少なくともそこは拾う対策です。
何故ならば”全く知らない問題を間違える”よりもなによりも、”勉強したハズの答えが出てこない”のが1番後悔するからです。
勉強のポイントは、
・最初は足腰を鍛え、細かい対策に走らないこと(テキスト外を意識する)
・だんだんとテキスト、問題と対策の精度を上げていくこと(テキスト内から効率よく得点を増やす)
・試験直前に仕上がりのピークを持ってくること(テキスト内の失点を減らす)
でしょう。
大事なのはこの期間配分は「僕自身が自分の力や環境を加味して配分した」ものですので、みなさんそれぞれに至適期間は異なると思われます。
そのあたりは各自で調整が必要です。
しかしあまり早期に仕上げてしまうと、力のピークを維持できなくなったり、”先行しているという安心”から油断することになります。
自分でも焦ってギリギリだと思うぐらい追い込んだ方が、集中も出来てより良い結果につながりますし、またその厳しい状況を乗り越える精神力が最後は必要です。
そもそもまともな試験なら、たとえ上位合格者であっても”順調に””楽に”合格はしてはいないでしょうし、またそれぐらいの危機感がない時点で”アウト”です。
競馬も試験も「第4コーナーを曲がった直線から」が本当の勝負です。
京都検定1級の勉強法15へ
その他の索引
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 3 ) | Trackback ( )
京都検定1級の勉強法13 中期(試験2か月前)

写真は、問題集
さて10月です。
中期になりましたので、そろそろピッチを上げます。
中期に大事なのは、テキストの出題からの“得点を増やす勉強”をすることです。
”得点を増やす”のなんか当り前と思われるかもしれませんが、その意味は明日分かります。
ここに至ってまだ問題と解説に手を付けていないので焦りますが、それぐらいでちょうどいいです。
今回は第9回目でしたので、過去問が8回分。
これを3級2級も選択肢を隠して記述式で、1週間に1冊ずつ解きました。
ですからこれらを解き終えたのが8週間後の11/22でした。
今回も例の4つの印をつけます。
○:正解(漢字も)
□:漢字間違い
△:思い出せそうで出て来ない
×:全く分からない
としました。
大体、1週間のうち月火で3級、水木で2級、金で1級を解いていました。
どうしても終わらない場合は土日に持ち越しました。
残り時間は、いやむしろこちらの方がメインですが、必死でテキスト通読の2回目です。
この時は漢字も相当意識して覚えにかかりました。
正直この頃が1番ツラかったです。
しかしこの時期での
テキストの暗記の精度が合否を大きく分ける
と言っても過言ではないのでしょうがないです。
この時期にテキストからの出題で”得点を効率よく増やす”のが合格への最短ルートでしょう。
11/22を目指してひたすら頑張りました。
そして11/23の第1回アマデウス会。
実は個人的に“ちょっと打ち上げ”状態でした(笑)。
京都検定1級の勉強法14へ
その他の索引
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 7 ) | Trackback ( )
京都検定1級の勉強法12 初期11(京都がわかる250問とテキスト通読1回目)

写真は、京都がわかる250問とテキスト
淡交社 小嶋一郎、読売新聞京都総局著
おすすめ度☆☆
“もっと”と“さらに”の2冊があります。
3級や2級と同じ4択ですが、問題はかなりのレベルです。
まあ難しいこと。
でも1級を受けるならば、これぐらい1度は掘り下げてもいいかなというレベルです。
この問題を9月から始めました。
一方でそれと並行して、1回目のテキストの通読を始めました。
1回目は覚えず、専ら読むことに専念しました。
最初から全部覚えようとすると進まないからです。
まずは”敵の全貌を偵察する”感じです。
しかし初回で大事にしたのは“一言半句読み飛ばさない”こと。
音読で全文字を読みました。
くれぐれも最初から全部を覚えようとしないことです。
この問題集と1回目の通読で9月は終わりました。
京都検定1級の勉強法13へ
その他の索引
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 8 ) | Trackback ( )
京都検定1級の勉強法11 初期10(きょうの京都)

写真は、きょうの京都
紫紅社
おすすめ度☆
これは365日のカレンダー形式で、京都の催事が説明してあります。
しかし365日は量が多いです。
イベント自体は覚えられても、一気に読むと肝心の日付が入ってこないです。
催事の知識は、テキストの最後にあるの催事の表と、問題と解説で出てきたものを“自分ノート”に書き出したものだけで十分でしょう。
それならこの本の1/3程度にはなりますし、逆にそれだけを完璧にした方が点数になるでしょう。
ここまでを8月末に読み終えていました。
目次
1月 初詣、都七福神まいり、通し矢、初天神
2月 湯立神事、節分、初午大祭、五大力尊仁王会、梅花祭
3月 雛祭、釈迦涅槃図、嵯峨のお松明、はねず踊り
4月 都をどり、やすらい祭、十三詣、壬生大念仏狂言、曲水の宴
5月 千本ゑんま堂狂言、駆馬神事、皐月の床、葵祭、三船祭
6月 京都薪能、県祭、竹伐り会式、夏越の祓
7月 祇園祭、七夕、祇園祭山鉾巡行、きゅうり封じ
8月 八朔、六道まいり、五山の送り火、千灯供養
9月 烏相撲、石清水祭、観月の夕べ
10月 ずいき祭、二十五菩薩お練り供養、時代祭、鞍馬の火祭
11月 亥子祭、お火焚、京の紅葉、まねき上げ
12月 吉例顔見世興行、大根だき、煤払い、終弘法、除夜の鐘
京都検定1級の勉強法12へ
その他の索引
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 11 ) | Trackback ( )
京都検定1級の勉強法10 初期9(みやこの近代)

写真は、みやこの近代
思文閣出版 丸山宏、伊従勉、高木博志編
おすすめ度☆☆
京都の近代について、政治、芸術文化、風俗などが見開き1ページで書いてあります。
個人的な問題かもしれませんが、近代史って苦手なんですね。
歴史の勉強でも最後の方なのでうやむやになってくる反面、新しいからこそ分かっている事実も多く、出題する気になればネタは無尽蔵です。
この弱点を矯正する目的でした。
個人的には役に立ったのですが、皆さんもそうなのかが疑問だったので☆☆にしました。
僕のように“近代史が苦手”な方にはおすすめですが、他の書物に比べるとカタイ内容ですので、読破するには気合が必要です。
目次
プロローグ
まちのインフラ
まちのイメージと環境
まちの建築
美術と工芸
なりわいと政治
まつりと世相
京都帝国大学
みやこの海外
エピローグ
京都検定1級の勉強法11へ
その他の索引
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 6 ) | Trackback ( )
由緒書きコレクション6(妙心寺 隣華院)

写真は、隣華院の由緒書き(ほとんどお墓の募集)と半券
さて今回は妙心寺塔頭の隣華院です。
通常は非公開、定期的な公開もなく、2012年の京の冬の旅で公開された時のものです。
半券は拝観の際に貰えますが、この由緒書きは確かひとこと声をかけて頂いたように思いますが定かではないです。
裏表で6ページ!?分ですが、由緒が書いてあるのは1枚だけで、あとはお墓の募集です(笑)。
まあそれでも「なにもお土産がないよりはいい」と思うのは、由緒書きコレクターの性でしょうか(笑)。
希少価値レベルは4ですね。
しかしこのお墓の募集なら普通に行っても貰えそうな気もしますが・・・。
次回の”由緒書きコレクション7”は、2/15の22:00の予定です。
希少価値レベル:由緒書きの入手困難さによる分類
レベル1:拝観すれば自然に手に入るもの
レベル2:ちょっと声をかければ、誰でも手に入るもの
レベル3:定期的な特別拝観でなら、手に入るもの
レベル4:稀な特別拝観でないと手に入らないもの
レベル5:特殊な状況でしか手に入らない、超レアもの
アンケートを実施しています。
左サイドバーにあります。
携帯の方はココ。
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 3 ) | Trackback ( )
京都検定1級の勉強法9 初期8(あさきゆめみし 全13巻)
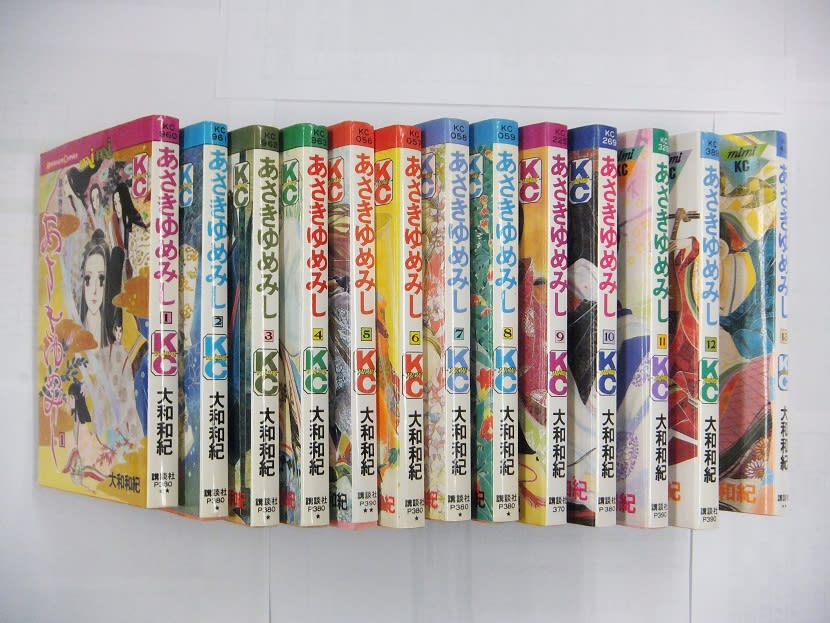
写真は、あさきゆめみし 全13巻
講談社 大和和紀
おすすめ度☆☆
これは有名でしょう。
源氏物語の漫画です。
源氏物語関係の問題はほぼ必ず出題されるのですが、非常に苦手意識がありました。
しかし源氏物語のオリジナルを通読するわけにもいきません。
そこでこの漫画の登場です。
本当に目的のために、手段は選びません。
読んでいるのを妻に見つかった時は、「どうしたん!?」と聞かれました(笑)。
そらそうですね。
そもそも普段は漫画を一切読まないオッサンが、少女マンガを読んでいるんですから。
姉が中学生時代に読んでいたのを思い出し、実家に急行し回収しました。
しかし途中の3巻ほどが“行方不明”だったので、それらはアマゾンで補充しました。
もちろん大事なのは自分が今読んでいるのが、オリジナルのどの巻なのかを意識して読むことですね。
僕はこれで源氏物語の問題に対する苦手意識はなくなりました。
京都検定1級の勉強法10へ
その他の索引
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 7 ) | Trackback ( )
由緒書きコレクション5(大徳寺 孤篷庵)

写真は、1回目の特別公開で購入した絵葉書と2回目の際の資料
まずここに初めて拝観したのが2011の秋の非公開文化財特別公開でした。
その際に「由緒書きはありますか?」と尋ねると、「由緒書きってものはないですが、この絵ハガキセットの外袋に由緒が書いています」と言われました。
孤篷庵ですからね。
”拝観した証”が欲しい。
次いつ入れるか分からないので、当然購入しました。
それが写真の②~⑦です。
まず②がその外袋です。
③は拝観した方はご存知の”忘筌席”ですね。
そして絵葉書をめくると④~⑦が出てきたのです。
「ここは知らないぞ!」と思い孤篷庵について調べると、2011の秋に公開していない”直入軒”や”山雲床”があることに気付いたのです。
以降はなんとかして”直入軒”、”山雲床”がみたいと探しに探した結果、NHKカルチャーの茶室探訪の講座(現在休講中)に辿り着いたのです。
この講座での孤篷庵で、晴れて拝観できました。
その際に頂いた資料が①です。
④と⑤は書院の前庭で、”忘筌席”からは上の襖で見えなくなっている向こう側にあたります。
そして”忘筌席”の手前座の右手奥に⑦の”直入軒”が、さらに右隣に⑥の”山雲床”があります。
いずれも普通には手に入らないので、希少価値レベルは5ですね。
これらも誰にも譲れない宝物です(笑)。
希少価値レベル:由緒書きの入手困難さによる分類
レベル1:拝観すれば自然に手に入るもの
レベル2:ちょっと声をかければ、誰でも手に入るもの
レベル3:定期的な特別拝観でなら、手に入るもの
レベル4:稀な特別拝観でないと手に入らないもの
レベル5:特殊な状況でしか手に入らない、超レアもの
アンケートを実施しています。
左サイドバーにあります。
携帯の方はココ。
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 2 ) | Trackback ( )
京都検定1級の勉強法8 初期7(図説 歴代天皇125代)
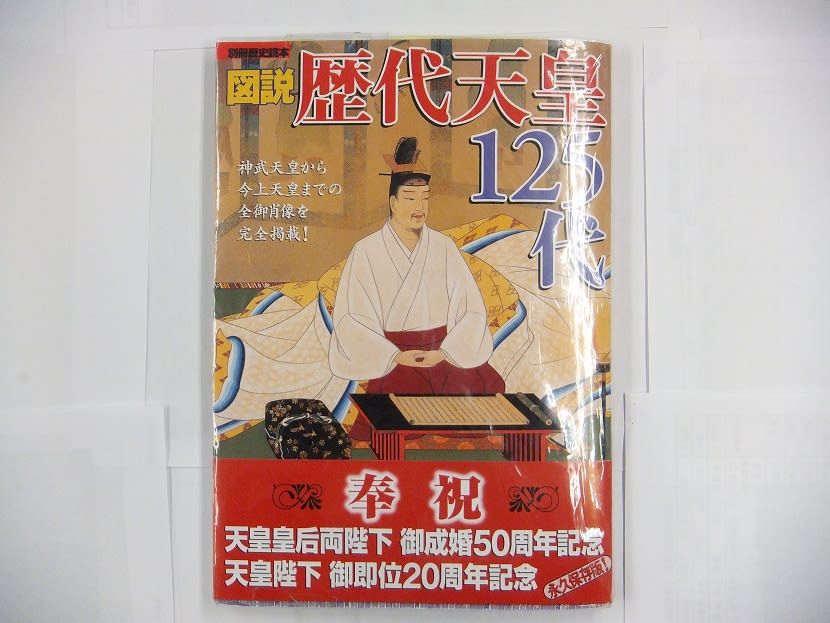
写真は、図説 歴代天皇125代
新人物往来社 別冊歴史読本
おすすめ度☆
歴代天皇の解説本です。
寺社の拝観の立て看板を見ていると、よく天皇の名前が出てきます。
しかしよく知らないと、いつの時代かすら分からなくないでしょうか。
例えば光孝天皇、光厳天皇と光格天皇では時代が全然違います。
それに業を煮やしたamadeusは、第50代 桓武天皇から第125代 今上天皇までのすべてを覚えたのです。
これで京都の歴史の時系列を追う1つの軸が出来ます。
拝観先の立て看板でいかなる天皇名が出てきても、時代軸が即座に定まります。
ただし覚えるのは重労働ですけどね(笑)。
もちろん覚える際には、“字面を丸暗記するのではない”です。
この本にある解説を読むと、なぜこの天皇が即位したのかという歴史的背景が見えるのが面白くもあり、むしろそれが勉強になるのです。
しかし僕も極端な性格ですので、第50代 桓武天皇以前はページを開いてもいません(笑)。
他にも歴代天皇の本はありますが、この本は肖像画の写真がメインで文章が長くないです。
写真で各天皇のイメージ付けをして、サラッと文章が読めるのでお手軽です。
どの道、歴史知識の足腰を“強靭に”鍛えたい人向けですね。
目次
古代天皇家の御肖像
中世動乱の闘う天皇像
徳川将軍家と天皇家
明治・大正・昭和・今上天皇の御肖像
京都検定1級の勉強法9へ
その他の索引
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 30 ) | Trackback ( )
由緒書きコレクション4(志明院)

写真は、志明院(しみょういん)の由緒書きの表裏
まず「志明院ってどこ?」という声が聞こえてきたので(幻聴!?(笑))。
鴨川は出町柳以北で賀茂川(左側)と高野川(右側)に分かれており、Y字になっているのは有名でしょう。
この右側の高野川をぐんぐん上流に進むと、大原があります。
今度は左の賀茂川をぐんぐん上流に進むと、また左右の2手に分かれます。
この右側はY字の真ん中奥に進んでいき、鞍馬・貴船に至ります。
さてではさらに左側奥に進むとなにがあるのか?
そうです、そこにこの志明院があるのです。
鴨川の源流、桟敷ヶ岳の麓です。
メチャ遠いです。
本編のマイナー散策には未掲載ですが、拝観報告はあります。
さて肝心の由緒書きです。
表はカラー、裏は白黒。
由緒、見所の解説と模範的な由緒書きです。
チャラチャラしていなくて、僕が最も好感を持てる種類です(笑)。
これは拝観時に頂けるので、希少価値レベルは1になりますが、
それ以前に「ここまで来てみろ!」ってことで、今回のレベルは”1.5”にしておきます(笑)。
お寺のお話になりますが、夏は涼しく、貴船のように人が多くなく、観光地化されていないところが非常にいいです。
是非思い切って夏の避暑に行かれてみてはどうでしょう。
ここには今までと”一味違う京都”があります。
希少価値レベル:由緒書きの入手困難さによる分類
レベル1:拝観すれば自然に手に入るもの
レベル2:ちょっと声をかければ、誰でも手に入るもの
レベル3:定期的な特別拝観でなら、手に入るもの
レベル4:稀な特別拝観でないと手に入らないもの
レベル5:特殊な状況でしか手に入らない、超レアもの
アンケートを実施しています。
左サイドバーにあります。
携帯の方はココ。
「京都のおすすめ」の総合索引へ
コメント ( 14 ) | Trackback ( )
| « 前ページ | 次ページ » |
 -泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札
——
-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札
——
 -火伏せ・防火(ブログ炎上防止)”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—
---------------
-このブログの見方
22:00に自動更新。
-
22:00は拝観報告。
--タイトルに訪問日時が入っているもの。--
内容は最近の拝観の--主観的な感想です。
----------------------
拝観報告がない時は、本編。
----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。-
内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。
-火伏せ・防火(ブログ炎上防止)”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—
---------------
-このブログの見方
22:00に自動更新。
-
22:00は拝観報告。
--タイトルに訪問日時が入っているもの。--
内容は最近の拝観の--主観的な感想です。
----------------------
拝観報告がない時は、本編。
----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。-
内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。