歯が痛くて二晩寝られなかった。本日は東海市への視察を断り、歯医者へ出かけた。歯の深いところで化膿しているということで治療してもらい、今はずいぶん楽になった。
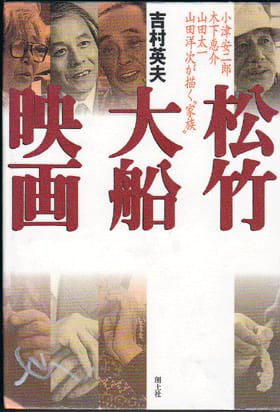
図書館の本「松竹大船映画」吉村英夫著 創土社 に小津安二郎のことが載っていたので、先日の文化の駅サテライトステーション事業のプレゼンで紹介しました。その文面を掲載いたします。
小津は生涯かけて、人の世がめんめんと続く姿を、親子、兄弟、夫婦にしぼって描きつづけた。家族の生成から別離、またの生成を、無常の相でみつめた。スタンダードザイズの小さな画面に、たった一人の人物が映るショットを多用し、孤独に生きる人と人とはつながりにくいが、悲しく寂しい宿命に耐えねばならないのだと説いた。だとすれば、小津の映像は暗く重いものになりそうである。だが、小津映画はいうほど暗いだろうか。そんなに暗い印象を観客に与えるのか。そうではない。むしろ逆である。(中略)
そう、小津映画を見ての印象は暗くない。巧まざるユーモアと深い情緒は、むしろ温かい。観客は究極の家族の姿を画面の奥に感じて、寂しいながらも、芸術作品に接したとする至福の瞬間を味わう。それが小津映画である。(中略)
突き放した人生観照の態度で人間を描いているようでありながらも、画面には人懐かしさがにじみ出る。どうしてか。そう、小津の人間存在への限りない思いがこもるからである。人間への愛(いと)おしさがあるから、映像から滋味あふれた人間的香気が漂うのである。
吉村英夫氏のこの言葉は、特に戦後、世界の小津と言わしめた作品群、その魅力の真髄を言い当てているようです。「東京物語」「秋刀魚の味」「晩春」「麦秋」「秋日和」どれもみな人生の孤独感が切々と迫ってくる、にもかかわらず、ほのぼの、しみじみとなんども観たくなるのは、このあたりに原因があるようでアリマス。
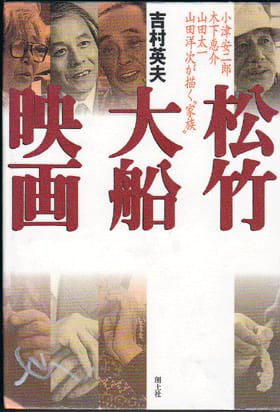
図書館の本「松竹大船映画」吉村英夫著 創土社 に小津安二郎のことが載っていたので、先日の文化の駅サテライトステーション事業のプレゼンで紹介しました。その文面を掲載いたします。
小津は生涯かけて、人の世がめんめんと続く姿を、親子、兄弟、夫婦にしぼって描きつづけた。家族の生成から別離、またの生成を、無常の相でみつめた。スタンダードザイズの小さな画面に、たった一人の人物が映るショットを多用し、孤独に生きる人と人とはつながりにくいが、悲しく寂しい宿命に耐えねばならないのだと説いた。だとすれば、小津の映像は暗く重いものになりそうである。だが、小津映画はいうほど暗いだろうか。そんなに暗い印象を観客に与えるのか。そうではない。むしろ逆である。(中略)
そう、小津映画を見ての印象は暗くない。巧まざるユーモアと深い情緒は、むしろ温かい。観客は究極の家族の姿を画面の奥に感じて、寂しいながらも、芸術作品に接したとする至福の瞬間を味わう。それが小津映画である。(中略)
突き放した人生観照の態度で人間を描いているようでありながらも、画面には人懐かしさがにじみ出る。どうしてか。そう、小津の人間存在への限りない思いがこもるからである。人間への愛(いと)おしさがあるから、映像から滋味あふれた人間的香気が漂うのである。
吉村英夫氏のこの言葉は、特に戦後、世界の小津と言わしめた作品群、その魅力の真髄を言い当てているようです。「東京物語」「秋刀魚の味」「晩春」「麦秋」「秋日和」どれもみな人生の孤独感が切々と迫ってくる、にもかかわらず、ほのぼの、しみじみとなんども観たくなるのは、このあたりに原因があるようでアリマス。
















