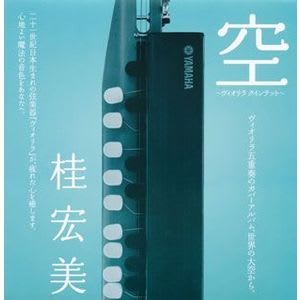高木仁三郎については当広場では、2011年5月10日に一度紹介させていただいた。
晩年、1999年の作、『市民科学者として生きる』は、先見的な原子力への警鐘の他に自身の人生の総決算的な死生観もあり興味深い。「来世の生まれ変わりは信じないから、自分から打って出て、私の命を次の世代へとつないでいくことができるのではないか。“生前葬”という考えがあり実行している人はいるが、もっと積極的に考えているつもりだ。」
「高木学校」や「原子力資料情報室」を設置し、後進の育成に力をそそぎ、現世において研究のみならず実践的な生き方を果たしたのは見事です。
「原風景」は7歳の時の前橋空襲だったと言う。疎開先から見た前橋の空はまるで「花火のよう」だった。私も旧富士見村に住んでいたという義母から空襲は「花火のよう」の話を聞いていた。国民学校(前橋中川小)1年生の高木少年は、空襲の他に終戦のこの年、夏休みの前と後では教育内容がガラッと変わった教師の言葉に接した。同じ教師の口から「日本は神国、英米は鬼畜と教えられていたのが、夏休み明けには「あの戦争は軍人が仕組んだ野蛮な戦争だった。これからは民主主義、米軍は解放軍」・・
大人たちが嘘っぽく、卑屈に見えた。軍人たちの潔い切腹もなかった。国家やお上は信用できないという認識は天童だった仁三郎君にはするどく感じ取れたようだ。
宮内庁からも問い合わせ
現在も活躍している高木仁三郎が主宰の原子力資料情報室。チェルノブイリ原発事故(1986年)時の日本の科学技術庁や厚生省は、今とまったく同じで「安全」をただ繰り返すばかりでデーターは公表しない。同情報室だけが公共的な役割を果たしていたという。そんなある日、宮内庁から食品汚染の問い合わせがあったという。
なぜ緑の党的な市民政党が伸びないのか
日本で緑の党的な市民政党が育たない理由を、高木仁三郎は日本の市民運動家が一匹狼主義、小異にこだわってしまい大きくまとまりながらもそれぞれの個性を維持することができない、自らのアイデンティを大切にすると結局まとまることを止めてしまう・・
とても紹介しきれないほど本書の高木仁三郎の言葉は重い。前橋出身者には、戦後当時の郷土前橋の情景描写にあふれ、懐かしさもひとしお感じることができます。ぜひご一読を。(敬称略)
おすすめ動画 反原発 市民科学者高木仁三郎
反原発 市民科学者高木仁三郎
| 市民科学者として生きる (岩波新書) | |
| 高木仁三郎著 | |
| 岩波書店 |