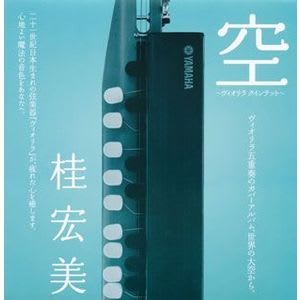群馬県大泉町は広報紙で、町内の公園、幼保育園、小中学校など公共施設の放射線量を測定し公表しました。測定場所、地表、地表50㎝、1mの3位置点。使用した測定器も明示、日本製(堀場製作所)の定評のある線量計。
38場所のうち、3位置点のうちいずれかでも年間1ミリシーベルトを超えたところは15場所。年間1ミリシーベルトは、人工放射線からの公衆被曝の線量限度、日常生活を除いて人が浴びる上限のこと(ICRP基準)。
今回の公表結果は、私が2つの測定器で自己流ランダムに測った数値とそう大差はなく十分に信頼できます。
広報紙の見出し、「結果は基準値以下でした」にいつわりは有りません。「基準を大きく下回った」の記述も正しい。しかしそもそも現在、国の定めている線量低減策を実施する基準値「毎時1.0マイクロSV」自体がかなり甘い。年間に換算すれば8.76ミリSVにもなる。チェルノブイリ事故では年間5.0ミリSVで避難勧告区域指定であったことを思うと・・。
それでも今、住民が不安に抱いている放射能汚染の影響について、38施設等(各3地点)にも渡って丁寧に測定したことは高く評価できます。近隣でもここまで細部にわたって測定結果を示した自治体は少ないと思う。
「広報紙」の役割である「PR(パブリックリレーションズ)の力(ちから)」は住民との結びつき、相互理解、信頼建設にあります。このことはすべてのメディアにも通じること。大新聞が、大衆受けを狙って“ただちに健康に被害はない”論調の気休め・安心記事ばかりで埋め尽くしているのはPRの精神に沿ったものではありません。企業広報では、厳しいリストラの記事を事前に、正確に社員に知らせることにより労使の一層の信頼関係が保たれます。このことは国家と国民の間でも言えることです。
真実の情報は、それが一瞬過酷な内容であっても素早く報知することで、情報を得た国民が適切な次善のアクション(行動)をとることにつながり、結果的に必ず有益なものとなります。その反対に重要情報の公開を渋ったことで被害が拡大してしまったことは、今回の大震災原発災害でも残念ながら露呈されてしまった。
「尖閣ビデオ」を公開した勇気ある元海上保安官の一色正春氏の言葉を思い出します。先の大戦で「もし大本営(国)が国民に迅速に正確な戦況を報じていたら果たして広島、長崎の悲劇はあっただろうか・・」と情報独裁による国家的なマイナス面を指摘されていた。
話が飛びましたが、町民の一人として数値をきめ細かく公表した大泉町紙「おおいずみ」の広報姿勢には拍手を送ります。
【写真】「おおいずみ」2011.9.10号表紙