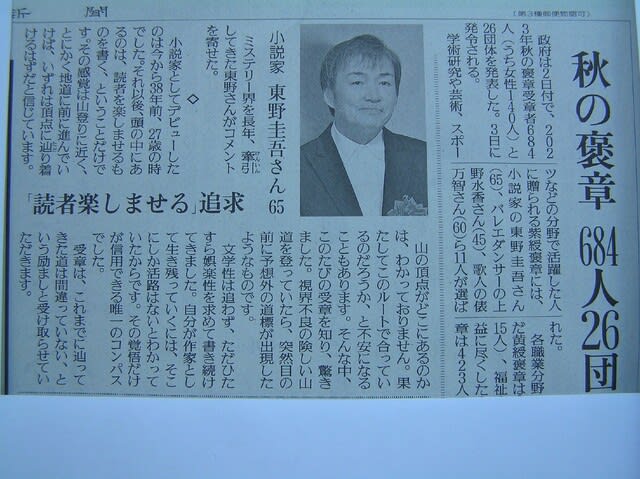はてさて、他県からお見えになったお客さんをどこにご案内しようか・・、となると本県ではまず「宇佐神宮」で決まり~。
なぜ?
「宇佐神宮は、大分県宇佐市にある神社。 全国最多の約44,000社ある八幡宮の総本社である。石清水八幡宮・筥崎宮と共に日本三大八幡宮の一つ。古代においては伊勢神宮と共に二所宗廟として扱われた。八幡宇佐宮または八幡大菩薩宇佐宮などと呼ばれた。
国東半島に広がる神仏習合の山岳信仰・六郷満山文化と深い関わりを持っており、太古からの原生林に囲まれた広大な境内は澄んだ空気に包まれ、八幡造の3棟の本殿(国宝)をはじめ、神橋、呉橋(くれはし)、能楽殿、宝物殿など、歴史的・文化的に貴重な建築物が立ち並ぶ。
樹齢800年のご神木や、踏むと幸せになる「夫婦石」、ハートの形をした建造物の文様「猪目」などが点在。恋愛成就や縁結び、商売繁盛など所願成就にご利益があって、全国各地から多くの人が訪れます。春には約500本のソメイヨシノが、夏には蓮の花が咲き誇り、四季折々の風情を楽しむことができる。」
というわけで、何しろ全国の八幡宮の総本社である。
広大な敷地、威容を誇る神殿を目の当たりにすると、思わず神のお加護にすがりつきたくなるほど。
しかし、なぜこんな栄えある神宮が九州の片田舎にあるかというと、大きな謎に包まれている。
で、去る8日(水)は横浜から来た高校時代の同級生「T」君を「宇佐神宮」に案内した。7日の我が家での「試聴会」は詳述したとおり。
当日は、雲一つない秋の青空が天井知らずのようにどこまでも透き通っていてまるで吸い込まれそう・・、まさにモーツァルトの音楽みたいだった(笑)。
別府からクルマで1時間ほどで到着。
平日とあって、やや閑散としていたがそれでも他県からとおぼしきグループがちらほら~。
「どちらからお見えになったのですか?」「ハイ、静岡県です」「ハイ、(神奈川県の)相模原です」といった具合。
玄人はだしのカメラマン「T」君が写真を取ってメールで送ってくれた。

なお、凄い美人を見かけたのでT君に「ぜひ写真を撮らせてもらおうよ」と、唆して「写真を撮っていいですか」と交渉してもらったところ、ご快諾。
トルコ人で現在は「ドバイ」に住んでおられるとのことだが、実に流暢な日本語だった。
すらりとした長身のスタイル、彫りの深さといい、肌の色艶といい、実物のほうが写真よりもずっと「魅力的」だったことを力説しておこう(笑)。
で、結局この日は宇佐神宮にすっかり時間を取られたので、その後の予定を変更して海沿い周りの「国東半島一周」コースへと切り替えた。
この日の走った距離は150Kmで、15時31分発(博多駅行き)の電車に間に合い、別府駅で見送った。
「来年の5月には2泊3日の日程で来たいのでよろしく・・」
「ああ、いいよ~」
クリックをお願いします →