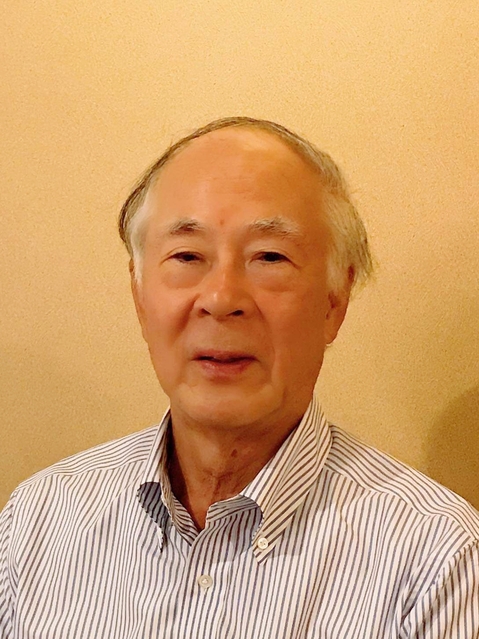菅首相の挫折で読み筋が狂う
2021年9月11日
総合月刊誌の雄を自認する月刊文芸春秋10月号は、雑誌研究史に残る大失態を演じました。菅首相をめぐる総裁選という大テーマを満載したところ、少なくとも3本が不発弾ないし誤爆となりました。
文春は10月号から、新聞時評「新聞エンマ帳」を復活させ、「コロナの無責任報道を叱る」という記事を載せました。タイミングが悪いことに、肝 . . . 本文を読む
閉幕しても五輪問題は終わらない
2021年8月9日
東京五輪では、競技場内の選手たちの躍動美の素晴らしさに酔いました。一方、競技場外の運営では、多くの問題が浮上し、多くの論点が浮き彫りになりました。五輪史上に残る大会となるでしょう。
運営側の不祥事の多発、コロナ危機、猛暑、政治的な思惑、経済的収支、開催都市の負担軽減、IOCの絶対的な権限への批判など、論点は拡散して . . . 本文を読む
大谷絶賛の裏には米球界の計算
2021年7月19日
大相撲名古屋場所で、6場所連続休場明けの横綱白鵬が45度目の優勝を飾りました。新聞は「白鵬の伝説まだ続く」「白鵬鬼の形相」(読売新聞)と、絶賛しました。白鵬と準優勝の照ノ富士は2人ともモンゴル出身です。
日本人力士は大関貴景勝が4日目から休場、同朝乃山は全休、関脇高安は2休、前頭筆頭の遠藤は10休でした。上位力士が . . . 本文を読む
質問の選択肢を意図的に調整
2021年6月1日
国際オリンピック委員会(IOC)、日本政府・組織委員会はコロナ危機に対する非常事態宣言の有無に関わりなく、東京五輪を強行開催する構えです。後戻りできないところに自らを追い込んでいく作戦です。
朝日新聞が社説で、開催中止求める一方、広告収入などの経営的な見返りが大きいスポンサー(協賛社)契約は破棄しないと表明しました。腸 . . . 本文を読む
「経営と編集」の二分法を逆用
2021年5月27日
朝日新聞が社説で「東京五輪中止の決断を首相に求める」(26日)を書きました。五輪のスポンサー(協賛企業)の新聞社としては、初めて「中止」を表明し、海外でも関心をもって報道されています。
社説は「中止」でも、今後も「オフィシャル・パートナー(協賛企業)を務める。五輪に関わる事象を公正な視点で報道していく。オフィシャル . . . 本文を読む
開催中止をとまでか書かない
2021年5月13日
最新のNHKの世論調査では、菅政権の支持率は35%まで下がり、不支持率は43%に上がり、不支持率が支持率を上回りました。読売の調査でも、支持率が43%、不支持率が46%で逆転しています。
3月の支持率が9㌽も上昇(2月比、読売)した時、菅首相は上機嫌で「官邸執務室に入るや否や、『ほらみろ。こんな難しい時期に俺以外の誰も . . . 本文を読む
商業五輪の協賛企業となった新聞の限界
2021年5月9日
民主主義社会に不可欠な言論機関を自認しているメディア、特に新聞の東京五輪に対する論調は優柔不断です。開催国の言論機関であるからこそ五輪中止論を率先して提言すべきなのに逃げています。
「無理に開催すれば、ごたごたが続く。開催中止の決断のほうが菅政権にとって大きな政治的功績になる」と、主張したらよい。強行開催より、 . . . 本文を読む
失われる新聞の中立性
2020年12月18日
全国紙の中では、日経新聞はまともな新聞だと思ってきました。それが今週、無残に打ち破られました。記事と広告ともとれる企業広告・特集を満載する前代未聞の編集方針が異様です。新聞離れを自ら招いているのに等しく、日経の経営者に猛省を求めます。
一年以上、前からでしょうか。企業シンポジウムとか国際会議特集とか、やたらとシンポジウムも . . . 本文を読む
サンプリングを困難にした社会の分断
2020年11月13日
米大統領選は事前の世論調査では、バイデン氏の圧勝という予想でした。それがトランプ氏の猛烈な追い上げで、大接戦に持ち込まれ、「世論調査も大統領選の敗者」とい批判が高まっています。
前回の16年の大統領選では、多くの世論調査「クリントン氏勝利」が見事に外れました。その結果を踏まえ、調査方法を改善したはずなのに、「 . . . 本文を読む
再編や統合に見向きもしない
2020年10月23日
地方の人口減、高齢化、地域経済の低迷、ゼロ金利などで、地方銀行の経営が厳しくなり、菅政権は地銀再編に向け、環境作りを始めました。地銀より地方紙はもっと深刻なのに、危機打開の動きは感じられません。
地方紙が消滅し、「取材空白地域」となった米国カリフォルニアの小都市で、住民不在の行政が加速したそうです。議員の報酬、市職員 . . . 本文を読む
伝達するだけのリポーター
2020年10月9日
日本学術会議の会員人事問題は、菅政権と会議側が全面対決する構図になっています。学者側も一枚岩でなく、見解の対立があるようです。かれらの言い分を聞いて、どちらに分があるのか判断するのは難しい。
こういう時こそ、新聞などが判断材料を発掘して提供すべきなのです。首相の会見では、発言の曖昧模糊とした部分を粘って追及しなかったのか . . . 本文を読む
倫理より生活重視が社会の空気
2020年9月22日
菅内閣に対する支持率が予想を上回る高さに達し、世論調査では74%(日経、読売新聞)を記録しました。朝日は65%、毎日64%と、どの調査でも高く、「なぜだろう」と、驚きの声も聞かれます。
清濁いろいろだった安倍長期政権の舞台裏を仕切ってきたのが、菅官房長官で、安倍氏とは一心同体でした。メディアでは、安倍批判が噴出していたのに、そ . . . 本文を読む
視野の狭い総裁選報道にも落胆
2020年9月13日
自民党総裁選に立候補した3氏が日本記者クラブ主催の討論会に臨み、14日の議員総会の投開票の結果を待つことになりました。政策発表、政策討論を経て、各議員らが投票して、新総裁を決めるのが民主主義のプロセスのはずです。その順序が逆さまですから、高揚感のない展開です。
肝心の政策構想の発表、政策討論は後回しで、主要派閥の水面 . . . 本文を読む
最悪の危機ほど活気づく
2020年9月8日
「コロナ後の世界」(文春新書)の執筆者の1人であるピンカー・ハーバード大教授(進化心理学)は「ジャーナリズムはどんな日でも、地球で起きている最悪のことを選んで報道する。いいニュースはなかなか報道されない」と、指摘しています。
コロナ報道では特にそうでした。NHKのニュースはこの夏、連日「東京都の新たなコロナ感染者数は400人 . . . 本文を読む
ニュースの評価表示が不可欠
2020年7月16日
「何が本当か」「どちらが正しいのか」。メディアが流すニュースに接していると、こうした判断がつきかねるケースが増えています。メディアは情報を急いで流していればいい時代から、情報の評価を伴うニュースの伝達が不可欠な時代に変わりました。
米国では、SNSで投稿への監視機能を強化する姿勢に転換を始めています。「政治家や政治関係 . . . 本文を読む