 科学界の非常識
科学界の非常識
2014年8月6日
STAP細胞をめぐる不正、捏造問題は、女性研究員の直属の上司が自殺するという痛ましい展開になってしまいました。今回の新発見の捏造というか事件が、第一級の科学者に自殺という非科学的悲劇を招いた責任はどこにあるのでしょうか。また、第二の犠牲者を絶対に出してはいけないと思っている人は、すくなくないでしょうね。
この悲劇を考える視点、課題はいくつかあります。
・渦中の女性研究者に対する心身のケア。
・理化学研という組織、機構の無責任さ、問題解決を先延ばしするだけの当事者能力のなさ。
・ノーベル賞の受賞者、理化学研の理事長でありながら表に出てこないの野依氏の処遇。
・一般常識が通じそうもない科学界の非常識。
わたしのブログで何度か、STAP問題を取り上げました。科学的なことは専門家にゆだねるとして、国際的な波紋を呼んだ不祥事に、日本を代表する研究機関がどうケリをつけていくのかに関心があったからです。最近のブログでは「残酷すぎる実験参加」と題して、まずSTAP細胞が存在しないとされるようになったタイミングで、本人に再現実験に当たらせるのは、拷問みたいな扱いだ、と書きました。本人は明らかに精神的不調に陥っており、夢遊病者のようで、精神科医などのケアが必要だと、思いました。
女性研究員が信頼し、慕っているであろう直属の上司の自殺に、どんなにか衝撃を受けたか想像できます。理化研に出勤しても、実験に手がつかない状態だと、メディアは伝えています。そうでしょうね。不正、捏造の直接的原因は本人にあるにせよ、問題の解決を引き延ばしているとしか思えない理化研が、本人を窮地に追い込んでいるのです。ただでさえ残酷な仕打ちを受けているうえに、上司の自殺で心のよりどころを失い、精神的不調はさらに深刻になるかもしれません。信じられないくらい遅れたタイミングで検証実験に踏み切ったときには、外部はすでに「STAP細胞はまず存在しない。無意味な実験だ」との評価でしたから、拷問ですよ、これは。
理化研は、だれかが女性研究員に付き添い、心身のケアをしっかり行わなければなりません。上司の笹井副センター長(52)は、最近、体調が悪く、研究者との議論も成り立たず、心配した理化研は家族と連絡をとって、休養や治療の相談を始めていたそうです。そこまで把握しながら、竹市センター長は、会見で「いろんなことで非常に批判されていた。行き詰まっていた。かれにとって苦しい情勢だったことは明らかだ」と、語りました。ひとごとのような発言です。もっと親身になって心身をケアしていれば、最悪の事態は防げたかもしれません。ひどい上司です。これ以上、犠牲者をだしてはなりません。
理化研は、個人(具体的には、女性研究員、笹井副センター長ら)に責任をとらせることで、幕引きをしようとしてきたのではないか、疑いたくなります。今回の不祥事の第一の責任は、捏造と不正を繰り返した女性研究員、新発見に目がくらみ、ぬか喜びし、論文の指導で信じられない脱線を続けた笹井副センター長にあります。ライバルの山中伸也教授に対する競争意識と嫉妬心も心理の底にあったのでしょう。さらに速やかな調査、追加実験をせず、問題の決着を先延ばしした理化研の体質にも、深刻な病理があります。
そうであっても、早く調査結果をまとめ、処分をしていれば、よかったのです。つまり、さっさと、かれらを処分して退職、辞任させ、精神的にケリをつけさせ、あらたな人生選択をできるようにしておいてあげれば、特に能力が極めて高いとされる笹井氏の悲劇は回避できたかもしれません。重大な責任があり、改革委員会から退任を勧告された竹市センター長は、なにを思っているのか、映像から見るかぎり平然としています。
野依理事長も、理解に苦しむ対応ぶりですね。貴重なエースを失いながら「驚愕しております。世界の科学界にとって、かけがえのない科学者を失ったことは、痛惜の念に耐えません」とのコメントはなんでしょうか。今回の問題では、正式の記者会見には、4月ころ、確か1度でたきりで、それも、論文の書き方、研究の仕方、指導がひどすぎるというような発言でした。トップとしての指導力に責任を感じていないようでした。すくなくとも、今回の自殺では、理事長が直接、姿をみせ、哀悼の意を示すべきでした。
いずれ、理事長をやめるでしょうし、やめて責任を取らなければなりません。ノーベル賞の名が泣いていることでしょう。
それにしても、科学界は不可解、非常識なところですね。女性研究員の出身大学は、博士論文にコピー、ペーストによる丸写しが多く、「不正」と判定しながら、博士号を剥奪しませんでした。「下書きを誤って提出してしまった」との、言い訳にならない言い訳を真に受けたふりをしました。「理化研批判、渦巻く学会。異例の見解相次ぐ」(8月2日の読売夕刊)など、厳しい世論に対し、「あらたな疑義も調べている」(理化研理事)と、平然としています。感度が鈍いのか、常識がないのか。
米国は、保健福祉省に研究公正局を設け、この種の問題がおきると、調査に乗り出すそうです。各国とも、最先端の研究開発に多額の予算を投入し、国際競争を制しようとしています。そこでは、特許料、利権収入を目当ての不祥事、不正も少なくありません。カネが絡んできますから、不正というより、もう事件なのですね。科学界や理化研の当事者能力のなさを思うと、こうした機構が必要になってくるでしょう。










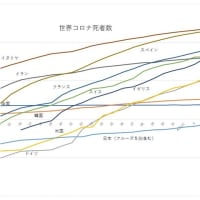









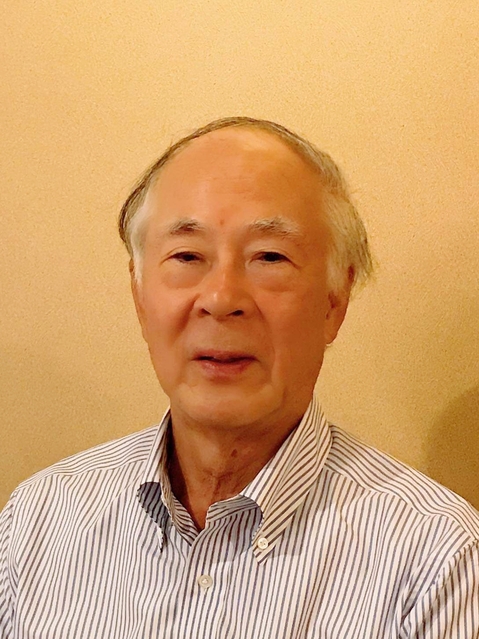

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます