安倍政権は消費者物価の上昇率の目標を前年比で2%としています。物価上昇率は景気を測る図る体温みたいなもので、デフレ脱却の結果、その程度の数値に達したら、まずまずアベノミックスは成功だと、考えるのでしょう。物価が上がり始め、今のうちに買いたい物を買っておこうという動きが強まれば、景気も温まってきます。
景気刺激策の効果で物価が上がり、物価が上がるから消費が増えるという循環に入れば、しめたものと政権は考えています。適度の物価上昇は絶好の景気刺激策になりますからね。そういう経済循環が始まるのを政権は期待しているのでしょうか。
それは好ましいことでしょう。問題は、どうも2%目標が独り歩きしているような気がすることです。2%の上昇といっても、その原因は様々ですよね。景気が本当によくなり、需要が高まり、その結果として、消費者物価が2%、上がるなら、デフレ脱却の証明になるでしょう。7月の消費者物価が前年比で0・7%、上がり、報道では「物価は2か月連続のプラス。脱デフレの動き」との見出しを掲げ、「総合的に勘案すると、デフレから脱却しつつあると、経済閣僚が発言した」と伝えています。どうも2%という数字そのものが重大な目標になってしまっているようです。
なぜか、経済閣僚も日銀総裁も2%上昇の中身を説明しようとはしません。来年4月に消費税が5%から8%へ、3%上がります。当然、消費者物価は上がるでしょう。企業は自己努力でできるだけ、コストを引き下げ、消費税込みの最終的な小売価格を抑えようとしますよね。それでも消費者物価は1・5%程度は上がるでしょう。それは「カウントしない」となぜはっきり言わないのでしょうか。
円安で輸入物価が上がっていますね。円安で企業の輸出は増え、輸出企業の収益は改善しますから、これは景気刺激要因になります。その一方で、輸入物価があがり、国内物価の上昇に波及し、消費者の負担が増えます。原発が止まり、火力発電の比率が高まり、原油、天然ガスの輸入が増えているところに円安が重なり、電力料金の連鎖的な値上げが進んでいます。この分は、2%目標とまったく関係のない次元の話です。2%目標から除外しなければならない動きです。円安によるガソリン価格の上昇も2%目標から差し引かねばなりません。
消費税引き上げ、円安、原発の停止などが重なり合い、2%目標の解釈は難しくなってしまいました。消費税引き上げを先取りして、今のうちに住宅建設などを始めようという駆け込み需要が発生しており、景気を好転させる一因になっています。これもデフレ脱却と物価上昇率の関係の分析を複雑にしています。当然、予想された動きなのに、日銀総裁が異次元の金融緩和政策を発表したとき、2%目標の中身の説明に深入りしなかったのは、なぜでしょうか。「とにかく2%だ」という気持ちがはやったのでしょうか。
インフレには、コスト・プッシュ型とデマンド・プル型があると、言われます。単純にこの二つは区別できません。相互に絡み合っているからです。それでも原発停止による電気料金の引き上げはコスト・プッシュ型の典型でしょうね。ガソリン価格も上昇もそうでしょう。消費税引き上げで小売り価格が上がるのは、コスト・プッシュ型というより、税制変更による物価上昇ですね。
デマンド・プル型というのは、景気がよくなって、需要(デマンド)が高まり、需給関係がタイトになって物価があがるインフレです。適度の上昇の範囲に収まっていれば、経済がよい循環になっていることになります。安倍政権が目指しているのは、このタイプの物価上昇でなければなりません。報道で時々、見かける「よいインフレ」とはこのことでしょう。そういう展開になるのか、コスト上昇先行型になるのか、五分五分でしょう。後者だとしらら、景気はよくならないのに、物価の上がり方のほうばかりが目立つとしたら、消費者は困惑することでしょう。
仮にいずれ、2%目標が達成されたとしても、その中身次第で、評価できる目標達成なのか、そうでないのかで議論が分かれるでしょう。その時になって大論争するより、今のうちからこの問題をどう考えているのか、政府、日銀に聞きたいところです。











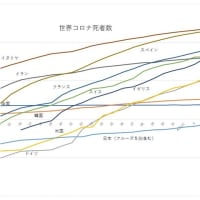









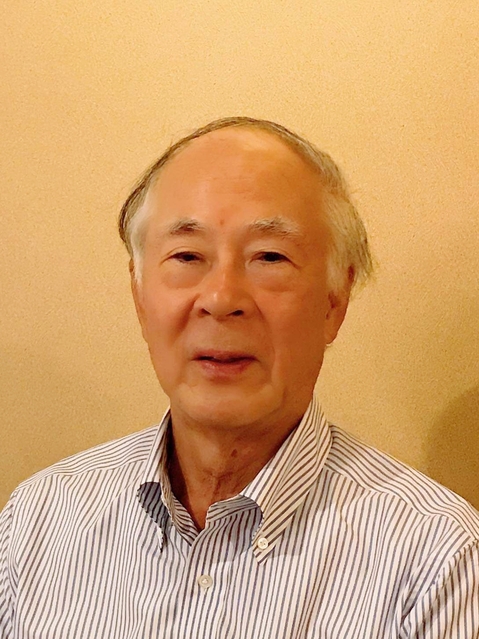

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます