恐れられる君主になれと
2024年12月20日
読売新聞主筆の渡辺恒雄氏が98歳で死去しました。すでに人物の大きさ、政界に対する影響力の大きさ、ジャーナリストとしての評価の仕方など、評伝が溢れかえっています。読売新聞社でナベツネさんに直接、接する時期がありました。ナベツネさんは活動領域が広く、その全容を追うことは私はできません。印象に残ったごくわずかエピソードをお伝えすることも、なんらかのお役に立てると思い、書くことにしました。
読書家だった同氏は書店にいくと、関心のあるコーナーに行き、しばらく本のタイトルを眺めています。選んだ1、2冊を買うのではなく、店員さんを呼んで「両腕を広げ、ここからここまで買いたい」と告げ、用意された台車の手押し車に何十冊も乗せ、地下の駐車場まで運び、トランクに積むのです。
店員さんも手慣れた様子です。「ナベツネさんは、何冊とかではなく、本棚の横の長さで本を買う。その長さは例えば1㍍に及ぶ」と言われていたそうです。本好きの同氏は、1999年、経営が行き詰まった中央公論を支援することになり、営業譲渡を受け、中央公論新社として、再出発しました。事実上の倒産で、再建のために読売本社から私を含め何人かが派遣されました。
本社における編集会議に毎月、私も出席し、出版状況、経営状態を報告していました。再建が軌道に乗り始め、かつて連続出版していた古典の名著シリーズを「中公クラシックス」として復刊しました。ある月、マキャベリの「君主論」を出版し、編集会議で紹介すると、同氏はページをめくり、「君主たる者は、恐れられるのと愛されるのがよいか」の章を選び、「二つあわせもつもは、いたって難しい。どちらか一つを捨ててやっていくとすれば、愛されるより恐れられるほうがはるかに安全である」と、読み上げました。
同氏は社内でも、社外でも「恐れられる」ことを心掛けていたと思います。編集では、自ら指揮を執る社説を大事にしていました。ある日、外交専門家(岡崎久彦、外務省OB)が主筆の部屋を訪れ、社説にクレームをつけにきました。烈火の如く怒り、「社説に文句をつけることは断じて許さない」と、罵倒しました。「恐れられる」を実践したのでしょう。この話を会議で後に聞かされました。
また、ある日の編集会議で、「夏休みに入るので、どの本を持参するか考えている」といい、結局、なんとヒトラーの「我が闘争」にしたというのです。見せてくれた「我が闘争」はボロボロになりかけ、セロテープを張りつけ、かろうじて本の体裁を保っていました。
わたしはまだ中央公論新社にいましたので、直ぐピンときて、帰りに丸の内の書店により、「我が闘争」を探しました。見つけたのは文庫のコーナーで、角川書店が上下2冊で出版していました。それを買い求め翌月の会議の際、同氏に差し上げました。「これは助かる」と喜んでくれました。
「我が闘争」は、20世紀最大の独裁者ヒトラーによるナチスの聖書と言われます。自らの政治手法、政権掌握の手法、群衆心理についての考察、プロパガンダのノウハウなど、独裁者が語るべき政治哲学を書いています。側近ゲッペルス宣伝相の「嘘も100回つけば真実になる」などの著作も読んでいたに違いない。
ヒトラーはホロコースト(ユダヤ人大虐殺)、反ユダヤ主義の信奉者ですから、ナベツネさんがそこにひかれることはあり得ない。「独裁者ならどのような政治手法で権力を強化、維持していくか」は参考になると考えたに違いない。目標1000万部を達成するには、大衆に対する宣伝活動に類する手法が必要だと思っていたのでしょう。政界に影響力を持ち、キングメーカー的な活動をするにも、ヒトラーの権力手法は参考になると考えたとしても、おかしくはないのです。
ジャーナリストを目指すなら、権力とどのように対峙するかが主題で、社内で権力を握ろうと思って、入社してくる人はまずいないでしょう。それに対し、多くのインテリが共産党にひかれたように、ナベツネさんもある時期に党員となり、共産党風の権力闘争、権力の掌握手法を学んだに違いない。しかも、政治記者の道を歩んだから、政治権力への接近、影響力の行使の手法を研究したのでしょう。
それも戦後の混乱期で、政界に人材が乏しく、政治家も記者との接点を求めた時代でした。そうした時代はナベツネさんのような政治記者が多かったに違いない。有力政治家の主筆室への訪問も喜んでいました。それを錯覚して、政治家と記者の一体化というナベツネ型をマネをする記者が絶えません。
盟友でもあった中曽根元首相は、将来、使って欲しいという思いで、「終生一記者を貫く 渡辺恒雄の碑 中曽根康弘」の墓碑を贈っています。「終生一記者」というには、ナベツネさんの正確な表現ではない。「一記者」を相当はみ出した異形の記者でした。それも戦後の混乱期、それに続く戦後社会が生んだ人物でした。現代の政治記者はそれとは、別の生き方をしなければならないと思います。











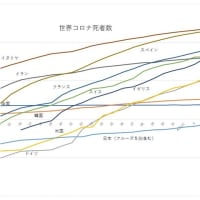









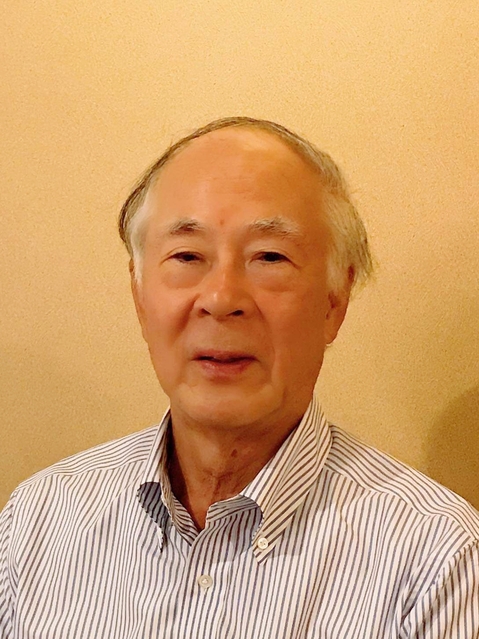

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます