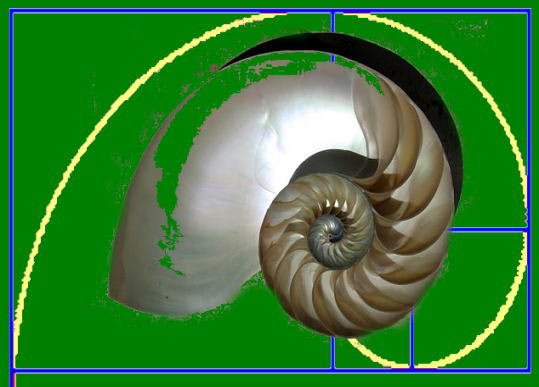・・・以下は「教えて!goo」からのコペピの英文・・・ It looks like snow(rain) , doesn`t it?・・・Is it gonna snow(rain) by the way?・・・I wonder if it's going to rain today.・・・Do you think it's going to rain today?・・・
「カナぁ~」のお勉強を・・・「推量のラム・メリ・ケム・ラシ、伝聞推定のナリ」、「比況のゴトシは本来は訓読のみの用法」・・・「コレかなぁ~・アレかな」は「推量」だろう・・・
以下は「ウイッキペデア」の原文を参照、参考にして、少々、改作して添付・・・
ーーーーー
「仮名・カナ・哉・金・可奈・かな」
正倉院所蔵の
奈良時代の・・・「奈=大+示
↓ =一+人+二+亅+八」
って、
「奈何(いかん)」、
「可奈(かな)」に
↓ ナゼ、使用されているんか?
公文書の記録には
本来
「多(おおい)」=「タ+タ」
↓ 「夕(セキ)」=夕方(ゆうがた)
朝夕(あさゆう)
潮汐(チョウセキ)
汐(うしほ・セキ)は
夕方の水で、海水・海流
上方の遊里(遊郭)で、
揚げ代が3匁の遊女
・・・夕方に多く見えだすのは銀河と星、
↓ 夕凪は海からの夕風
と書くところを
「夕」、
↓
「牟(むさぼる)」=ボウ・ム・吽(鳴)く・貪る・兜
↓ 求める・むさぼる・むさぼり奪う
欲張る
始終、連続する動き(行動・行為)
「謀」として使用
梵語「ム」の音訳字
「眸=ひとみ=瞳」
「牟=大麦=おおむぎ」
「牟食(ボウショク)」
「牟然(ボウゼン)」=牛の鳴く声
「阿吽(アウン)」=無常→変化
「牟=ム+牛」で類字は
「鉾(ほこ)」だから
「ム」は形態として、
息や口輪ではなく
「牛の角」で、先の尖ったモノだろう
だが、
「牛=𠂉(簪、櫛→角)+十(礀丅)」で
カミ挿し(角)の十(礀丅・拾)
「角」を有する動物を形字そのものである
「十(牛の身体)=礀+丅」
「ム」は漢字の意味は
「私」の源字である・・・「7・ワの逆字」?
・・・牛の頭に載っている
「私=シ・よこしま・わたくし=ム」
↓ とはダレか・・・?
↓ 牟=ム=私→よこしま(邪)
↓ →Ego・selfish・我儘
↓ 「私」は儒教的な君臣忠孝の
↓ 「私=よこしま」であり
↓ 「自我・自覚された我」
↓ ではない・・・
と書くのを
「ム」とし
漢字の一部を使って
その漢字の意味、
「多=タ←おほい」、
「牟=ム←むさぼる」として
表記した・・・
現在の平仮名「つ」に似た文字が記された
「つ」に似た文字は漢字の
「州」を字源にしている・・・?
↓
平仮名・片仮名の
誕生に繋がるもの・・・
仏典を講読する僧侶の間で、
その仏典の行間に
漢字の音や和訓を示す
借字などを
備忘のために書き加える例・・・
この借字が
漢字の
一部や
画数の少ない
漢字などを使い、
本来の漢字の字形とは
違う形で記された
行間に記すためには
字形をできるだけ省き
漢字で記される
経典の本文と区別するため
これが片仮名の源流・・・?
↓
文献上では
平安時代初期以降の用例が確認できる・・・
片仮名は
誕生の経緯から、
漢字に従属し
その意味や音を理解させるための
文字として扱われていた・・・
借字としての漢字を
草書よりも
さらに
崩した書体で記した
『土佐日記』など
平仮名による文学作品が
平安時代以降、発達
↓
借字が「かな」と
呼ばれるようになったのは、
漢字を
「真名(まな)」に対照したもの
当初は
「かりな」と読み、
撥音便形
「かんな」を経て・・・神流・神無(月)・寛和
↓ 鉋=大工道具(木材を平面に削る)
銫(セシウム・ショク
Cesium element)
族(アルカリ金属元素)の一
元素記号 Cs
原子番号55
原子量132.9
銀白色の軟らかい固体金属
アルカリ金属中、反応性は最大
融点は摂氏28.45度
炎色反応は青紫色
光電管の製造に用いる
canna=大きな華やかな
花の房を持つ、
カンナ属の植物の総称
アサ・大麻・管
カンナビス
大麻の乾燥した
雌蘂(シズイ)
↓ 麻薬の原料
「かな」の形に定着・・・
梵語の
カラナ (करण、Karana、音字の意)
からの転化という説も・・・?
古くは単に
「かな」といえば平仮名のこと
「ひらがな」の呼称が現れたのは
中世末のこと・・・
これは「平易な文字」という意味・・・?
片仮名の「かた(片)」とは・・・机、寝台、椅子、鼎
などの片足・・・
相似四脚の半分にした物
不完全なことを意味・・・・・・・不完全では無く分轄、分別
漢字に対して
省略した字形・・・・・・部首の
偏旁冠脚
形成文字で
類型的な意味を表す
偏旁を
意符(義符、形旁)
音声を表す偏旁を
音符(声符、声旁)
部首は
意符に使われること多い
漢字構成の配置場所
偏(ヘン)左配置
旁(つくり・ボウ)右配置
冠(かんむり・カン)上配置
脚(あし・キャク)下に配置
構(かまえ・コウ)
外側に囲むように配置
垂(たれ・スイ)
上から左側を
覆うように配置
繞(ニョウ・ネウ)
(ジョウ・ゼウ)
左側から下側を
とりまいて配置
↓↑
偏 旁 冠 脚 構 垂 繞(遶)
ヘンボウカンキャクコウスイニョウ
↓↑
変 貌 観 客 輿 出 饒?
天照國照彦天火明櫛玉饒速日尊
邇芸速日命
饒速日命
賑囃子?
変 貌 閑 却 項 出 遶?
↓ 似義葉哉詞?
↓ 哉(かな)詞?
平安時代の
平仮名の文章、和文
単語は
大和言葉
平仮名を用いるのが基本
しかし
「源氏」だとか・・・・・源字
朝廷の官職名など、
大和言葉に
置き換える事が・・・・・置換→痴漢=漢字おたく
婦女子に悪戯する徒
扶助詞に意多事等する訳
不可能で
漢語を用いるしかない場合は、
漢字のままで記されていた
漢語はあくまで
漢字で記すものであり、・・・アタリマエだろう・・・
漢語を平仮名で表記する
慣習がなかった・・・・・・・アタリマエだろう・・・
だが万葉仮名は「漢字」である
文章の
読み取りを
容易とするために、
大和言葉も必要に応じて
漢字で表記された・・・・・・万葉仮名で?
和歌の場合は、
慣習的に
漢語や漢字の
表記を避けるように
詠まれ書き記されていた・・・訓読みとしての万葉仮名?
「古事記序文」説明での
漢語と和語の混淆文を読め
↓
文章の構文
漢字が導入された当初は
「漢文」の規則に従って・・・漢文文法
読み書きされていた
後、
漢字で記した言葉を
日本語の構文に従って
並べる形式が生まれた
助詞などを
借字で語句のあいだに
小さく書き添える形式
(宣命書き)が・・・・・・・宣命→本居宣長?→注釈
鈴屋大人(うし)→古事記伝
行われるようになり、
それら借字で記した
助詞が片仮名となった・・・乎古止点のコト?
(をことてん・をことてむ)
漢字の右上から時計回りに
「ヲ、コト、ト、ハ、…」
漢語や
漢字で記された文章に、
片仮名が
補助的に付加された
その両者はやがて統合され、
『今昔物語集』
に見られるような、
日本語の文章の中に
漢語を数多く取り入れた
和漢混淆文として発展
当初の
『今昔物語集』は、
漢字で記された
語句のあいだに
小さく
片仮名を書き添える
「宣命書き」と
同じスタイルで書かれていた
やがて
漢字と仮名を
同じ大きさで記すようになった
↓
第二次世界大戦後あたりから、・・・一気に時代がトンだ
文章の表記には原則として
平仮名を用い、
片仮名は外来語など
特殊な場合に
用いるようになった・・・明治時代頃からだろう
↓
異体字をふくむ・・・・・い=イ・ゐ=ヰ
え=エ・ゑ=ヱ
ん=む・ン=ム
平仮名と片仮名は
明治時代になると・・・・明治である
政府によって
字体の整理が行われ、
その結果
学校教育をはじめとする
一般社会において
平仮名・片仮名・・・・・明治である
と呼ばれるものとなった
↓
仮名における
清音と濁音
音節には
清音と濁音の別があり、
濁音をあらわす
平仮名・片仮名には
濁点が付くのが約束
しかし仮名には、
古くは
濁点が付かなかった
仮名が生れる以前の
借字の段階では、・・・・「万葉仮名の段階」?
清音に当てる
借字のほかに
濁音に当てる借字を
区別して使っていた
↓
日本語の文は見た目には
漢字の羅列であり、
それをなるべく
間違いの無いように・・・・ナゼ「間違い」の漢字なのか?
単漢字と熟語漢字なのか?
文法上の使用の間違いなのか?
文節上のことなのか?
「間違い」の「間」とは?
「文節・字間」のコトなのか?
読み取らせるためには、・・・助詞の
「てにをは(弖爾乎波・天爾遠波)」
「てにはを(弖爾波乎)」
漢文訓読の
補読に補助として
漢字の四隅につけた
「助詞・助動詞・活用語尾・接辞」
などの古称
借字の音の
清濁についても
使い分けをする必要があった
↓
平安時代以降の
仮名には
清濁の別が無くなった
それは
連綿によって
仮名の文字列に
意味の区切りを作り出し、
文の読み取りを
以前よりも容易にした結果、
仮名の清濁を
使い分ける必要がなくなった・・・
濁音を示す表記を用いなくても、
不都合を感じない
文を綴れるようになった・・・
『古今和歌集』の
伝本のひとつである
「高野切」には・・・?
紀貫之の詠んだ和歌、
「そてひちて・・・・・そでひちて
むすひしみつの・・・むすびしみづの
こほれるを・・・・・こほれるを
はるかたけふの・・・はるかたけふの
かせやとくらむ」・・かぜやとくらむ
無濁点・→附濁点
となる・・・
「そて」を「そで」、
「かせ」を「かぜ」
と読むのは、
この
和歌の
文脈では
「そで」、「かぜ」としか読めないから・・・?
ひとつの仮名で
清音と濁音を兼ねるようにしていた
単語だけを取り出せば、
混乱が生じる・・・・・・・混乱は日本文学の原点?
前田利益が
「大ふへん者」
と大書した旗を背負い、
それを
「大武辺者」
と読んだ同僚から
僭越を責められた際に、
「これは
『大不便者』
と読むのだ」
と返した逸話・・・・・・面白いね・・・ボクと同類かも
濁点の起りについては
漢字のアクセントを示す
声点からきており、
本来
仮名には
必要なかったはずの濁点は、・・・・必要だったろう・・・
辞書の類や
『古今和歌集』などの
古典の本文解釈において、
言葉の意味を
確定させるために
使われるようになった
↓
他の文字にも
チェロキー文字は
仮名の五十音で
カ行とガ行を区別しない
チェロキー語の話者は
文脈で判断できる
ヘブライ文字では
子音のみを
用いるのが普通で
母音は文脈で判断する・・・・ナゼか?・・・
多分、
敵(國)に
記録文書が奪われても
「本当の音声(意味)」では
理解されないようにした?
記録文字は暗号化された?
神の名を妄りに呼ぶな、って
きっと、正体がバレルことを
怖(懼・恐・おそ)れた?
母音の付加は
新たにヘブライ語を
学習する者への便宜、
あるいは
外来語にしか用いられない
↓
仮名を
習得するための和歌
『古今和歌集』の仮名序
「…なにはづのうたは、
みかどのおほむはじめなり。
あさか山のことばは、
うねめのたはぶれよりよみて、
このふたうたは、
うたのちゝはゝのやうにてぞ、
てならふ人の、
はじめにもしける」
「なにはづのうた」というのは
「仁徳天皇に渡来人の
王仁が、・・・・・・王爾の「千字文」
なにはづに
さくやこのはな
ふゆごもり
いまははるべと
さくやこのはな」
という歌を奉ったという古事から・・・
また
「あさか山のことば」
というのは、
葛城王、
すなわち
橘諸兄が
東国の視察に行った折、
その土地にいた
采女だった女が、
「あさかやま
かげさへみゆる
やまのゐの
あさきこころを
わがおもはなくに」
という歌を作り
諸兄に献上したという話
「てならふ」とは
毛筆で文字を書く練習をする事
「手習い」
上にあげた和歌2首が、
当時
仮名(平仮名)の
書き方を練習するのに
最初の手本とされていた・・・?
↓
和歌は文の長さが
三十一字
と限られており、
子供が
仮名の手ほどきを受ける
教材としては手ごろであった
その数ある和歌の中から
「なにはづ」
と
「あさかやま」
の歌が
「てならふ人の、はじめにもしける」
といわれたのは、
実際この2首が
古い由緒を持った歌
同じ句や
同じ仮名が繰り返し出てくる
「なにはづ」
の歌は
「さくやこのはな」
という句が二度もあり、
「あさかやま」
も
「やま」
や
「あさ」
という
仮名が二度出てくる
同じ言葉や仮名を繰り返すほうが
子供にとっては
内容を覚えやすく、・・・・?
また
同じ文字を
繰り返し
書き記すことにもなる
↓
『源氏物語』の
「若紫」の巻
幼女の紫の上を
光源氏が引き取りたいと
紫の上の祖母である
尼君に申し入れると、
「まだ
難波津(なにはづ)を・・・難波津→難葉事(通・亠)
何葉告
だに
はかばかしう・・・・・・・捗々しい・果々しい
つゞけ侍らざめれば、
かひなくなむ」・・・・・・歌意無く拿務(納務・名務)
という返事
「なにはづ」の歌も
まともに書けないような
幼い娘なので、
源氏の君の
お相手にはならない
と断られた
「はかばかしう
つゞけ侍らざめれば」
とは
仮名を連綿として
うまく書きこなせない
ということである
仮名は
文字として覚えるだけではなく、
その仮名を
連綿で以って
綴れるようにするのが
当時の仮名文字の習得
自分の書いたものを
人に読み取らせるためには、
仮名の連綿は
書式の上でも
必要なことだった・・・アタリマエ・・・
↓
仮名の
発音と表記
平安時代
日本語の音韻に変化
「こひ(恋)」という
仮名に対応する
発音は
「ko-ɸi」であったが、
「ko-wi」と変化
「wi」の音をあらわす仮名は
ワ行の「ゐ」であり、
そうなると
「こひ」は「こゐ」と
記されるようになるかと思われそうだが、
文献上
「こひ(恋)」
を
「こゐ」
などと書いた例はい・・・書いてもイイ、ワルクない・・・
仮名文字を習得した
当時の人々にとっては、
恋は「こひ」という仮名で記す
のがそれまでの約束事
発音が変わったからといって
「こゐ」と書いたのでは、
他者に
「恋」という
意味で
読み取らせることが出来ない・・・相互理解は
個人的な教養の
問題である
「こい・コイ」の漢字は
複数あるから
つまり
音韻に関わりなくその
表記は一定しており、
これはほかにも
「おもふ」
など使用頻度の高い言葉ほど
その傾向が見られる
頻度の高い言葉でも、
何かのきっかけで
変わってしまいそれが
定着したものもある
「ゆゑ(故)」は「ゆへ」、
「なほ(猶)」は「なを」
と変化し記されていた
とにかく
誰かが率先して
人々に指導するということがなくても、
仮名の表記のありかた
仮名遣いは仮名を使う上で、
不都合の無い程度に
固定していた・・・・・?・・・都合がイイ
↓
不都合のなかったはずの
仮名遣いとは別に現れたのが、
藤原定家の定めた
仮名遣い、
定家仮名遣
定家が
仮名遣いを定めた目的は、
それを
多くの人に広めて
仮名遣いを
改めようとした
などということではない
定家は当時すでに古典とされた
『古今和歌集』
などの歌集、
『源氏物語』
『伊勢物語』
などの物語を頻繁に
書写していた・・・・・コピペは写しとして完全ではない
仮名遣いを定めたのは
それまでは
表記の揺れがあった
仮名遣いを、
自分が写した本においては
この意味では
こう書くのだと規範を定め、
それ以外の意味に
読まれないようにした
↓
当時いずれも
「wo」の音となっていた
「を」
と
「お」
の仮名は
アクセントの
違いによって
書き分けるよう定めており、
「置く」は「をく」、
「奥」は「おく」
と書いている
その結果
定家の定めた仮名遣いは、
音韻の変化する以前のものとは
異なるものがあったが、
定家は自分が
写した本の内容が
人から見て
読みやすい事に
腐心したのであって、
仮名遣いは
その一助として
定められたに過ぎない
定家の
個人的な事情により、・・・個人的な事情である・・・
定家仮名遣
と呼ばれるものは始まった
定家の定めた仮名遣いは
その後、
南北朝時代に
行阿によって増補
それが
歌人定家の権威もあって、
定家仮名遣と称して
教養層のあいだで広く使われた
↓
明治になると
政府によって
歴史的仮名遣が定められ、
これが広く
一般社会において用いられた
↓
第二次大戦後
現行の
現代仮名遣いが
一般には用いられている
現代仮名遣いは
おおむね
「1字1音の原則」
によって
定められているとされるが、
以下のような例が存在・・・
ひとつの音に対して
複数の仮名があるケース
/e/, /o/, /wa/ は通常
「え」「お」「わ」
だが、
格助詞の場合は
「へ」「を」「は」と書く。
/zi/,/zu/ は通常
「じ」「ず」
だが、一部のケースでは
「ぢ」「づ」と書く
↓
ひとつの仮名が
複数の音をもつケース
「は」「へ」は通常
/ha/, /he/
だが、
助詞の場合は
「わ」「え」と同様に
/wa/, /e/
と発音
「う」は
/u/
の音標であるとともに、
ウ段・オ段に添える
長音符でもある
たとえば、
かなで書けばいずれも
「よう」であるが、
「酔う」が
/you/ (「よ」+「う」)
であるのに対し、
「用」は
/yor/ (「よ」の長音)
である
↓
現代仮名遣いにも
以前からあった仮名遣いと同様に、
発音には拠らずに
書きあらわす例が定められている
「続く」は「つづく」と書くが、
「つずく」と書くように
定められてはいない・・・・書いてもイイ・・・
「蝶々」は「ちょうちょう」と書くが
「ちょおちょお」
や
「ちょーちょー」
は不可・・・?・・・書くのは個々人の「自由」である
・・・享受側も、その意味は「自由」である
現代仮名遣いとは
実際には、
歴史的仮名遣を
実際の発音に近づけるよう改め、
「続く」や「蝶々」のような例を
歴史的仮名遣と
比べて少なくしただけのもの・・・
↓
歴史的仮名遣
や
定家仮名遣
に基づかない
仮名は
日本語の音韻に変化が起こった結果、
それが定家以前に見られた
一般的な慣習によるものにせよ、
また
個人や国家が定めるにせよ、
仮名遣いを
発音とは違うところに
求めなければならなくなった
↓
琉球語の仮名
琉球王国時代からの
仮名使用の伝統
仮名表記の
琉球文学が生み出された
↓
アイヌ語仮名
アイヌ語表記文字
↓
台湾語仮名
仮名を用いて、
台湾語、客家語、高砂族
の言語を表記する方法が考案され、使用
台湾原住民の言語の
↓
文暦二年(1235年)
京都蓮華王院の宝蔵に
紀貫之自筆の・・・・・「紀の貫く之」の名前に
疑問は無いのか?
『土左日記』
(表紙には「土左日記」)が所蔵されて
いたが、
定家はそれを
閲覧する機会を得たので、
その本文を
書き写し写本を作った
この臨書の最後には、
「為令知手跡之躰、
如形写留之。
謀詐之輩、
以
他手跡
多称其筆。
可謂奇怪」・・・この記録自体が奇怪である?
(貫之の手跡が
こういうものだと知らしめるために、
その通りにここに写しておく。
いんちきなことをする連中が、
他人の手跡を多く持ち出して
貫之のものだと称しているからである。
奇っ怪というべき事である)
と記
当時、
貫之筆と称する
偽物が多く出まわっていた・・・ナゼ?
↓
「乎(を)」
や
「散(さ)」
などの変体仮名は別として、
おおむね現在のものに近い
字体の仮名が
連綿で記されている・・・
なお
「仮名」
を
「かな」
と読むのは
常用漢字表付表で認められた
熟字訓・・・
「か」
は
「かり」
の転訛であり、・・・・
漢字音ではない・・・・
重箱読みではない・・・「か」の漢字は無数にある
「多重箱読み」であろう・・・?
ーーーーー
・・・