仮称)枝折本城・・新発見の城

お城のデータ
所座地:米原市枝折地区 小字長尾 孫字 本城 map:https://yahoo.jp/8_E1qe
区 分:山城
現 状:森林
築城期:織豊期末期
築城者:土肥吉左衛門か?
城 主:土肥六郎衛の三男 吉左衛門
遺 構:曲輪・登り土塁・箱掘・堀切・竪堀
標 高:212m 比高差20m(林道より)
目標地:枝折地区の流星火薬庫
駐車場:林道脇の流星火薬庫の空地
訪城日:2107.12.10
写真集:https://www.facebook.com/osamu.tanaka.5074/posts/960356477460261
https://www.facebook.com/osamu.tanaka.5074/posts/960358140793428
お城の概要
米原市枝折集落の「天神社の湧水」を抜け、南西に進む林道がある。林道脇の流星火薬庫の空地に駐車して林道進むと明るくなった所が、両側の城跡である。
林道で分断された、谷側は比高差5m位の曲輪5であるが日当たり良くて雑草で遺構は解かりずらい。反対側から曲輪4に入ると人口林で、遺構は確認出来きた。箱掘・曲輪・登り土塁・畝状竪堀・等素晴らしい城郭遺構が残る。
『滋賀県中世城郭分布調査6 旧坂田郡の城』のにも、掲載されていない新発見の城郭遺構です
『近江坂田郡志』『滋賀県中世城郭分布調査』に「米原町枝折地区 小字長尾 孫字 本城」を記す。枝折地区の小字城戸口から孫字本城へ。2010年6月16日、長谷川博美氏・田畑喜久雄氏で【新発見した】。その後長谷川博美氏・田畑喜久雄氏が現地を踏査・作図:長谷川博美氏がした。
・旧米原町枝折地区 城郭関係地名『滋賀県中世城郭分布調査6 旧坂田郡の城 P115・P300』
51ー屋敷 52ー元城 53ー城戸口 54ー殿ノ上 55ー本城
旧米原町下丹生地区 城郭関係地名 57-元城




石田三成の恭兵屯勢伝説のある、米原市下丹生坂口の「石田の森」の上にある森林に2009年『戦乱の空間8号』で、慶長期と推測される「狼煙穴数か所」確認されている。
お城の歴史
城主や築城者・築城期を確定する文献資料は残念ながら存在しがない。『村の由来と村の発展』米原町史編纂委員会の資料に「戦いに敗れた名のある武将が枝折に陰棲しようした、平内の四方助けなるものが、更に東の山深い谷間その落人を案内したとある」。当地は小字平内のはるか山影にある城である。『改訂近江坂田郡志』は、「関ケ原に石田方として参陣した枝折城主・土肥六郎衛の長男 市太郎・次男 市次郎は戦死し、土肥六郎衛の三男 吉左衛門は陰棲し慶長18(1613)年に当地で他界した」とあり、当城は土肥六郎衛の三男 吉左衛門は陰棲した隠れ城の可能性推測される。
土肥六郎左衛門実勝とされ、源頼朝の家臣土肥次郎実遠の末葉で、足利尊氏の世に近江・美濃の野武士を平定して功があり。
箕浦庄の地頭として下向した御家人とされ、番場・多和田・醒井に分住し、箕浦庄の三土肥と称した。
『土肥八人衆・土肥八軒衆』は、醒井(醒飼)氏・野瀬氏・江籐氏・野勢氏・池田氏・ニ国氏・籾居氏・堀氏の八軒を云う。
駐車場・・・ここから林道登ります。




 登り土塁
登り土塁




 枝折城(山城)方面
枝折城(山城)方面
 枝折本城・・著作権🄫踏査・作図:長谷川博美氏
枝折本城・・著作権🄫踏査・作図:長谷川博美氏
参考資料:城歩会 枝折城見学会資料(2006年 長谷川博美氏・田畑喜久雄の新発見の枝折本城)。『村の由来と村の発展』米原町史編纂委員会
本日の訪問ありがとうございす!!















 下丹生地区から谷筋を北の尾根まで急斜を登ると、既に小町谷城の西端の岩場が続く。
下丹生地区から谷筋を北の尾根まで急斜を登ると、既に小町谷城の西端の岩場が続く。



 南3廓の巨岩
南3廓の巨岩 米原市下丹生に県道17号沿いから、枝折城、小町谷城尾根遺構を遠望
米原市下丹生に県道17号沿いから、枝折城、小町谷城尾根遺構を遠望

 長谷川博美氏作図
長谷川博美氏作図 最初の堀切(50cmの堆積)
最初の堀切(50cmの堆積) 櫓台東下の堀切(30㎝の堆積)
櫓台東下の堀切(30㎝の堆積) 南下を西側に回り
南下を西側に回り 主郭部へ登り
主郭部へ登り 土塁
土塁 櫓台です
櫓台です 5段曲輪が
5段曲輪が 東側に土塁
東側に土塁 虎口(炭釜に使用され壊されていますが)
虎口(炭釜に使用され壊されていますが)























 物見櫓台か?(310m)
物見櫓台か?(310m)



 西側の上段の曲輪へ
西側の上段の曲輪へ









 林道ゲイトは施錠されて、入れない
林道ゲイトは施錠されて、入れない
 主郭部虎口の石垣
主郭部虎口の石垣
 東屋
東屋 此処から城域・山腹大曲輪か?
此処から城域・山腹大曲輪か?

 最初の自然地形の土橋状
最初の自然地形の土橋状 左右の竪堀城
左右の竪堀城


 小曲輪か?
小曲輪か?









 主郭部
主郭部
 主郭の虎口か?
主郭の虎口か?


 主郭部虎口の東側下石垣
主郭部虎口の東側下石垣























 水没前の徳山村
水没前の徳山村

 徳山城跡見学会資料より『作図:長谷川博美氏』
徳山城跡見学会資料より『作図:長谷川博美氏』


 ・雨天と急傾斜の危険性から、大堀切に降りないで下さいと注意したのに無視された方がいましたね。
・雨天と急傾斜の危険性から、大堀切に降りないで下さいと注意したのに無視された方がいましたね。



























 官山寺城の位置
官山寺城の位置


















































 籠城山城俯瞰図{城郭研究家 長谷川博美氏作図}
籠城山城俯瞰図{城郭研究家 長谷川博美氏作図}







 遠景
遠景




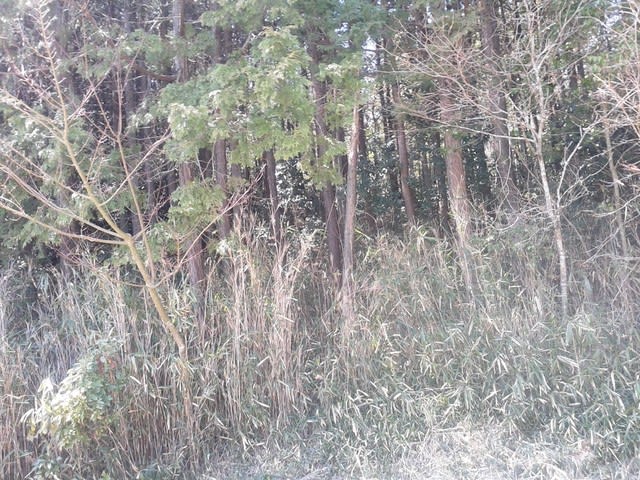 登城口
登城口







































 滋賀県中世城郭分布調査より
滋賀県中世城郭分布調査より





























 石垣
石垣

















 低土塁(山頂)
低土塁(山頂) 





























 県道45号より(遠景)、屋根上が土塁!
県道45号より(遠景)、屋根上が土塁!






















 箱掘
箱掘














 三角点
三角点














 三角点
三角点
 北側の土塁
北側の土塁





 堀切か
堀切か
 西側堀
西側堀














 【小脇館】と【小脇山城】の中間に標高:150mの山中に【小脇城】
【小脇館】と【小脇山城】の中間に標高:150mの山中に【小脇城】 「小脇城」
「小脇城」






















































 山頂部(小脇山城)
山頂部(小脇山城)


















 森が「小脇城」推定地
森が「小脇城」推定地 集落の左の森が「小脇城」推定地、
集落の左の森が「小脇城」推定地、


 南曲輪の案内状(織田軍は、南から攻めあがった)
南曲輪の案内状(織田軍は、南から攻めあがった)


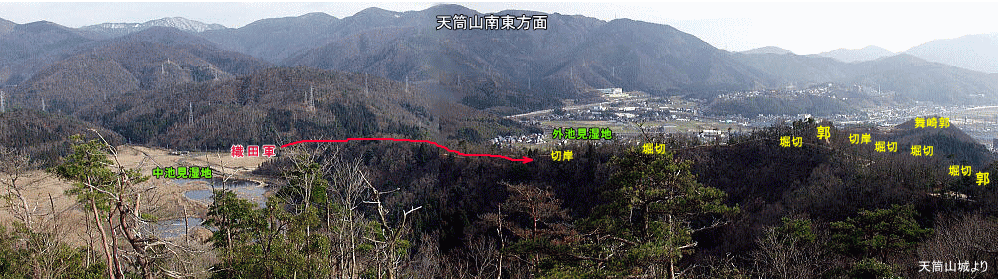 織田信長が越前(福井県)の朝倉義景を攻撃したところ、同盟関係にあった妹婿の小谷城の浅井家の裏切りにあい、挟撃の危機に瀕したため、木下藤吉郎と信長の同盟軍の徳川家康が後衛(家康の後衛に疑問をもつ向きもある)となって、信長本隊が信長勢力地まで帰還するのを援護した戦い。
織田信長が越前(福井県)の朝倉義景を攻撃したところ、同盟関係にあった妹婿の小谷城の浅井家の裏切りにあい、挟撃の危機に瀕したため、木下藤吉郎と信長の同盟軍の徳川家康が後衛(家康の後衛に疑問をもつ向きもある)となって、信長本隊が信長勢力地まで帰還するのを援護した戦い。 


















































 天筒山城遠望
天筒山城遠望












