
現 状:神社・宅地
館
遺 構:
築城期:
築城者:
岡城は、立入ヶ丘小学校の南側にある田中神社境内辺りに築かれていた。
城の遺構も何も残っていないが、すぐ北側にあった立入城の警護の役割を持った城か?
歴 史
岡城は、築城年代や築城者など詳細不詳。






 立入ヶ丘小学校
立入ヶ丘小学校
 神社境内に「馬繋(うまつな)ぎ」と呼ばれる大きな石が残されている。
神社境内に「馬繋(うまつな)ぎ」と呼ばれる大きな石が残されている。
参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、守山城物語・お城の旅日記
本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!

現 状:神社・宅地
館
遺 構:
築城期:
築城者:
岡城は、立入ヶ丘小学校の南側にある田中神社境内辺りに築かれていた。
城の遺構も何も残っていないが、すぐ北側にあった立入城の警護の役割を持った城か?
歴 史
岡城は、築城年代や築城者など詳細不詳。






 立入ヶ丘小学校
立入ヶ丘小学校
 神社境内に「馬繋(うまつな)ぎ」と呼ばれる大きな石が残されている。
神社境内に「馬繋(うまつな)ぎ」と呼ばれる大きな石が残されている。
参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、守山城物語・お城の旅日記
本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!

 2006年の遺構…守山城物語より
2006年の遺構…守山城物語より
お城のデータ
所在地 : 守山市焔魔堂町 map:http://yahoo.jp/pHotov
現 状:宅地・水田
区 分 : 平城
築城期:平安期?
築城者:
遺 構:
目標地:十王寺(閻魔堂)
訪城日 :2014.12.22



お城の概要
焔魔堂城の築城年代や築城者など詳細は不明であるが、城に因むとされる「城之浦」という小字の北側に小字「新替」が存し、その中央が周囲より一段高い畑地となっていて、中世土器片が表面採取されたことから、城館跡と推測されている。
なお、「新替」は「新開」の転訛としたもので、城の廃絶後に新しく耕地として開かれたことを示すものでないかと考えられている。一部で住宅開発に伴う発掘調査が行われているが城郭に関係する出土はないようである。
 小字新替(城跡)
小字新替(城跡)



焔魔堂町交差点を左折し、南西に110m程先の右手前方が十王寺。
焔魔堂町交差点を直進し、200m程行った左手奥が小字「新替」。焔魔堂町西交差点の少し手前。
守山城物語を資料に、周辺を探す遺構周辺は宅地開発進み、大きく様変わりしている。
お城の歴史
『一遍上人絵伝』第四巻の詞書に「江州守山のほとり、焔魔堂といふ所におはしける時」比叡山の僧重豪が訪ねてきたことを記しており、鎌倉期には「焔魔堂」は既に地名化して集落の名となり。山門の一つの拠点であったことがうかがえる、焔魔堂城にも、「山徒」的な在地領主が居住した。
なお、焔魔堂という町名は、小野篁(802~50)が閻魔堂(五道山十王寺)開基に高市玄麿作と伝わる閻魔大王像を安置したことに由来する。
十王寺は、浄土宗寺院で閻魔堂とも称され、また、小野篁が十王と倶生神の像を刻み、これを祀ったことから十王寺と称されるようになった。十王とは人間の死後の世界で生前の行いを裁く王の事で、閻魔大王などを指す。五道とは人間が生前の善悪所業によって到着する五つの場所(天上、人間、地獄、畜生、餓鬼)のことである。
しかし、小野篁が亡くなった後、いつ間にか十王が無くなり、倶生神のみとなり、日野の新楽院より十王像の寄付を受けている。現在の堂内には、十王、倶生神、小野篁像、閻魔の本地仏である地蔵菩薩、閻魔王が祀られている。


 閻魔堂向かいの神社(閻魔堂町自治会館)
閻魔堂向かいの神社(閻魔堂町自治会館)

 徳栄寺(中仙道沿い)
徳栄寺(中仙道沿い)
参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、守山城物語、geocities
本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!
 虎口
虎口


お城のデータ
所在地:亀山市川崎町川崎一色字野畑 map:http://yahoo.jp/Nm0Knu
築城期: -
築城者: -
改築者:羽柴秀吉
城 主: -
区 分:平城
遺 構:土塁・空掘・井戸・現地説明板
城 域:70m×120m
訪城日:2014.12.6



お城の概要
古城跡が所在する川崎町は、安楽川と八島川、御幣川が合流し、安楽峠越えの街道や近世には巡見道が走る交通の要衝であった。
周辺には、落山城跡や野元坂館跡、青館跡があり、特に峯城跡は八島川対岸に位置する。
古城跡は、八島川左岸、川から約10mの高さの河岸段丘上にある。
南側に谷が入り込む急斜面を選地しており、自然の地形を巧みに利用した築城といえる。
主郭となるのは、周囲に土塁が巡らされた曲輪1で、東側が開口し虎口2が設けられる。
この虎口は南側の土塁幅が広く、横矢が掛かる。
また、曲輪1には北西側にも虎口状の土塁開口部があり、横堀3へ通じている。
曲輪1の北側は、土塁と堀を連続して配置することで防御を固め、さらにそれらを屈曲させることで横矢を掛けるといった構造をしている。
このような複雑な構造は、築城当初のものではなく、天正10年(1583)とその翌年、羽柴秀吉軍が峯城を攻めた戦いの中で改修されたものと考えられる。
ただし、横堀が峯城側に設けられている点や、「九々五集」に「秀吉公ハ川崎村ニ本陣シ給ふ」と記されている点から、羽柴方の陣城とする見解がある一方、峯城への侵攻路を押さえる位置に虎口が設けられている点から、峯城方の支城とする見解があり、改修時の築城主体については明らかではない。
古城跡の築城にいたる経過や時代背景は不明である。
しかし、八島川のまさに対岸に峯城跡が位置することから、峯城跡に対する「古城」で、峯築城以前はここが峯氏の居館であった可能性がうかがえる。
八島川東岸の段丘上に築かれ、城の西側は崖状、南から東には入り組んだ自然谷を利用して築城されている。
唯願寺(真宗高田派)前の道から主曲輪への虎口部が確認できるが、道路によって取り崩され東側の自然谷から虎口への経路は不明、現状は寸断された道路の西側に虎口から入城できるが、未整備で概要は目視は困難な状態であった。
虎口を入ると正面に高さ3mほどの土塁が北側へと廻っており、主曲輪へは土塁を迂回する形で南側から入る。
北側の土塁上に上がると、こちら側には三重の空堀が巡らされ圧巻である。この三重の堀を越えると、西に向いて食い違い虎口が設けられており、こちらは搦手か。
食い違い虎口を形成する土塁は更に北に延び、防御ラインを形成しており、井戸跡も確認できる。
唯願寺(真宗高田派)の背後の竹薮の中に3重の空堀が見え、中に入り土橋から虎口、土塁などを楽しむ事が出来る。
八島川へ下る道路の左側にはすでに深い空堀があり、その道路北側は、主郭正面への虎口が確認できますが、中は竹と藪で主郭へは侵入できません。
唯願時の左横を進み城域に北側から入るとすぐに高さのある土塁と3重の空堀、長大な横堀が目に入ってきます。
 八島川へ下る道路の左側にはすでに深い空堀があり
八島川へ下る道路の左側にはすでに深い空堀があり 



歴 史
なお、北方約1kmには峯城があり、峯城の支城ではないかと考えられているが、現在の古城城の縄張りからは、天正11年に秀吉が伊勢攻めを行った時に、秀吉方によって改修され、本陣であった。
古城(ふるしろ)跡の築城にいたる経過や時代背景は不明である。
現在残る複雑な城郭構造は、築城当初のものではなく、天正11年(1583)とその翌年、羽柴秀吉軍が峯城(亀山市川崎町) を攻めた戦いの中で改修されたものと考えられる。
羽柴方の陣城とする見解がある一方、峯城への侵攻路を押さえる位置に虎口が設けられている点から、峯城方の支城とする見解があり、 改修時の築城主体については明らかではない。『現地説明板より』












参考資料:現地説明板・伊勢の城
本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!

 龍王寺(県史跡 雪野寺跡)
龍王寺(県史跡 雪野寺跡)

 木造十二神将立像(甲冑姿)・・・ご住職の好意で本堂の立像を拝見(写真は×)
木造十二神将立像(甲冑姿)・・・ご住職の好意で本堂の立像を拝見(写真は×)



 妻から形見としてもらった箱を開けると出てきたのがこの梵鐘=重要文化財(川守・龍王寺)
妻から形見としてもらった箱を開けると出てきたのがこの梵鐘=重要文化財(川守・龍王寺) 大蛇の姿絵(川守・龍王寺)
大蛇の姿絵(川守・龍王寺)








 暮れにきと 告ぐるぞ待たで 降りはるる 雪野の寺の 入相いの鐘 和泉式部
暮れにきと 告ぐるぞ待たで 降りはるる 雪野の寺の 入相いの鐘 和泉式部 赤穂浪士墓
赤穂浪士墓


後藤館跡(滋賀県東近江市中羽田町)は、近江守護・佐々木六角氏の重臣・後藤氏の在地居館跡である。
後藤氏の名は室町時代前期にあらわれ、六角氏の家老の位置にあった。
十六世紀中頃、後藤但馬守賢豊は六角義賢の信望を受けて権勢をふるったが、永禄六年(1563)義賢の子・義弼に謀殺された。
これが観音寺騒動の発端となり、六角氏は家臣団の信望を失い、やがて織田信長に滅ぼされる(『現地案内板』)。
後藤氏館跡は、周囲に基底幅約11m、高さ約3mの土塁を築き、その外に堀を穿った単郭構造の館跡で、東西幅、東辺の長さ約100m、西辺の長さ約120mの変形四辺形プランを呈し、西辺土塁の中央部に正門が存した(『現地案内板』)。
当時の在地領主の館は、非常時に備えて土塁、板塀などの防御施設が設けられ、敷地内には主屋、納屋、蔵、厩などの建物が存した。当館跡の建物配置は定かでないが、昭和五十六年の発掘調査で井戸跡、厠跡、柵跡などが検出され、その位置から主要な建物は敷地内北部中央付近に存したと推定される(『現地案内板』)。
六角重臣の居館跡ということだが、水田にぽつんと石垣と土塁が残るのみである。しかし、大規模な遺構で、観音寺城と類似する貴重な史跡である。































武蔵国多摩郡(現東京都八王子市)横山荘を中心に、勢力を持っていた武蔵七党のひとつ横山党の嫡男として生まれる。父は時広。
石橋山の合戦の頃から頼朝に仕えていた。寿永元年(1182年)8月、頼朝の誕生日を祝して梶原景時や畠山重忠と共に御護刀を頼朝に献上した有力御家人七名に名を連ねており、「吾妻鏡」ではこの記述が時兼の初見とされる。
父の後を受け、正治2年(1200年)より淡路国の守護となる。叔母が鎌倉幕府侍所別当の和田義盛の妻であり、時兼の妹が義盛の長男常盛の妻であった。
このように和田氏一族とつながりが深かったため、建暦3年(1213年)に義盛と執権北条義時との対立による和田合戦では、和田氏側に荷担した。
乱は将軍源実朝を擁する義時側の勝利に終わり、時兼は和田常盛や甲斐国都留郡の武士古郡氏とともに都留郡波加利荘へ落ち延びたが、その地で常盛ともども自殺して果てた。享年61。時兼の首は固瀬河辺に晒されたという。所領の横山荘も没収され、横山一族は凋落した。



|
竜王町川守の龍王寺の梵鐘(重要文化財)には、次のような説話が伝わります。
その昔、美男として名高い小野時兼(おののときかね)の妻が実は平木沢の大蛇で、妻から形見としてもらった箱を開けると出てきたのがこの梵鐘であるというものです。大蛇の住む平木沢は、東近江市上平木の御澤神社の白水池で、境内から湧き出る名水を汲みに訪れる人が今も後を絶えません。
今回の探訪は、東近江市観光ボランティアガイドと県の文化財専門職員が同行案内し、龍神伝説にまつわる龍王寺から御澤神社周辺の文化財を詳しく訪ねます。
現 状:畑地・集落
館
標 高:84m 比高差:0m
遺 構:曲郭跡(微高地)
築城期:
築城者:
お城の概要
布施野城は、布施野集落の西側付近にあったとされる。小字を「堂の内」という微高地の畑が存在し、城館があったと考えられている。また北西に隣接する田地も城関連の地名小字「条ノ越」という。
小字「堂の内」と「条ノ越」・・・「城ノ内」・・・「城ノ越(腰)」の転訛され、城跡との関連が考えられる。「堂の内」は、周囲に対して一段高い微高地となっている。
布施野城址とされる小字堂の内一帯の田畑は、西の小字条ノ越に対して一段高くなっています。さらに、堂の内のなかにさらに一段高い畑地があり、城の中心部と推測されます。在地領主の居館カ?。





歴 史
伝承や史料はなく、詳細は不明である。が小字「堂の内」と「条ノ越」・・・「城ノ内」・・・「城ノ越(腰)」の転訛され、城跡との関連が考えられる。「堂の内」は、周囲に対して一段高い微高地となっている。
参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、守山城物語
本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!

 京阪:穴太駅集合
京阪:穴太駅集合


 出発式
出発式 本日の登城ルート
本日の登城ルート
お城のデータ
所在地:大津市坂本町 map:http://yahoo.jp/vGXy-T
築城者:脇屋義助
築城期:南北朝期
改築者:明智光秀
改築期:坂本城の砦として改築
改築期:元亀元年(1570)
初城主:浅井・朝倉氏
区 分:山城
遺 構:虎口,石積み 標高 421m比高 約320m
訪城日:2014.12.13


南北朝時代に脇屋義助なるものが、後醍醐天皇が比叡山に籠った時に、尊氏らの北朝軍から防衛するために築かれた。
その後は、明智光秀が坂本城を築城した時に、坂本城の砦として改築して、坂本城落城と同時に廃城となります。
明智光秀の坂本城跡の北には、光秀の墓がある盛安寺があります。 さらに少し北へ京阪電車の線路を越えると、登山道入口に出ます。
その道を、墓場や古墳跡を左手に見ながら、小一時間登山して、橋を渡ってしばらくすると三叉路に出ますので左に行くと、壷笠山の方向に進みます。


 穴太野添古墳群で青空講座
穴太野添古墳群で青空講座



お城の概要
壺笠山城は坂本城と共に、近江坂本から京都一乗寺へ抜ける白鳥越えのルートを押さえる位置にあり、元亀元年の姉川の戦い後も続く元亀争乱の中、浅井・朝倉軍が立て籠もった城である。
当時、近江から京へ出るには、逢坂山越え、山中越え(志賀越え),途中越、そして白鳥越えと四つのルートがあったとされるが、白鳥越え以外のルートは、拡張・舗装されて車でも通行が可能である。
壺笠山城は坂本と京の間に聳える標高421mの壺笠山山頂に築かれている。 ここは坂本から比叡山を越えて京へ至る白鳥越えの街道が通る要衝である。
壺笠山城は円形の主郭の外側に帯曲輪が一段巡る縄張りである。主郭は北側に虎口があり、一段下の帯曲輪は南側に虎口がある。側面には若干の石積が所々残されている。
一方、白鳥越えのルートは、坂本から壷笠山の北側を通り、京都一乗寺へ抜けていると考えられるが、そのルートの全貌は明確であるとは言い難い。
今回、壷笠山城へ登るにあたっては、この白鳥越えルート。穴太駅の南から谷を詰めて、尾根筋に上がり、忠兵衛山(あほ山=青山城)の山腹をまいて壷笠山北側の鞍部に出るルート。
階段状の削平地が現れる。横堀状の地形も認められ、「浅井・朝倉軍が築いた陣跡か」尾根には道があったが、ルートを辿り、白鳥越えのルートを探る。
旧白鳥越えは、谷筋を詰めるルート:歩きやすい道、住宅地奥から山中に入り、比高差約100m、時間にして15分ほど登って、削平地を通り越した辺りから関西電力のメンテナンス道が付けられている。この道を登ると簡単に高圧線鉄塔下に出ることが出来る。尾根に出てからは、白鳥越えの道を辿り、約1時間で壷笠山と忠兵衛山の鞍部。そこには、広い林道が。滋賀里から延びている道がこの林道。
壷笠山への登り口は、鞍部から東へ20m~30mm。道を間違わなければ、しっかりとした登山道を約15分足らずで、壷笠山の山頂に着く。ピンクのビニールテープを目印に100m程
壷笠山の山頂は、雑木で、主曲輪は直径25m程度の円形をしており、主曲輪周囲には帯曲輪を廻している。この山自体が古墳だというから、山頂を削り下げて曲輪にした。
主曲輪や帯曲輪にも土塁はなく、虎口の位置は分かり難いが、主曲輪の北東に石造りの階段があり、ここが主曲輪の虎口であることが分かる。南東にも虎口らしき形状が認められる。主曲輪周囲の帯曲輪には、至る所に人頭大の石が散乱しており、主曲輪の切岸には石積みがあった。
帯曲輪の西側切岸には、人頭大の石で積んだ石積みが長さ15mほどにわたって残っている。また西側斜面には6~7段の曲輪が配置され3段目の曲輪切岸にも石垣が確認できる。 壷笠山は独立峰で、南側斜面は断崖、東と北側斜面は斜度がきついが、西側だけは支尾根が延び、支尾根を下ると京都方面へと道は続いている。
白鳥越えが400年以上昔に使われた道とはいえ、過去に利用された道。
忠兵衛山の山腹を巻くようにしてルートが西向きに変わる地点で、平子谷方面に通じていると考えられるルートと合流する。
平子谷から壷笠山へ登るルートがある。
壷笠山への登山口には案内板もあると。私が平子谷の林道入口まで行った時には、ここから約500mほど歩くと壷笠山の真東の登山ルートに出る。
また、住宅地から山中に入ってすぐに現れる曲輪群について、浅井・朝倉軍が築いたものでは?。滋賀県教育委員会発行の「淡海の城」に記されている”大手道の曲輪群”は、これらの遺構を指している。
滋賀県教育委員の資料に記されていることを、大手道と白鳥越えが一致する必要性はない。










 壺笠山城・・・登城口
壺笠山城・・・登城口



歴 史
信長公記には「志賀御陣の事」
-------------信長公記 志賀御陣の事-------------
九月廿四日 信長公、城都本能寺を御立ちなされ、逢坂を越え、越前衆に向ひて御働き。旗がしらを見申し、下坂本に陣取りこれある越北衆、癈軍の為体(ていたらく)にて、叡山へ逃げ上り、はちヶ峰・あほ山・つぼ笠山に陣取り候。
-------------
元亀元年(1570)9月、突如挙兵した大坂本願寺を包囲した信長の隙をついて浅井・朝倉連合軍が湖西路を南下します。急きょ取って返した信長軍に対して、浅井・朝倉軍は比叡の山々に砦を築いて楯籠もりました。
一方信長は山麓の穴太から坂本にかけて陣所を構え、その年の暮れに和睦が成立するまで両者のにらみ合いが続きました。
信長最大の危機滋賀の陣です。この時、浅井・朝倉軍が楯籠もった陣所の一つが壷笠山城です。標高422メートルの山頂部に築かれた城跡で、すぐそばを京都と坂本を結ぶ間道である白鳥越えが通ります。折れを持った虎口や石垣が一部に残っています。

 虎口の帯曲郭から、琵琶湖ビュー
虎口の帯曲郭から、琵琶湖ビュー
 壺笠山頂421m
壺笠山頂421m 直ぐ北側に方位計
直ぐ北側に方位計 東側の虎口
東側の虎口
 谷を隔て、比叡山の塔・堂(北西)
谷を隔て、比叡山の塔・堂(北西)
 平子の林道脇の滝
平子の林道脇の滝
 石仏
石仏




今回は、滋賀の陣の舞台となった壷笠山城を見学します。近くには京へ抜ける
間道である白鳥越えが通り、今もその痕跡をたどることができます。
・日時 平成26年12月14日(日) 13:00〜16:30
京阪石坂線穴太駅集合・解散
※駐車場がありませんので、公共交通機関を利用してご参加ください。
※穴太駅周辺も含め、コース上にトイレはありません。事前に済ませて
おいてください。
・場所 講義:穴太野添古墳群(大津市穴太) ※屋外での青空講義です。
現地見学:壷笠山城跡
・行程 京阪穴太駅→穴太野添古墳群(講義)→壷笠山城跡→京阪穴太駅 全行程約5km ※険しい山道あり 健脚向き
※雨天の場合、途中で中止することがあります。
・定員 60名(事前申込制) ・参加費 50円(保険料等実費分)
連続講座「近江の城郭」 第2回 壷笠山城(つぼかさやま)と東山道
詳細
元亀元年(1570)9月、突如挙兵した大坂本願寺を包囲した信長の隙をついて浅井・朝倉連合軍が湖西路を南下します。急きょ取って返した信長軍に対して、浅井・朝倉軍は比叡の山々に砦を築いて楯籠もりました。
一方信長は山麓の穴太から坂本にかけて陣所を構え、その年の暮れに和睦が成立するまで両者のにらみ合いが続きました。
信長最大の危機滋賀の陣です。この時、浅井・朝倉軍が楯籠もった陣所の一つが壷笠山城です。標高421メートルの山頂部に築かれた城跡で、すぐそばを京都と坂本を結ぶ間道である白鳥越えが通ります。折れを持った虎口や石垣が一部に残っています。
参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、日本城郭大系 、
本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!
お城のデータ
所在地:甲賀市甲南町上馬杉小字岡ノ下 (旧甲賀郡甲南町上馬杉小字岡ノ下) map;http://yahoo.jp/cGURUU
現 状:山林
築城期:室町期
築城者:
城 主:
遺 構:曲輪・堀切
区 分:砦・丘城
標 高:230m 比高差:30m
目標地:上馬杉油日神社・岡ノ下池
駐車場:東側に路上駐車
訪城日:2014.12.5


お城の概要
染田砦は南西に向かって伸びた尾根の先端に築かれている。
染田砦は最高所から一段下がった尾根の山腹から南西に向かって階段状に削平地を連ねる。
最高所の削平地の背後は自然地形の尾根であるが、少し北側に浅い堀切が残っている。
南西の尾根先から入れそうなのだが薮化している。東側の個人宅への斜道を登り、南へ、畑から入城した。
参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、日本城郭大系 、 甲賀の城
本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!








お城のデータ
所在地:亀山市川崎町森字殿町 map:http://yahoo.jp/8JFOe9
築 城:貞治6年(1367)
築城者:関盛忠の五男【峯 政実】
城 主:関五郎政実・峯八郎四郎・岡本宗憲
区 分:平山城
遺 構:堀切・土塁・堀・枡形虎口・天守台・帯曲輪・本丸・空堀
面 積 :140m×300m
標 高:85m 比高差20m
三重県指定史跡
訪城日:2014.12.6





お城の概要
滋賀県土山町山女原から安楽越、石水渓を経て、安楽川に沿って下る川崎地区の北側に位置しており、川崎地区民家の裏手の丘陵地にあたる。
川崎地区の川崎農協から300m~400m北の林の中に白い看板が見える、ここが峯城への登り口になる。
浸食谷を入っていくと、峯城への入り口を示す看板があるが、峯城の城域は白い案内板背後の斜面を登ったところから始まっている。急な斜面で登り難いが、山城好きの方にはこちらから上られることをお勧めする。
斜面を登りきると、2条の堀切と曲輪を経て本丸に至る。本丸の南~西~北は土塁をめぐらし、西側斜面は切岸で処理している。
伝天守台西側には帯曲輪を配し、本丸北側土塁の先は自然地形を利用した大きな空堀を配し、空堀を隔てた北側には、更に高さ0.7~0.8mの土塁を伴った曲輪を配して、虎口も認められる。 城域には雑木を「峰山城の史跡を守る会」が整備を進めている。
天正11年2月、秀吉軍の大軍に攻められたにも関わらず、1,200人の守備兵で40日間以上も持ちこたえた城であるという。当時は安楽川と八島川が峯城の山裾を洗う要害地形を利用して築城された。










 2014長谷川博美氏の現地踏査図
2014長谷川博美氏の現地踏査図

歴 史
峯城は安楽川と八島川に挟まれた標高85m程度の丘陵地に位置する山城で、正平年間(1346~70)に関盛忠の五男峯政実が築城したと伝えられる。
以後峯氏の居城であったが、天正22(1574)峯八郎四郎が伊勢長島で討ち死にしたため峯氏は滅亡した。
その後は岡本宗憲が城主となったとされるが、天正11年(1583)羽柴秀吉の北伊勢進攻、翌12年小牧長久手の戦いの前哨戦により二度の争奪戦が繰り広げられた。
天正18年(1590)岡本宗憲が亀山城に移されるにあたり廃城にされた。
中心部の北・西・東側には高い土塁が廻り、一段高い土壇には瓦が散布していることから、石垣を持ち瓦葺きの建物が存在した。中心部の北にはいわゆる虎口も見られ、室町末期から安土桃山時代にかけての城郭の姿が良好に遺されており、中世城郭から近世城郭への過度期の城郭遺構で全国的にも希少な城址である。
未発掘調査・未整備の貴重な城郭遺構であり・・・「整備・植栽なぞの公園化はせず」後世に、現状保存を望む!

































































































城郭研究家の内田氏「天守台で【又ギ巴】発見」


 天守が瓦屋根の存在の確証!
天守が瓦屋根の存在の確証! 平瓦の破片(城郭史跡の400年も山内保存)
平瓦の破片(城郭史跡の400年も山内保存)



























日 時 2014年12月6日(土)10:30受付〜14:30解散予定
内 容 天正11年期 織豊系陣城(柴田/滝川)両陣城比較検討
1賎ケ岳合戦 柴田勝家 玄蕃尾城 大図面披露解説
2北伊勢戦線 滝川儀太夫 峯城 北郭大図面解説
3峯城伝天守台見学「天守郭詳細図による縄張の解説」
講 師:愛知中世城郭研究会 長谷川博美氏
案 内:城址研究家 打田典範氏
協 力 峯城址を守る会
場 所 集会駐車場所(三重県亀山市川崎町柴崎公民館駐車場20台)
参加費 1000円 保険費100円 資料A4×8P
定 員 50名(要申込)
主 催 米原市文化協会 教養部会『城歩会』
協 力 (地元有志様各位)
問合せ 『城歩会』事務局 宮本ユウコ 090—1583—9033
長谷川 メール wwmy29831@maia.eonet.ne.jp
参考資料:伊勢の城、長谷川氏の踏査図面・レジュメ
本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!



お城のデータ
所在地:甲賀市(旧甲賀郡)甲南町下馬杉字山ノ内 map:http://yahoo.jp/f0GavW
区 分:丘城
現 状:竹林・墓地
築城年:室町期
築城者:馬杉丹後守か?
遺 構:土塁・曲郭・堀切
目標地:下馬杉バス停
訪城日:2014.12.5




お城の概要
西出城は、上記Y字の左の分岐に相当する丘陵の中間付近に築かれている。30m×20m規模の主郭を設け、北側の尾根に対して堀切を、南面に掘り残しの土塁を配している。その土塁の南東側に12m×10mの小さな郭が続き、南東面には土塁を築いている。北端の堀切からこの土塁までが城域と見られているが、さらに分岐部までの50m間に小さな平坦地が続いている。
両城とも城域の判断が難しい城である。










お城の歴史
在地土豪の馬杉氏に関係する城か。
下馬杉・島神社・・・社伝によれば当神社は延徳二年四月に安芸の厳島神社の御分霊を勧請し時の領主馬杉丹後守が氏神として奉祀す。安永八年正月災害に依り破損甚しく同年六月改築し現在に至っている。











































 西出城・・・遠景
西出城・・・遠景
参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、甲賀市史(甲賀の城)、淡海の城
本日も訪問、ありがとうございました!!。感謝!!

 駐車位置(グランド横)
駐車位置(グランド横)
お城のデータ
所在地:甲賀市甲南町野川小字樫ヶ本 (旧甲賀群甲南町野川小字樫ヶ本 ) map:http://yahoo.jp/2mZY8z
現 状:山林
区 分:丘陵城
築城期:室町期
築城者:
城 主:
遺 構:曲輪・土塁・堀切
標 高:210m 比高差:20m
目標地:福泉寺
駐車場:福泉寺
訪城日:2014.11.19・2014.12.5

お城の概要
野川城は福泉寺の西背後にある丘陵の頂部・先端に築かれている。
西側を土塁として削り残した削平地が尾根先にあり、南へ伸びている。土塁の西側は堀切によって遮断している。
福泉寺の裏に城道がある・・・(福泉寺の東に民家から少し登ると城道がある)





歴 史
詳細不明。






















 土塁の西側は堀切によって遮断.
土塁の西側は堀切によって遮断.


 土塁の西側は堀切によって遮断。
土塁の西側は堀切によって遮断。




 西側土塁下の堀切北西側は家臣屋敷跡が続く
西側土塁下の堀切北西側は家臣屋敷跡が続く 公園化された、下屋敷・家臣団屋敷跡
公園化された、下屋敷・家臣団屋敷跡






 南先端
南先端


























 野川城(遠景)下野川児童広場より
野川城(遠景)下野川児童広場より
参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、日本城郭大系 、 甲賀の城
本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!
 松原内湖遺跡から出土した巻数板(近江八幡市安土町下豊浦・安土城考古博物館)
松原内湖遺跡から出土した巻数板(近江八幡市安土町下豊浦・安土城考古博物館)
滋賀県文化財保護協会は4日、彦根市松原町の松原内湖遺跡から、鎌倉時代末期に疫病などの災厄を防ぐため集落の境界につるした「巻数板(かんじょういた)」が出土したと発表した。
毎年作り替えて古いものは燃やすなど廃棄したとみられ出土例が少なく、全国で2例目。湖東地域などでは、今も「勧請縄(かんじょうなわ)」や「勧請吊(つ)り」と呼ばれる同様の正月行事があり、同協会は中世と現代をつなぐ貴重な資料だとしている。
巻数板は木製で縦12・8センチ、横27・8センチ。息災を願い仁王経や般若心経を読み、12本の卒塔婆を立てたことや、元徳三(1331)年正月八日の記載がある。
当時の説話集「三国伝記」や「一遍上人絵伝」などには、勧請縄の伝承や、卒塔婆を立てたり門柱の間に縄を掛け巻数板をつるす様子が登場する。また、出土場所の周囲に集落跡とみられる多数の柱穴があることから、現在の勧請縄と同様に出土した巻数板も集落の境界で厄よけに用いられたとみられる。
集落跡近くからの出土は他に例がなく、今回の巻数板は集落単位で行われる現在の勧請縄のような行事が鎌倉時代末期までさかのぼることを示すという。
滋賀県立大の水野章二教授(日本中世史)は「滋賀は結束の強い村落が発達した場所で、鎌倉時代末期から南北朝時代に原形が登場した。巻数板はそれを裏付ける中世の村落研究上重要な資料だ」と話している。
6日午後1時と午後3時からそれぞれ30分間、安土城考古博物館(近江八幡市安土町下豊浦)で巻数板が公開される。無料。問い合わせは同協会TEL077(548)9780。
京都新聞より
犬上川の上流には、奇岩が折り重なる中を水がしぶきとともに流れ落ちる「大蛇が淵」があります。
ここに鎮座する大瀧神社は、江戸時代には瀧宮(たきのみや)と呼ばれ、犬上郡内の水田を潤す犬上川の水源をつかさどり、五穀豊穣をもたらす神として大いに信仰を集めていました。
多賀大社の奥宮として現存する大瀧神社本殿(県指定有形文化財)は、寛永15年(1627)に徳川家光の下知によって造営されたものです。
多賀大社、胡宮神社本殿もほぼ同時期に造営されたことが判明しています。
多賀町大瀧神社・胡宮神社・多賀大社の三社を歩いてめぐる今回の探訪では、多賀観光ボランティアガイドと県文化財専門職員が同行案内し、多賀三社および周辺の文化財を詳しく訪ねます。
近江鉄道 多賀大社駅






敏満寺城







胡宮神社






































大門池





 勝楽寺城(遠景)
勝楽寺城(遠景)

犬上川



楢崎古墳






 勝楽寺城(遠景)
勝楽寺城(遠景)
高源寺

 佐和山城より移築門(馬が駆け抜けるられるように、敷居がない)
佐和山城より移築門(馬が駆け抜けるられるように、敷居がない)




 勝楽寺城(遠景)
勝楽寺城(遠景)
大滝神社へ









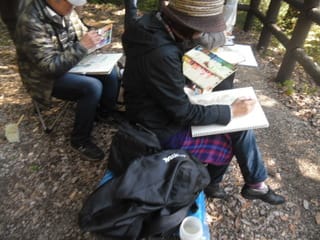








大蛇ヶ原











 皇帝ダリア
皇帝ダリア




国道307添いのSL公園





多賀大社門前:絵馬通り


多賀大社
















 村山たか
村山たか
村山 たか(むらやま たか、文化6年(1809年) - 明治9年(1876年)9月30日)は、江戸時代末期(幕末)から明治時代初期に活躍した女性で、舟橋聖一著の『花の生涯』のヒロインとして知られる。別名村山加寿江(かずえ、可寿江とも)。
1809年(文化6年)、近江国犬上郡多賀町で、多賀大社にあった寺坊尊勝院の娘として生まれる。生後すぐに寺侍村山氏に預けられ、18歳の時に当時の藩主である井伊直亮の侍女となる。
20歳になり京都に上って、祇園で芸妓となり、その際男子をもうけるが、私生児であった為に自らが引き取り、生まれ故郷の彦根に戻る。その際彦根城下で蟄居生活を過ごしていた井伊直弼と出会って情交を結び、またその数年後に直弼を通じて出会った長野主膳とも深い関係になったとされる。やがて直弼が大老となり、江戸に移った後二人は別れたとされるが、安政の大獄の際には京都にいる倒幕派の情報を江戸に送るスパイとなり大獄に大きく加担した。日本の政権に属した女性工作員としては、史上初めて名をとどめる存在である。
本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!

 堀切・土橋
堀切・土橋
お城のデータ
所在地:伊香郡余呉町東野 map:http://yahoo.jp/lY63_M
築城期:天正11年(1583)
築城者:堀久太郎秀政
陣 将:堀久太郎秀政
区 分 :陣城
遺 構:土塁・曲郭・虎口・竪堀・土橋・説明板
城 域:30m×20m
標 高:270m 比高差70m
訪城日:2014.11.29

お城の概要
菖蒲谷砦は東野山砦と堂木山砦を結ぶ線上にあって、東野山の麓の標高270mほどの山を中心にして2つの尾根筋先端に曲輪を配してる。
林道から比高差30mほどを登ると山の斜面を切出した20m×30mほどの曲輪に出る。この曲輪が南尾根先端の曲輪である。更に20mほどの比高差を登ると低土塁で囲まれた曲輪に出る。
主郭部は更に30mほど登った位置にあり、切出しの曲輪と土塁で囲まれた2つの曲輪からなり、背後には斜度のきつい斜面にもかかわらず堅堀を入れている。


歴 史
天正11年(1583)賤ヶ岳の戦いで秀吉軍が布陣した砦で、秀吉軍の砦の中でも低い山に築かれている上、北国街道にも近く対柴田軍との最前線にある。
菖蒲谷砦


 堀切・土橋
堀切・土橋






























参考資料:城郭フォーラム資料、滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城
本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!