瓶割山城を独り占め!
4月7日・・・桜やモクレンが咲き、うぐいすの声を聴きながら。
ちょっと時間が出来たので、瓶割り柴田で有名な・・・
瓶割山城跡を独り占め!
 いつも車で通るのに気付かなかった!
いつも車で通るのに気付かなかった!
 長光寺城(別名瓶割城)
長光寺城(別名瓶割城)




お城のデータ
所在地:近江八幡市長光寺町 map:
別 名:長光寺城
現 状:山林
築 城:鎌倉時代中期
築城者:佐々木四郎政堯
初城主:佐々木四郎政堯
区 分:山城
遺 構:一の丸・二の丸・米倉・井戸・石垣・堀切・土橋
城 域:150mx150m
標 高:234,5m 比高差:120m
目標地:日吉神社
駐車場:日吉神社近く公園内に駐車
戦 い : 応仁2年(1468) ○六角高頼(西軍) VS ●六角政堯(東軍)
元亀元年(1570) ○織田信長 VS ●六角承禎
お城の概要
長光寺城は標高234mの瓶割山の山頂付近に築かれ、北側眼下をはしる中山道が八風街道と交わる武佐までは直線距離にして約1km。東近江における要衝の地にある。
登り口は妙経寺横の不二滝、若しくは長福寺町の公民館前にある。どちらも山頂までは約25分程度。道はハイキングコースとなっており、案内板が立てられ判りやすくなっている。
不二滝から登ると主曲輪西側の堀切に出る。堀切横の石垣は、高さ6mを越え城内最大のものである。長光寺城は15世紀中期に佐々木四郎政堯によって築かれたのを創築とし、その後は六角氏が入り、元亀年間には織田信長の家臣・柴田勝家が入っているが、この石垣は斜度をもたせて積んでいることから、後年の柴田勝家時代のものではないかと思われる。
堀切の左(東)は主曲輪、右(西)は二の曲輪で、堀切に渡した土橋が非常に状態良く残っている。主曲輪は東西50~60m、南北30mほどで、東尾根に三の曲輪を配置した連郭式の曲輪配置である。二の曲輪は主曲輪と同程度の広さと推定されるが、雑木が生い茂り広さを読み切れない。曲輪西側の尾根筋は堀切で処理し、虎口部は石垣が積まれている。主曲輪東側の三の曲輪は南側斜面に3~4段の帯曲輪を配している。東尾根は堀切で処理されておらず、城域ラインは不明。この長光寺城は主曲輪以外の二の曲輪、三の曲輪にも石垣、石積みが見られる。特に主曲輪と三の曲輪の境界部分(井戸跡下)には一辺が50~60cm、大きなものは一辺が1mを越える石が散乱しており、主曲輪の西虎口に見られるような石積みがされていたことを予感させるが、現地では確証がとれなかった。おそらく廃城の際に徹底して破壊されたのではないだろうか。信長公記には信長が安土城を築城する際、観音寺山(繖山),長命寺山,長光寺山,伊場山から石を集めたと記述されており、長光寺城の破城が暗示されている。
訪城日:2011.4.12
北に>>>観音寺城址の繖山==観音正寺が頂上近くに!
北東に箕作山城址
 南に雪野山
南に雪野山
 東に布引山城
東に布引山城
北西の、手前は八幡山城址、後ろは長命寺山
西は水茎岡山城(戦後干拓されて陸続きに!)水茎岡山城址・右が八幡山城址
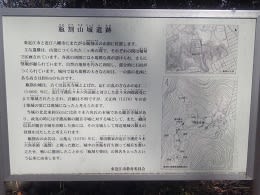
 一の郭(本丸)を一人占め!
一の郭(本丸)を一人占め!
 最大の石垣です
最大の石垣です
 二の郭の石垣
二の郭の石垣
 一の郭と二の郭の土橋です
一の郭と二の郭の土橋です
瓶割山から下りて、近江八幡市西宿に佐々木氏の重臣伊庭氏の末裔・・「伊庭貞剛邸」跡看板が???。
また、「伊庭貞剛邸阯」北に西宿城の遺構も残る。
長光寺城の戦いと瓶割り柴田
野洲河原の戦いに先立ち、柴田勝家の守る長光寺城で戦いがあったともいい、このときのエピソードが「瓶割り柴田」の名の由来となっている。しかし、この話は『武家事記』が初出であり、事実ではないと見られている。
『武家事紀』によると、元亀元年(1570年)6月に六角義賢父子は長光寺城を囲んだ。義賢は郷民から長光寺城内は水が出ず後ろの谷から掛け樋で引いていると聞き、平井甚助に水源を止めさせた。勝家は残った水を入れた瓶を三つ並べ、このままでは渇して死ぬのは疑いなく、力のあるうちに必死の戦いをしようと言うと、皆が賛成した。そこで三つの瓶を打ち割り捨て、翌16日に城外へ打って出て六角の旗本を切り崩し、野洲河原で三雲・高野瀬・水原の六角勢を討ち取ったという。ここでは、これより勝家を俗に「ツボワリ柴田」、「鬼柴田」と呼ぶようになったとする。
この話は次第に尾ひれがつき、『常山紀談』では、六角側が水源を絶った後、平井甚助が和平の使者に立って城内に入った。対面の後手水を請うと、勝家は缸(かめ)に水を入れて小姓二人で担いで来させ、甚助が手洗いを済ませると、残った水を庭に捨てさせた。甚助が帰って城内には水が豊富だと報告し、六角側は困惑。勝家は最後の宴をして水を皆に飲ませると、缸を眉尖刀(なぎなた)の石突で砕き、夜明けに六角側を急襲して大敗させ、800余の首を上げた。信長は勝家に感状を与え、これより勝家を世に「缸砕り(かめわり)柴田」と称したとなっている。
 「絵本太閤記」の瓶割り柴田
「絵本太閤記」の瓶割り柴田
『絵本太閤記』になると、元亀元年5月21日(1570年6月24日)に六角軍は兵800余人の籠城した長光寺城を攻撃するが落ちず、六角側に多数の死者がでた。義賢は家老三雲新左衛門と図り、城中への水源を止めた。義賢は平井甚助を使者とし勝家に士卒の助命を条件に降伏勧告を行うが、勝家はこれを拒絶した。甚助が部屋を出ると、多数の兵が庭で沐浴していた。甚助は帰って城中には水が充分にあると報告した。一方、勝家は残った水瓶三つを庭に置き、これから討ち死にしようと思うが、老父母や幼子のいる者は城を出て落ち延びよと言うと、誰も逃げる者はいなかった。勝家は皆に思う存分水を飲ませると、もはや蓄えは無用と長刀の石突きで瓶を砕いた。6月3日早朝、勝家は敵が油断しているところへ打って出て、300余人を討ち取り、義賢は石部城へ落ち延びた。信長は勝家を称えて手ずから感状を与え、これより世人は勝家を「瓶割り柴田」と呼んだとする。鯰江城落城もその年で、実際には佐久間盛正・蒲生賢秀・丹羽秀長・柴田勝家によって落城。
シリーズ「淡海の城」(19)より
瓶割山城(かめわりやまじょう)(近江八幡市長光寺町・長福寺町・武佐町、東近江市上平木町)
瓶割山城(長光寺城)は湖東平野に存在する独立丘陵である瓶割山(長光寺山)に位置する城郭遺跡です。山の名は元亀元年の六角勢の攻勢の折、この城に立て篭もった織田家の家臣、柴田勝家が城の中に備えた水瓶を割って士気を鼓舞し城を出て、戦いに勝利を収めたという故事に由来しています。勝家はこの戦いの後、「瓶割柴田」の異名をとったと言われていますが、実際にこのような戦いが起こったどうかは記録に残っていません。ただし、『信長公記』には「長光寺に柴田修理亮在城。」という記述があるので、実際に布陣はしていたと考えられます。
発掘調査が行われていないため詳しい状況は判明していませんが、現在のところ山上部には、帯郭が周囲に構築された最大規模の郭(『蒲生郡誌』の図で本丸と命名)を中心として大小多くの郭が残存しています。「本丸」から北および東に延びる尾根上には郭が連接して郭が構築されています。北側の尾根上には縁辺に土塁が構築されている郭があります。東側に延びる尾根にも本丸よりも少し規模の小さい郭が北側尾根と同様に連接して構築されています。
瓶割山城縄張図(振角卓哉氏作成)
一方、南西へ伸びる尾根上では2箇所大規模な郭が構築されています。これらの郭は大規模な堀切によって区画されており、本丸と隣接する郭の間(『蒲生郡誌』では「二ノ丸」)は土橋で連絡されています。また、山上部の郭の各所には竪堀が配されています。山上部の郭には複数の石垣が構築されています。最も大規模なものは、本丸南西部に位置するもので比高差約6mを測ります。城内に見られる石垣は埋もれている部分が多く、『蒲生郡誌』に掲載された平面図には現在では確認できない石垣が書き込まれていることから、実際には石垣が他にも存在しているものと考えられます。この山上部に残る遺構以外に瓶割山山中には郭と考えられる遺構が残存しています。山麓東側には根小屋とされる土塁で区画された遺構が残ることから、瓶割山全体が城郭として使用されたものと考えられます。
 瓶割山城縄張図(振角卓哉氏作成)
瓶割山城縄張図(振角卓哉氏作成)
 二ノ丸南側の堀切・土橋
二ノ丸南側の堀切・土橋
 本丸南西部の高石垣
本丸南西部の高石垣
応仁の乱の際に「長光寺」に城を築いたという記録があることから、この時期に瓶割山城の歴史は始まったと考えられていますが、現在山上部に残る遺構は郭に高石垣が構築されていること、本丸、二ノ丸の南西部に枡形虎口とも解釈できる部分を持つことから柴田勝家の布陣によって構築されたものではないかと考えられます。もともとの長光寺城の遺構も取り込まれているかもしれませんが、はっきりしません。また、東に延びる尾根の南斜面には連続して小規模な郭が構築されている部分があり、城郭としては珍しい構造となっています。この付近には石仏・一石五輪塔が散在していること、山や麓の集落の「長光寺」という地名から、寺院に関連した遺構の可能性もあります。
瓶割山城へは麓の近江八幡市長福寺町、東近江市上平木町から山頂に向かう山道があります。自動車利用の場合、近江八幡市長福寺町の登山口へは国道8号線六枚橋交差点から県道14号線を八日市方面に向かい、コンビニエンスストアのある交差点を左折し登山口の日吉神社へ向かいます。ただし、登山口付近に駐車場はありません。東近江市側へは県道41号線から左折し、山麓へ向かうと鳴谷団地北側、御澤神社近くにある草の根広場付近に登山口があり、説明板が設置されています。草の根広場横に数台駐車可能な場所があります。山内には林道が通じていますが、一般車両は進入できません。
公共交通機関の場合、近江鉄道平田駅からは約20分で東近江市側の登山口、JR近江八幡駅からのバスを利用すると、長福寺停留所で近江八幡市側の、鳴谷、平木の各停留所からは東近江市側の登山口にそれぞれ徒歩20分程度で向かえます。
瓶割山城では、平成20年度に東近江市側で里山森林と遺跡整備を兼ねた事業が実施され、山麓から山上部の遺構へ向かう通路・案内看板が整えられました。また、山上部での周囲の見通しがきくようになり、郭の形状や石垣も捉えやすくなり、見学し易くなりました。平成21年度は近江八幡市域で同様の事業が実施される予定です。(上垣)
注)山および城の名称は「長光寺「瓶割」の両方が用いられていますが、今回は行政上用いられる名称に拠りました。
参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、Wikipedia
今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。































 旧虎姫町の元虎姫町長と藤田時遊館長は立ち上げた!
旧虎姫町の元虎姫町長と藤田時遊館長は立ち上げた! 前日雨降る中、有志と共に共有林から切り出し、早速見本杖も出来ていた!
前日雨降る中、有志と共に共有林から切り出し、早速見本杖も出来ていた! 有志・賛同者は参集して、もくもくと杖づくりを・・・!
有志・賛同者は参集して、もくもくと杖づくりを・・・!
 手で持つ所はすべり止にと皮を剝かず、杖の先にはゴムスベリ止め!
手で持つ所はすべり止にと皮を剝かず、杖の先にはゴムスベリ止め!



 端材や間伐材、山の地主さんに低木(杖サイズ)を切らせてと、お願いしよう!
端材や間伐材、山の地主さんに低木(杖サイズ)を切らせてと、お願いしよう!








 観音寺
観音寺 観音寺絵図
観音寺絵図
















 いつも車で通るのに気付かなかった!
いつも車で通るのに気付かなかった! 長光寺城(別名瓶割城)
長光寺城(別名瓶割城)




 南に雪野山
南に雪野山 東に布引山城
東に布引山城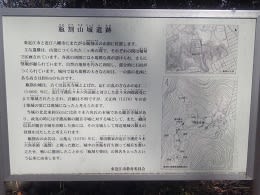
 一の郭(本丸)を一人占め!
一の郭(本丸)を一人占め! 最大の石垣です
最大の石垣です 二の郭の石垣
二の郭の石垣 一の郭と二の郭の土橋です
一の郭と二の郭の土橋です

 二ノ丸南側の堀切・土橋
二ノ丸南側の堀切・土橋 本丸南西部の高石垣
本丸南西部の高石垣