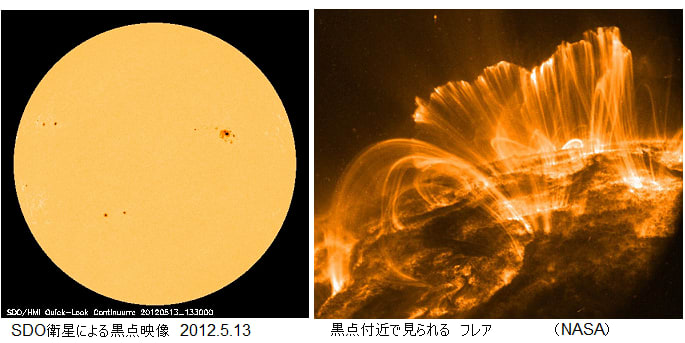タイタンに生命の可能性
「タイタン」は土星にある60個以上の衛星の中の一番大きな衛星だ。タイタンは太陽系にある衛星の中で唯一の地球の様な濃い大気が確認されている衛星で、生命体がいる可能性がとても高いと言われている。
しかし、生命がいるとしても、地球型生物とはちがったタイプの生命になるらしい。いったいどんな生命だろうか?
タイタンを包む濃い大気は、表面気圧は地球の1.5倍、大気の主成分は窒素 (97%) とメタン (2%) であることが計測されている。重力が大きく低温(分子の運動エネルギーが小さい)のため重力で大気(窒素分子)を引きとめておくことができていると考えられる。タイタンの表面重力は、1.35 m/s2と地球より小さいため、表面気圧は地球の1.5倍であるが、単位表面積あたりの大気量は地球の10倍に相当する。
太陽系内の衛星で大気を持つものには木星の衛星イオや海王星の衛星トリトンなどが存在するが、タイタンほどに厚い大気を持つものはない。また、タイタンには地球によく似た地形や気象現象があるとされている。すなわち、液体メタンの雨が降り、メタンおよびエタンの川や湖が存在すると考えられていたが、このことは、近年のカッシーニ探査により確認された。

続きはこちら → http://blog.livedoor.jp/liberty7japan/
参考HP Wikipedia:タイタン National Geographic:衛星タイタンの大気、生命には若すぎ?
 |
最新太陽系―惑星探査機のカメラが捉えた (ニュートンムック Newton別冊) |
| クリエーター情報なし | |
| ニュートンプレス |
 |
太陽系惑星 |
| クリエーター情報なし | |
| 河出書房新社 |