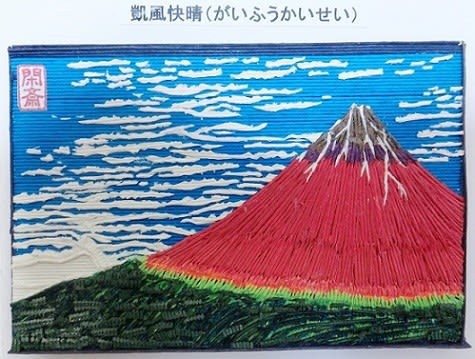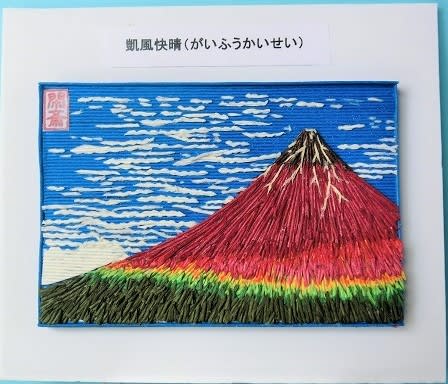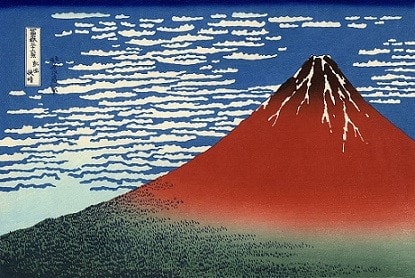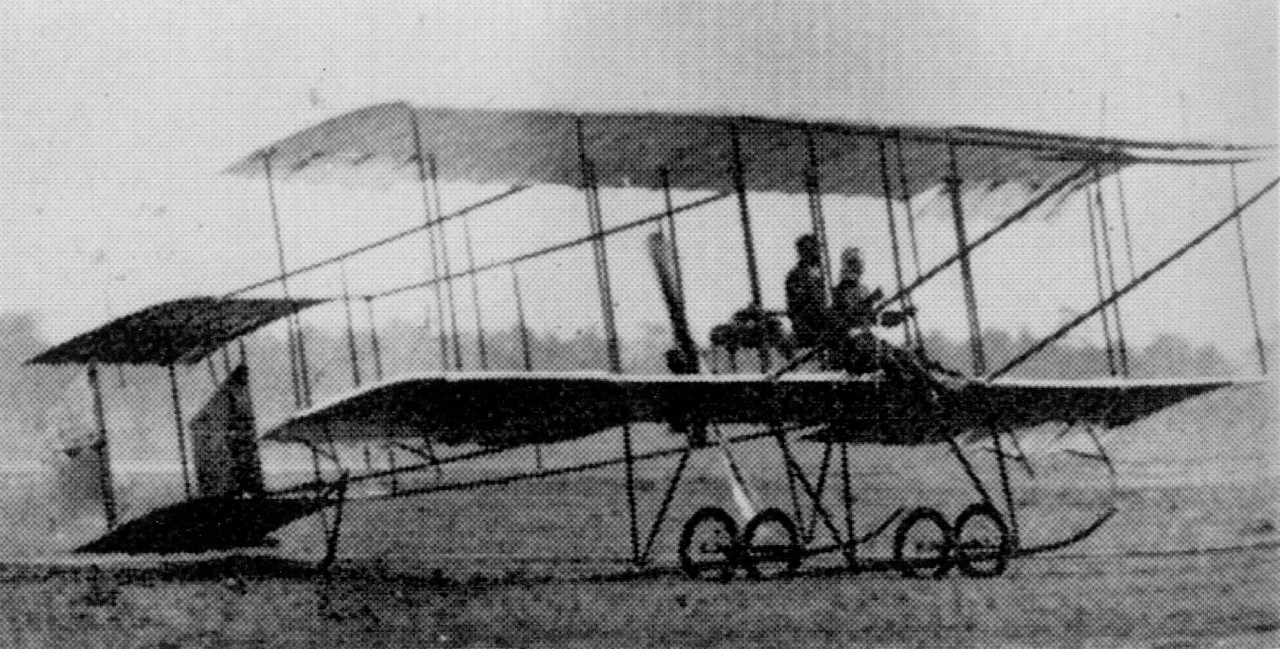「除夜(じょや)」とは、一年の最後の日「大晦日(おおみそか)」の夜のこと。
かつては一年の神「年神(歳神)」を迎えるために朝まで眠らずに過ごす習慣があった。
除夜には各家庭で「年越しそば」が食べられ、深夜0時を挟む時間帯に寺院では「除夜の鐘」が撞かれる。除夜の鐘は多くの寺で108回撞かれる。
除夜の鐘が108回の由来
眼(げん)・耳(に)・鼻(び)・舌(ぜつ)・身(しん)・意(い)の六根のそれぞれに好(こう:気持ちが好い)・悪(あく:気持ちが悪い)・平(へい:どうでもよい)があって18類、この18類それぞれに浄(じょう)・染(せん:きたない)があって36類、この36類を前世・今世・来世の三世に配当して108となり、これは人間の煩悩の数を表すとされている。
また、月の数12、二十四節気の数24、七十二候の数72を足した数が108となり、一年間を表しているとの説もある。除夜の鐘は、これら108の煩悩を一つ一つ消し去るといわれている。