
調べてみると最初は2015年に河出文庫から出ている。村岡花子さんの訳で竹宮恵子さんが解説を書いている。
今回図書館で借りたのは1964年(昭和39年。昭和39年は東京オリンピックの年だった)
の初版で、読んでみたがちょっと言葉遣いが違う、今年のオリンピックの騒ぎもまだ新しいがあの東京オリンピックからは57年の時が流れた。
なるほど村岡花子さんが初めて紹介した「赤毛のアン」の初版は1952年(昭和27年)はこういう言葉で訳されていたのかなと、ついでに調べてみた。
アンシリーズで書棚に並んでいるのは1979年版10冊(昭和54年版で45刷)セットで買うと12冊、12冊?みんな読んだつもりが10冊しかない。あと2冊は何?とまた虫が騒いで調べてみたら「アンの想い出の日々、上下巻」が増えていた。これは読んでないが戦死した魅力的なウォルターの想い出もあるなら読んでみなくては。
訳の言葉遣いに気を取られて一瞬「そばかす」を忘れていた。
尖がった本を読みかけていて、冷えてしまった思いをあたためようと新訳のKindleアプリを開いた。
図書館の村岡訳はそんな風で読みにくかった。それで光文社の新訳で読み返したが、やはり古典の名作も読みやすい新訳が楽だった。
乳児院に捨てられ、赤毛で顔中にそばかすがありおまけに右手首がない。子供時代どこにも貰い手がなく、ろくに学問も受けられなかった。浮浪者のようななりで、アメリカ南部、リンバロストの森にたどり着いた。木材会社の飯場は活気がありそこの支配人に近づいていった。
痩せてみぼらしい若者は一目で役に立たないと思えた。マックリーン支配人は一言で断ったが、なぜか話だけは聞くことにした。若者は正確できれいな言葉を話し声は澄んで礼儀正しかった。
ただ南に広がる深い森の見回りは到底無理だと思えた。
しかし若者は真剣に頼み込んだ。試しに使ってみよう。御者長夫婦と子供たちが森のそばに住んでいた。そこに下宿させて様子を見ることにした。
若者は「そばかす」という名前しかなかった、名無しでは困る。支配人は尊敬する父の名を与えた。
若者の仕事は一日二回南の作業場までの小道を回って張ってある鉄条網が無事か調べ、極上の材木が盗まれないよう目を光らせなくてはならない。
森は深く沼は淀んで蛇もいる聞きなれない鳥が甲高い声で啼く。始めは一歩ごとに恐怖で体がすくみ上がった。それにも慣れ。様々な鳥の声が聞き分けられ、その可愛らしい姿や巣作りを見、野生の花の可憐な美しさや四季折々に木々が葉を染めて散りまた新芽が芽吹く。冬は残り物を生物に与える、鳥は体のまわりで飛び、頭や肩に止まって餌をねだりノウサギやリスも集まるようになる。
そこで彼の心は豊かにのびのびと育っていった。御者長のダンカン夫妻や子供たちは優しくおおらかで暖かい家庭の仲間に加えられた。支配人のお気に入りになり、あまり使い道のない給料で買った本を読んで森の生物の名前を知り、小屋を花で飾りくつろぐようにもなった。
野鳥を撮って調べるバードレディーや、美しいエンゼルとも知り合った。
そして偶然行方のしれない子供を探している貴族がやってくる。
この読みどころは森は銘木を探している者や会社には宝の山だが、そこに入ってみると自然の息吹は豊かで厳しい中にも美しく、生物たちの世界は自然の流れのままに、鳥は去ってまた訪れ、花は咲き、常に豊かで変わらない。
優しさや厳しさを身をもって感じそれに育てられる「そばかす」の日常が感動的で、心身ともに逞しくまっすぐに育っていく様子が、忘れ物を見つけたような感動的な名作だった。
















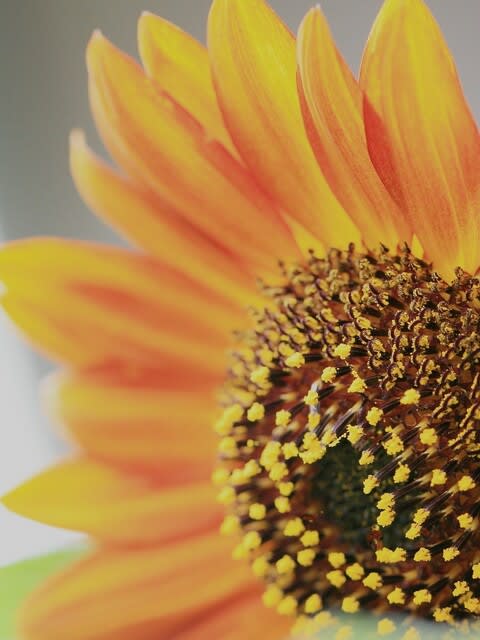


 77
77













