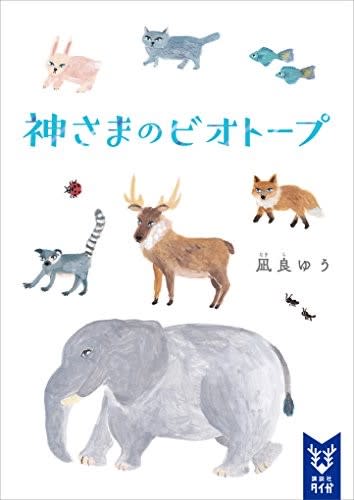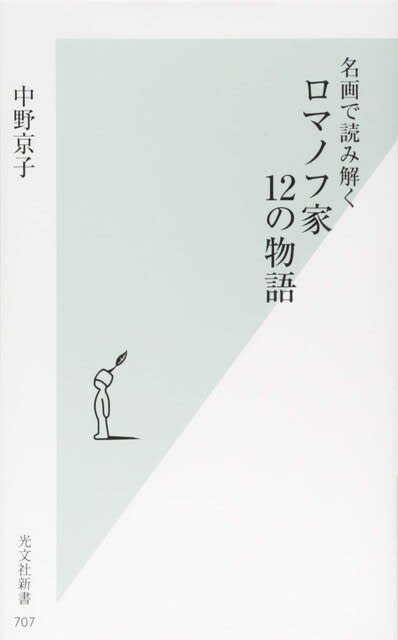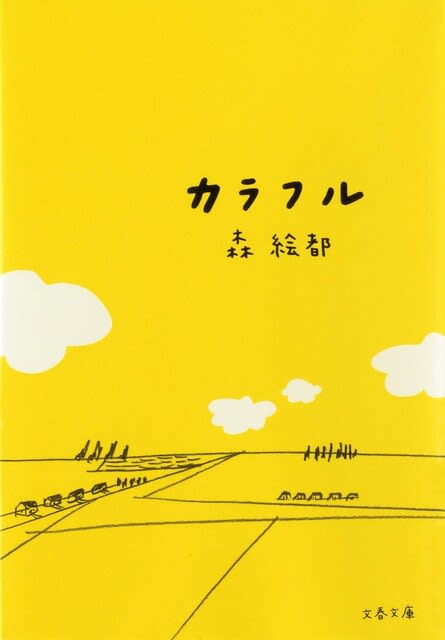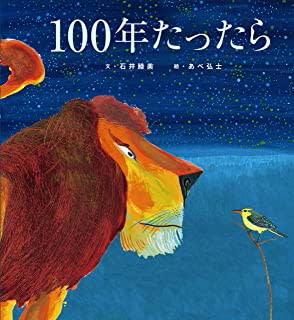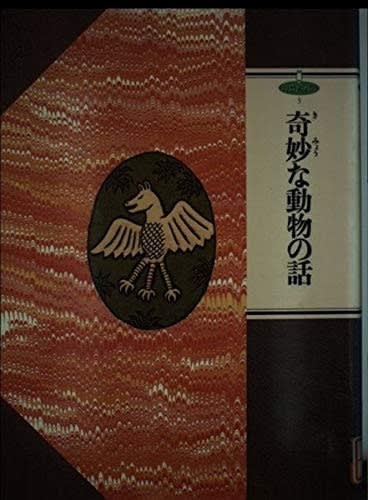でも断言すると、これは面白かった。
いとうせいこうさんの作品は読んだことがないが取り敢えずデビュー作を読むのがいいらしい。
見仏記は相棒がみうらじゅんさんで相当ぶっ飛んでいたりするので、いとうさんが本筋に引き戻しつつ、ありがたい仏さまを見て歩く、この二人の会話が愉快でたまらない。
ここでも奥泉さんが話の翼を広げるだけ広げてどこか世界の違う所に飛び出しそうになるのを、いとうせいこうさんがそれとなく地上に引き戻す。手綱さばきがいい、息もあっている、見仏記と同じようなパターンで、だから面白い。
読んだものも読まなかったものも、二人の話から納得できたり、さすがに作家の視点がと感じたり、ユニークな表現で、照らし出して読ませてくれたり類を見ない。 本音が即本質に通じているという、作家・作品解説と言えばいえる、面白すぎる本でした。
目次を見ると
1 カフカの「変身」は結構ベタなナンセンス・コント
2 ゴーゴリの「外套・鼻」はいきなりハイパーモダン
3 カミュの「異邦人」は意外にイイ人
4 ポーの「モルグ街の殺人」は事件じゃなくて事故でした
5 ガルシア・マルケスの「予告された殺人の記録」は臓物小説
6 夏目漱石の「坊ちゃん」はちょっと淋しい童貞小説
7 デュラスの「愛人」にはアナコンダは出てきません
8 ドストエフスキー「地下室の手記」の主人公は空気読みすぎ
9 魯迅の「阿Q正伝」は文学史上もっともプライドが高い男の話
私、「愛人」は面倒な文体に内心呆れて、読みかけてやめました。呆れるというのは全く自己本位な感情でして、映画ともども名作だということがよくわかりませんでした。
その上「地下室の手記」は青空文庫で読んだのですが、これもあまりの憂鬱な内容と主人公がいやな奴過ぎて、読むのをやめました。ただどこがいやなのかという所は、地下室にいて地上に出ない見識、自覚はあるのだという主人公はよしとして、ドストエフスキーも、まぁどちらも作家と作品ながら不愉快満載でした。
奥泉 まぁ大多数の人は、思い込みのセルフイメージと他人から与えられる規定の微細に調整しながら、ある程度、一つの像にまとまって生きていますよね。だけど、地下生活者は違います。
いとう 違うの?
奥泉 自分というものが決定されることがすごく怖い「私」というものが信じられないんです。
いとう それは、自分で規定することが苦しいのではなくて、他者との関係の中で「私」が規定されていくことが苦しいわけ?
奥泉 そう。
とか
また脇注で
全編、逆切れしている中学生みたい…いとう
読みにくさ抜群…いとう
一人称小説は、なんでも地下室に行くと面白い…奥泉
ここなんて奥泉さんの面目躍如かも
例えばこんな風に、私のいやな気分を分析してくれます。
伝記なんて書かれても阿Q本人は読めないのに(笑)…奥泉
会話がおかしく爆笑、「変身」問答も面白かった。
変身
外套・鼻
異邦人