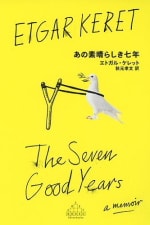読んだことはなかったが、二文字の競馬ミステリの背文字は本屋さんでもお馴染みだった。本好き仲間が言うことには「へぇぇ、あれを一度も読んでないの? 一冊も?」
作者は2010年に亡くなってしまったけど息子さんが書き継ぐそうで。
もうそんなになるのか訃報は新聞で読んだが。
まぁ元気を出して!!ミステリは競馬だけでないし、最近は自転車も、宇宙船も、あれもこれも何処もかしこも殺人や詐欺や、誘拐で大騒ぎなのに。と言いながらも、元気づけのために読んでみた。
う~~ん、これはやはり初期作品のハードボイルド。でも読んでいって、いつの間にかフランシスさんの手の内に取り込まれた。
歴史と階級の英国、競馬界も礼儀正しい。でも裏には裏があって、賭け屋が群がるギャンブルの世界も見える。
面白かった。主人公シッド・ハレーに初めてお目にかかった。この元騎手は競馬シリーズに珍しく2作品に登場する愛すべき人物らしい。
彼はチャンピオンジョッキーで名の知れた障碍競馬の騎手だったが、落馬して左手が不自由になった。妻とはうまく行かないが義父とはお互いに心を許す仲、どうも義父が裏で糸を引いたらしく、探偵社に入る。やる気もなかったが、漏れ聞くと気に入った競馬場がどうもおかしい。人気が衰えたところに不動産屋が目をつけたようだ。
馬には走りやすい絶好のターフを持つ競馬場だ。彼はやる気が出た。
闇からピストル、裏にはきな臭い陰謀。怒りと競馬愛は彼を生き返らせた。
読後そんな煽り文句が出るくらい、当時の読者は沸いたのだろう。作者フランシスの略歴では華やかな騎手生活を送り、内情に最も詳しい、背景もいい。
競馬も馬も遠くからしか見たことのない世界だったが、騎手や厩舎の調教師、上流社会に住む馬主たちの息遣いが伝わってきた。
時代の波は少しずつこの偉大な、当時で言う「競馬スリラー」にも寄せてきているようにも思える。それでもただ一人主人公として二作目に登場するのシッド・ハラーに敬意を評して、「利腕」も読んでみよう。
いつもご訪問ありがとうございます。 ↓↓↓
応援クリックをお願い致します/(*^^*)ポッ