だれぇ しばらく雨って言ったのは、
答えがない。見回すとまた私の勘違いかも、
いつものことでした(-_-;)
で、この時を逃がすな。と庭に出たのです。

きりすぎて今年は数が少なく、ちょっと淋しい。

昨年はフェンスからいくつも花房を出して
通る人に撫でてもらっていたのですが。

毎年大きくなって隣の合歓が遠慮気味です。

今年初めて植えたのですが、きれいな種類です。

毎年青くなったりピンクになったり
今年はオレンジ寄りで珍しいです。
だれぇ しばらく雨って言ったのは、
答えがない。見回すとまた私の勘違いかも、
いつものことでした(-_-;)
で、この時を逃がすな。と庭に出たのです。

きりすぎて今年は数が少なく、ちょっと淋しい。

昨年はフェンスからいくつも花房を出して
通る人に撫でてもらっていたのですが。

毎年大きくなって隣の合歓が遠慮気味です。

今年初めて植えたのですが、きれいな種類です。

毎年青くなったりピンクになったり
今年はオレンジ寄りで珍しいです。
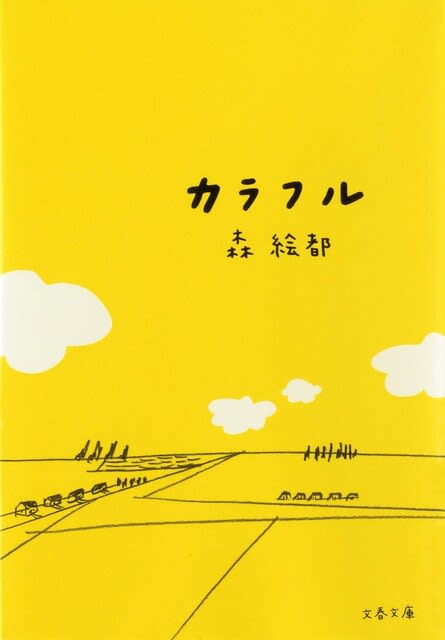
真の体を借りて修行する羽目になった、僕はもう死んだのに。輪廻から外れふわふわの魂になって呑気にやろうと思っていたのに。下界でもう一年間生きてみるという抽選に当たってしまった。
雨が続くと晴れてほしい。やっと晴れの二日目また干しました。なにもかも(o^―^o)ニコ。
周りの新緑も眩しくて、近くの山道でも走ってみますか?
でも寝坊しすぎて。近所を徘徊して収穫の花。

ハマナスが垣根から顔を出して

アップでもう一枚

(オオヤマレンゲは白でなくては)
朴ノ木でした m(__)m

「ウクライナ人を怒らせるな」という昔からよく知られた格言のせいで、ウクライナ人はすぐに頭に血がのぼる過激な民族のように誤解されてはいるが、そうではない。
ウクライナ人は穏やかで朴訥で誠実な民族だ。だからこそ、自分たちの誠実さを利用して裏切るようなことをする人間への怒りは激しい。
格言には、そういう意味も含まれているのだ、誠実には誠実をという万国に共通する教訓を秘めた格言なのだ。
シェード―ガーデンの予定が立って植え込みだけになりほっとしました。
今日は晴れたので庭に出てみました。

アゲタラム(バッソブルー)

ナデシコ(ダイアンサス)

バーベナ (スーパーベナ・アストゥインクル)

矮性千日紅
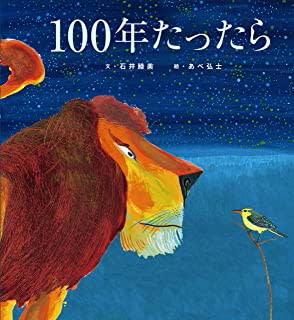

いつまで書いていてもきりがありません。いよいよ筆を擱くときが来たたようでございます。私はこの宇宙に、不思議な法則とからくりを秘めている宇宙に、あなたと令子さんのこれからをお祈りいたします。
さようなら。お体、どうかくれぐれもお大切に。さようなら。
しとしと降る雨は濡れなければ嫌いではないのですが、庭の草木の気持ちになると、やっぱり太陽を求めて少し首を伸ばし過ぎてしまって、折れるのではないかと心配になります。特に種から出てきた子供たちは特に伸びすぎます。今日はやっと晴れました。
この花のブログに参加してからは、美しい夢のあるお庭めぐりが楽しみです。今まで下ばかり向いて野草の観察をしてきましたが、木もあまり知らないし、大きな花を育てる庭もないし、園芸種はあまりわかりませんので、花の名前を見てはよく見かける花はこういう名前でこう植えるのかとお庭めぐりが楽しくなっています。
それに子供の頃親しんできた野生の花はもう見られないのかと思って、やっと方々探しまわって出会うと感激して写してきましたが、どうしても出会えない花があります。ネット上ではそういった花の写真を見かけます。こうしてPCの前に座っていても雨の日の楽しみが増えました。
それでまた晴れた今日は庭の花たちの観察をしました。

これは枯れかけていたので試しに根をきれいに洗って、春蘭の要領で
植えてみました。なんだか成功したようで、見ると花が咲いていました。

気をよくして、日陰で枯れかけていたので同じように洗って
植えてみましたが、どうも性質が違うようで
これはもう手遅れで駄目かも(´;ω;`)ウッ…

ユキノシタ
花好きでもこれは広がって困りものです。葉っぱの天ぷらは
おいしいそうですが、いろいろ薬効があっても食べる気持ちになりません。
お花は翁か少女かという不思議な形で、つい写してしまいます。

やっと咲きました、今年は色なしで素朴な姿です。

千日紅と間違う大きさで、手毬という名前も卓球台がいりそうです。
今年はピンク色に咲いていますが小さくて恥ずかしそうで可愛らしいです。

隅っこにカラーが威張って茂っていましたが、銀木犀の枝を切って
日当たりがよくなったからか、ミョウガがどこまでも増えていきます。
まぁ仲良く茂っていることだしミョウガの花を収穫するまで眺めています。

カラーをつくずく眺めてのぞき込んでいたら、中に変なものを見つけて
少しぞっとしました。よくよく見たらどの花の中にもあります。
なんだろうとあちこち調べましたがわかりません。

夕方になってもう気になって気になって。とうとう一つ花を切ってきて
プレパラート代わりにCDケースにいれ解剖しました。
カッターを今時備え付けている消毒液につけて花を真っ二つに。
中の青いものも真っ二つになりましたが種のような形状で
中の白い部分が子房のように見えます。蒔けば生えそうです。
でも根茎で増えるものでしょうカラーは。ただでさえ苞が渦巻いたような変な
花なのに、中にこんな緑の塊に角が生えたようなものができているなんて。
解剖しても何にもわかりませんでした。花が終わったら試しに
蒔いてみますけど。なんか変な奴感が去りません。

気をとり直して挿し木は、初めてなのにすくすくと育って
コンロンカばかり大きくなってきました。白い葉がひらひらして
綺麗なのですがこんなに元気だとコンロンカ畑でも作らないと('◇')ゞ

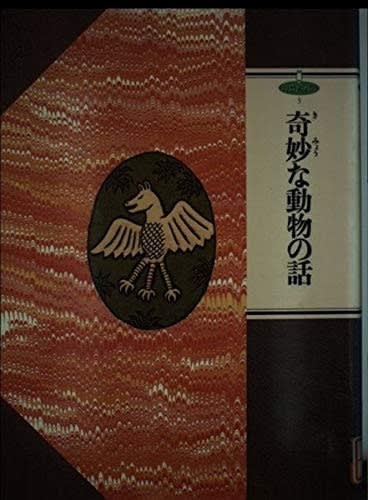
『蛇』は鴎外の妻と母親、つまり嫁姑の不和を描いた『半日』の続編と言われている。森家の嫁姑の不和はよく知られたところで、家長たる鴎外は大いに頭を悩ませていたことだろう。
市大の植物園が今月末まで閉園で、この分ならしばらくは開きそうにありません。
花の季節なのですが・・・。
近くの公園が拡張されて、脇道の両側にユリノキの並木ができました。なかなか花が咲かない幼木だったのですが、いつの間にか見上げるように大きくなって、今日そばの道から見るともう花はアップで写すことができなくなっていました。成長が早い木です。



チューリップツリーともよばれる
綺麗な花が咲いています。
広い薔薇園のある友人のところで「薔薇の会」という名前で同級生が毎年集まっていました。
持ち寄りの料理とお酒とカラオケの賑やかな会でした。残念ながら長く続いた集いも今は休会中です。
薔薇の名前を100くらいは言えるという薔薇好きの友人は100種を超すバラを育てています。
ふと温室を覗いていて、そばの大きな木の上の白い花を見つけました。よく見えないので二階の窓からのぞくと、白い珍しく受け咲の「オオヤマレンゲ」でした。持って帰っていいというので、運動部の元気な人が梯子をかけて折ってきてくれました。
名前のように蓮の花の上に人型が乗っているようで、蓮華の上に座っている仏像を連想しました。
それからは、この時期になると朴ノ木などモクレン科の仲間を探しました。
このユリノキもその仲間で、小ぶりですが黄色い模様があって美しい形をしています。
ユリノキと言えばポーの「黄金虫」でこの木に乗った髑髏の目から地面に縄を垂らして、宝物を見つけたのでした。葉が大きくて丈高くなる木がストーリーにぴったりだったのでしょうか。

志賀高原のオオヤマレンゲ

クリスマスローズの花にかけていた袋を開けてみました。
三個の個室に種が出来るようですが、今年初めて咲いた若い株だからでしょうか、一つの部屋に7粒入っているだけでした。
お互い種を作るのも、採るのも初心者同士です (^▽^)/
大きな園芸店が親切な動画にしては種から育て方まで教えてくれました。
実生だと半年後あたりで発芽するようで、発芽率は27%、これだと二粒弱です。若い花だから元気に芽を出すかもしれないと思って見ていますが期待はあまり膨らみません。
大体、自然の法則は種が地面に落ちる時が蒔き時なのかなぁと思ってしまいますが、人工的に交配して作り出される新しい品種は、もう原種の頃の習慣を忘れているかもしれません。
一応木陰に置いてみたり持ち出したり、覆いをしたりしてみようと思います。
掲載されている写真を見ると、どの花も美しく種類も多くて、クリスマスローズを集めて育てている人が、初めて種を採る話をすると「見に来て、種を上げる」と言ってくれます。
ついふらふらっと貰ってきそうになりますが、そこを我慢して。
自家製は初めてだし、じっと見ていると思いがけず黒いつやつやした種が、もうすでに可愛らしく見えます。
今ならアジサイなどもホント美くしい花がたくさん咲き誇っていますこれが揃って庭で咲いてくれたら嬉しいだろうと思うのですが、
どんな花が咲くかな、先祖返りということもあるし、二三年後に成長して咲いた時は、あの真っ白い花でなくてもまぁいいか、と今から気合いを入れています。
自然の中でも生き残りは難しくてそれなりの知恵を絞って今まで種をつないできたのでしょう。それぞれの花を見ると咲いた時の嬉しさと なんかちょっとしんどいことを背負った気がします。
どんな花が咲くか、その前にちゃんと芽を出すのか、育ての親になった気分で勉強中です。

ノーベル文学賞を受けた作家の持つ光と影、その家族と、かかわった人々の人生。カーリン・アルヴテーゲンの5作目
カーリンの著作はシリーズになっていないので、順不同で手に入った順に読んできた。そしてここまできて、彼女の作品の拠り所というか底を流れる形が分かり掛けてきた。
まず何か障害にぶつかった後にそれを乗り越え、読者を安心させる。
生きていれば訪れる大小の逆境と思われる時期、人生の闇に落ち、憎悪し、悲哀の淵に沈むとき、その絶望と辛くも乗り越えてきた再生の過程などが形を変えて作品になっている。
小説というものはそんなテーマを繰り返しで、読者は主人公と共に悲喜こもごもの時間を過ごす。
ところが同じ作家の文章やストーリー運びに慣れてくると、ちょっと休みたくなる。
こんなことを言うと作品ごとに目新しい世界を作り上げるのは作家にしても苦しい仕事に違いない。よくわかっているが、そんなわがままでこの作家を一休みしていた。
図書館本の期限が来て、あとに誰も続いてないことで少し延滞しやっと読んで書き始めた。
「影」という題名もカーリンの世界だろうと想像した。
偉大なノーベル賞作家の持つ「影」だ。作家の名前を持つ家族、作家の栄光の陰で生きていく不自由な欺瞞の多い暮らし。そしてついに檻が崩壊して、落ちていく家族の姿がある。
子供の頃から、本はたくさんあった。ほとんど叔父たちの古い教科書や参考書、好みの文学書など。一冊だけ回し読みをしている月刊雑誌。そこには切れ切れの文豪作品の読みどころがあり、海外小説の翻訳本もあった。本は大切にし、床に置かず跨がず名文は覚えて朗読をする、そんな田舎暮らしだった。作家は見たことのない世界を作りだす偉大な創造主のように見え、成長して図書館の本棚に出会って驚き、少ない小遣いをはたいて溜めた本は、宝物のようだった。
作家が尊敬され、ましてノーベル文学賞を受けて世界に認められ、出す本は次々に売れてファンが群れ、生活は豊かになっていった、人々の想像通り偉大な世界を持つ偉大な作家になった時、人間離れをした実体が作られる。
現実の影はどんなものだろう。時が経ちそんな作家も作家でなくなる時がある。
影の真実の姿が出てくるときその顔は、予想した通りもうすでに光を失ったしなびた老人だった。
作家の栄光の余波で生きてきた家族、息子、嫁。
孫は陰におぼれて死んでしまい、同じように年取って頑迷な老婆になった妻はまだいた。
世評を覆すような過去が、長く使えていた家政婦から引き出されてくる。彼女は作家を尊敬しあがめていたが、大きな秘密を抱えて孤独に亡くなった。そこに後始末をする管財人の女性が部屋を訪れる。
秘密の顔はそこから徐々に現れてくる。
栄光と影を持つ偉大な世界的な賞は大きな光に照らされる。しかしそれは広く照らす光のわずかな一隅かもしれない。
大きな世界を作り出す文学作家、創造主に近づこうとする科学者たち。
それを探り超えようとする人間の知恵が顕彰される、ノーベル賞の影を描き出した作品。
人間の卑小な一面を見る濃い不幸を書き出している。
今日の庭の花は雨で喜んでいたり、しおれていたり。植物も生きる仲間だと思いながら、今日は写すだけ。

ワイルドストロベリー
小さな赤い実がなるのですが、グランドカバーにしたら
シュートが四方八方に伸びて元気です。

真っ白な八重のクリスマスローズが3年ぶりに咲きました。
あまり美しかったので、お茶袋をかぶせて種取りです。
茶色が透けているので晴れたら覗いてみます。

どこからか庭に種が飛んできてあちこちに生えます。
風に乗ってきたプロペラが着地したのでしょう。
これは赤い芽が鮮やかな種類で30センチくらいになりました。

ヤマアジサイも白から薄紫になって花も少し大きくなりました。
七変化が少し衣装を替えた所かな可愛らしい。
随分前にこの可憐さにひかれて買って来たようで。

ホウセンカベロニカ、元気に芽が出ています。

チゴユリ
もう亡くなった近所の山野草好きの方にいただいて
大切にしているのですが今年は咲きませんでした。
無くなるのではないかと心配しましたが、
山では目立たない花も庭に置くと貴重な花になっています。
ご近所だった二人の息子さんは遠くに進学して独立され
家は売家ののぼりが立ったと思ったらすぐに降ろされて
新しい家族に引き継がれました。

このばらを弟がきれいに包装して母の日に持ってきました。もう15年ほど前です。
母は体を悪くして同居していたのですが、優しい性格なのに口と頭は元気で
「もうそろそろかと、珍しく母の日を想い出して様子を見に来たんだね」
などと辛口でした。単身赴任で滅多に会えない弟が来たのに
まぁ素直に喜ばなかったこと。さすがの親子です。
毎年密かに期待して待っていたのでしょうか。
うちの庭の唯一の薔薇でツルバラですが
今でもおとなしく植木鉢で頑張っています。
毎日細かい雨が降り止まない。でもちらっと見たらバーベナの葉っぱがおかしい。
これは今年もいるな!!大嫌いな軟体動物。殻なし巻貝。
「今日はどこかに行った?」「うん ナメクジの餌を買いに」「餌?」
確かに一番おいしそうな高い奴を買ってきました。
「天誅だ!!」 一応やさしく「天に代わってお仕置きよ」
そうだ、外が雨ならキッチンです。

かれこれ一年、育ってます💛

新芽も出てきました、今年は咲くかな?

窓辺が気に入ったのか、いつまでも満開。