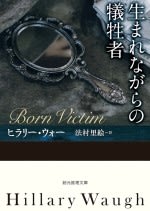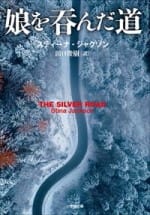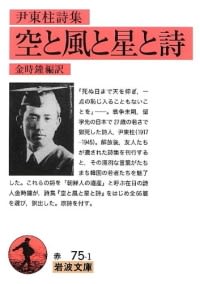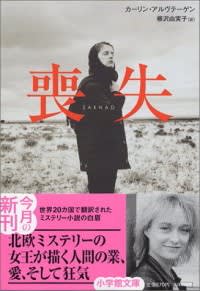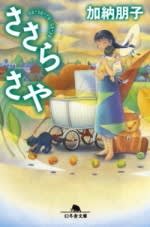フロリダ半島の北ジョージア州の大西洋岸にそって広く細長い湿地がつながっている。独特の地形は、潟湖や沼地を形成しながら温暖な湿度の高い夏とたまに雪が降るような、人が住むにはあまり恵まれていない地域である。
小さな集落を作ってバラバラに住むインデアンの多彩な種族に交じって白人が住むには、訳ありの過去があるとみられ、一様に貧しく「貧乏白人」とあざけりをもって呼ばれたりしている。
カイヤはそういった両親や兄弟と共に住み着いた。父は戦争で負傷し軍人傷病手当てが唯一の収入だった。
父は街に出ては飲んだくれて帰り、母は家事に疲れ夫婦げんかの果てに子供を残して家を出たまま帰らなかった。
6歳の時には兄弟も姉も家を出て行った。残った父は沼地から海に舟を出し、漁をして糧を得ていたがそれもついにカイヤを捨てて出て行った。
カイヤは沼地にたつボロ小屋に住み、習い覚えた父のボートを走らせて漁をし、貝を掘って売りに行き、湿地で生きていく。
母のそばで見たささやかな野菜作りをまねてみたりもする。保護官が学校に入れるが周りの蔑みに絶えかねて一日で逃げて戻り二度と通学はしなかった。
読み書きもできず計算も苦手だったが、自然の中で生き抜くことはできた。
湿地の自然は変化に富み時に優しくカイヤを包み込んだ。植物や動物の吐息はカイヤの生活にしみこみ、四季折々の風景の中で、貧しく明日の糧も乏しい中で生きていく。
海岸線に沿って伸びている複雑な地形に入り組んだ島や、小さな岬や集落のある半島を徒歩で行き来しながら、雑貨屋の夫婦に暖かく見守られ、息子のテイトは彼女に読み書きを教え暮らしを何かと手伝ってくれる。だが彼も町の大学に去っていった。
街の人気者で素行の悪い青年がカイヤに近づいてきた、外れの火の見櫓にのぼって、落下して死んだ。
狭い地域の大事件だ。
近くに住むカイヤが捕まった。町行きのバスで往復したというアリバイがあったにもかかわらず、人々の偏見と犯人捜しの好奇心で彼女は裁判にかけられる。
しかし火の見櫓は湿地に立っていて、往復の足跡が全く見つからない。彼女を犯人にする決め手の証拠がなかった。足跡は湿った土地では湿度によって地面の表面のかたちが変化し、凹凸は平らに戻ることが多い。
事件ではなかった、事故だったと処理された。
カイヤは同じ湿地の暮らしに戻った。
時がたちテイトは近くに出来た研究所に勤めていた。めぐり合うべくしてめぐり逢い二人は家庭を持ちカイヤの小屋で暮らし始めた。
テイトの献身的な愛情のおかげで、人間の愛には湿地の生物が繰り広げられる奇怪な交尾競争以上の何かがあると、けれどカイヤは人生を通し、人間のねじ曲がったDNAのなかには生存を求める原始的な遺伝子がいまなお望ましくない形で残されていることも知った。
潮の満ち引きのように果てしなく繰り返される自然の営み、自分もその一部になれれば、カイヤはそれで満足だった。カイヤはほかの人間とは違う形で、地球やそこに生きる命と結びついていた。この大地に深く根を下ろしていた。この大地が母親だった。
カイヤは64歳まで生き傍にはテイトがいた。そしてカイヤのノートを読んでみると。
ストーリーは起伏はあるというものの興味深く飽きさせない工夫が読み取れて初めて
書いた小説らしい新鮮味があった。
自然の中で、いわゆるジャングルで動物に育てられたという話に似た指向だが、体験を元に、よりリアルな自然の深みや、その香りや独特の霧や波の音や遠く近く聞こえるかもめの鳴き声や、時には自然のもたらす荒々しさも実際に肌身で感じたリアルな表現が素晴らしかった。そこで暮らす心の豊かさに感動した。
大人に囲まれた母の郷里の暮らしは、衣食住に不自由はしなかったが、寂しかったような気がする。独りで森や雑木林の中を歩いて育った子供時代、四季折々の自然が与えてくれた恵みを今でも忘れない、時々訪ねてみるが、この本を読むとカイヤの成長とともに、海辺も少しずつ形を変えていたようだ。変わっていくあの頃の自然の風景が思い出されて共感も深く、時とともに世界が変わっていくことがうら悲しくもあった。カイヤが生物学に打ち込む道を選んだことに感動した。
夏の夜、田んぼの方からカエルの声に混じってジージーと鳴き声がする。オケラだと教えてもらったが、オケラもザリガニもちょっととんがった顔をしている。ザリガニは鳴きそうにないがもし鳴くとしたらオケラ声かも知れないな いえ、ただの妄想で(^^)