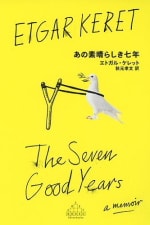
2016年発行のリアルな生活エッセイというか、掌編小説というかごく短い話36編で構成されている。
子どもが生まれて7歳になるまで、一年ごとを区切りにして、作者ケレットの日常や出来事を、暖かいというかヤッタネ!というかユーモアと機知溢れる文章で綴っている。テーマは、息子が生まれて育っていく過程の微笑ましい出来事、それを解決する両親が愛情溢れる言葉で息子の持ってくる問題をしなやかに答えながら育てている、子どもが外の世界に触れて帰ってくると、両親は童話のような言葉の中に隠された教えや智恵で、温かく包んで微笑ましい。
作者は、問題のイスラエルの首都テルアビブに住んでいる。遠く近く戦闘の音が響く中での暮らしが、実感として感じられる。他国から見れば常に内乱の中にされされている暮らしだが、住民としては渦中にいる状況をユーモアを交えて語っている、そうであっても外から見るとなにか危険な臭いを感じてしまうが。
「戦時下のぼくら」にはそういったに日常に触れている。
7年間にわたる家族の話には両親と兄と姉の暮らしにも触れ、生き方を異にした2人も理解して受け入れている。仲がいい。姉は正統派ユダヤ教徒になって生まれ変わった「亡き姉」
ユダヤ人の両親がワルシャワゲットーで迫害され逃げ続けた話も書く。
小説を書いて世界で読まれるようになったが、原文はヘブライ語で書かれていてそれから訳されているそうだ。
そういった家族や両親、息子を交えた家族の話が殆ど、失敗談や、おかしなエピソードや外国の変わった風習に戸惑ったことや、ちょっとした心温まる生活など、とても危険な国の人には思えない。
父親は癌になるが前向きで勇気を与える。「父の足あと」
妻のシーラが言った。
「心配いらないわよ。私たち二人がなんとかやり過ごさなきゃいけないことが何であろうとも、それはきっと一瞬のことよ。どんなにいひどくったって、残りの人生のたった一日に過ぎないわ」
私は何度も緊急入院して、ベッドで思った、手術といっても長い人生のたった一時間か半日、そうすればまた生きていける。
それは、思いがけず堕ちた穴で希望を失わずにいられる呪文のような言葉でシーラの言葉ににうなずいた。
この夫妻は「ジェリーイッシュ」という映画を作った。みた記憶がある実にいい映画で、これがこの作者で登場人物だとは知らなかった、カンヌ国際映画祭で新人監督に与えられるカメラ・ドールを受賞している。















