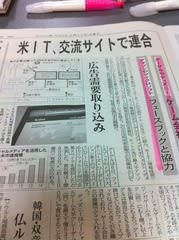| SNSビジネス・ガイド Web2.0で変わる顧客マーケティングのルール斉藤 徹,的場 大輔,藤井 達人,川井 拓也,猪川 知紀,宇佐美 進典,在賀 耕平,宮澤 弦,伊藤 靖インプレスジャパンこのアイテムの詳細を見る |
*写真は関連商品です。
SNSのビジネスモデル:
SNSのビジネスモデルは大きく分けて「広告収入モデル」「ユーザー課金モデル」「他サイト誘導・連動モデル」が成立している。
広告収入モデル
インターネット広告により収益を得るモデル。広告収入を収益の柱としているSNSはmixiやMySpaceなどが挙げられる。いかに多数のユーザーをサイト上に滞在させ、PV(ページビュー)を獲得できるかがこのモデルの鍵となる。SNSで広告収入をあげるにはそれなりのユーザー数が必要とされるため、そこまでコミュニティを育てていくにはサーバーなどを運営していく計画的な資本戦略が必要とされる[要出典]。
ユーザー課金モデル
提供しているサービスに対し、サービス利用料という形でユーザーに対して直接課金し、収入源とするモデル。PVの多さに依存せず、人的ネットワークなどSNSの特徴を積極的に活用したサービスの提供に重点を置いている点に特徴がある。現在ではビジネスネットワークの構築や職探しに利用される米国LinkedInなどのSNSが挙げられる。
またこれとは別に基本的に無料で提供しているサービスに一部サービスに付加機能を加えた有料サービスを提供して課金をするモデルもある。(例:mixiプレミアム)
他サイト誘導・連動モデル
SNS内での広告収入や課金収入に頼るのではなく、SNSをユーザーの集客や定着のツールとして捉え、自社・他社問わず他のサイトに誘導、あるいは連動させることにより得られるシナジー効果(相乗効果)を期待するモデル。ヤフー株式会社の井上雅博CEOが語るようにYahoo! Daysなどの大手ポータルサイトが運営するSNSはこのモデルを取り入れようとしている。
また携帯向けSNSのモバゲータウンはモバオク、ミュウモなどの外部の課金サービスに誘導することで収益をあげている。
なお、これら三つのモデルは、そのいずれかはそれぞれのSNSで中心となっているものの、例えば広告収入モデルはほぼすべてのSNSで取り入れられているように、ビジネスモデルを組み合わせていくのが一般的である。
アメリカ、韓国では広告収入以外にもEC事業(アバター、ホムピー)といった色々なビジネスモデルが構築されつつある。例えばサイワールドなどは月10億円以上の利益を広告(20%)とEC(80%)により生み出している[要出典][2]。その一方で、限られた会員内とはいえ、個人情報の流出の懸念も一部であり、未成年者の利用を制限する動きもある。(アメリカでは12歳以上なら利用が可能の為)
このようなSNSサイトの媒体価値の向上の中、
アメリカでは、ネット検索大手グーグルとをルトディズニーがSNSを通じて遊ぶゲーム開発会社を相次ぎ買収し、
ディズニー傘下のブランドとゲームを組み合わせることで収益化を図る。
アマゾンは、フェースブックと協力し、 利用者が友人の好みの音楽や書籍を購入したり、友人の誕生日プレゼントを選んだりできるサービスを開始している。
またマイクロソフトは、ネットを通じて友人と文書や表を共有できるサービスを開始した。
アメリカのネット利用者はSNSに費やす時間がネット利用時間のうちで最大で、この比率は一年前に比べて7ポイント高い、23%となった。
また、SNSの広告マーケットは他のネット広告を大きく上回る成長率で年率34%の成長を遂げているという。
日本だとまだインパクトは少ないように感じるが、今後のびる市場なのだろう。