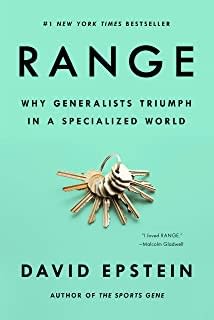運気を磨く 心を浄化する3つの技法
★★★★★あなたは、世界であり,世界はあなたである。〜クリシュナムルティ(インドの思想家)273
人生を肯定する和の思想
▼
根幹:
ゼロ・ポイント・フィールドと繋がる能力
心の世界を変える技法
0-0-2書き出し
★★★★★実は、世の中で「天才」と呼ばれる人々は,この「潜在能力」を、普通の人の何倍も開花させた人々に他ならない。それゆえ、我々も,もし心の中のネガティブな想念を消し,心をポジティブな想念で満たすことが十全にできるならば,同様の才能を開花させる可能性があるのである。117
▼
★ ★★★★「運」が強いことは、究極の資質、究極の力量と言って良いほど、大切なものである。27
★ 一流の世界においては,「技術」や「能力」を超え、やはり「運の強さ」が極めて重要な条件になっていく。30
① この本。コンサルのイメージのある田坂さんが差真の科学的観点から語る運気の磨き方。
冒頭:潜在能力の開花のさせ方から始まり,下記人間関係での運気を磨く方法まで。
こころがふときれいになる一冊。
本書:それは、そもそも、ポジティブな想念とネガティブな想念という分離や対立を超えた「究極のポジティブな想念」を心の中に実現する方法である。19
どうすれば、我々は、心の中からネガティブな想念を消すことができるのか。
どうすれば、我々は、心の中をポジティブな想念で満たすことができるのか。18
◇ 運気の定義
◇ 運気を引き寄せる:この5つの世界にどう対応するか
5つの世界:
第一:個人的な意識の世界
第二:集合的な意識の世界
第三:個人的な無意識の世界
⇒
特に重要。
第四:集合的な無意識の世界
第五:超時空的な無意識の世界101
運気の定義:
1直感が閃くということ
2予感が当たるということ23
3好機をつかむということ
4シンクロニシティが起こるということ
◎ 集合的無意識
人々の心は,深い無意識の世界で,互いに繋がっている。57
◎ 超時空的な無意識 デジャヴ既視感
人間の「表面意識」の世界の奥深くにある「無意識」の世界が、我々の人生における「運気」に影響を与えている。48
5コンステレーションを感じるということ25
コンステレーション:星座
「コンステレーション」を感じるとは,人生で起こる、一見、無関係な出来事や出会いに,何かの「意味」や「物語」を感じ、その意味や物語に従って選択や行動をすると、良い方向に導かれること。25
【良い運気を引き寄せるただ1つの条件】
我々の心の状態が、その心と共鳴するものを「引き寄せる」
引き寄せの法則
★ ★★★★仏教においても、目の前にある世界は,自分の心が現れた者に他ならないということを意味する「三界唯心所言」という言葉が語られている。33
0-0-3書き出し①の後に、
★★★★★「感謝はすべてを癒す」という言葉があるが,その言葉通り、この「感謝」の言葉を用いる技法は,劇的にではないが,静かに、我々の傷ついてしまった人間関係を癒していく。そして,何よりも,我々の心を癒していく。177
「人生の習慣を改める」
「人生の解釈を変える」
「人生の覚悟を決める」
②-a世界の成り立ち★★★★★
◇ ゼロ・ポイント・フィールド仮説
◇ 色即是空、空即是色:宗教とのつながり
現代科学の最先端、量子科学の世界で議論されている。
核心:
宇宙のすべての場所に偏在するエネルギー場のことであるが,この場に,宇宙の過去、現在,未来のすべての情報が記録されているという仮説。76
その場に、宇宙の過去、現在,未来のすべての出来事が「波動」として「ホログラム的な構造」で記録されているという仮説。77
▲
◎ 現代物理学の世界では,過去、現在,未来は同時に存在しているものとされている。79
◎ ゼロ・ポイント・フィールドに記録されている未来は、「可能性の未来」だからである。言葉を返れば,このフィールドに繋がることによって予見される未来は、無数にある未来の可能性の中で,最も起こりそうな未来である。83
◎ 我々の「心」がこの「ゼロ・ポイント・フィールド」と量子レベルで繋がっており、そのため、我々は「ゼロ・ポイント・フィールド」から情報を受け取ることができ,また、この場に情報を送ることができるという仮説でもある。85
◎ 1つの波動は,その波動と「類似の周波数」ものと「共鳴」を起こす。87
まずはネガティブな想念を消すことから始める。
②-b★★★★★
結論:
◎ 子供のように無邪気であること
▲
◎ 邪気=ネガティブな想念がない状態。122
◎ 「無意識を変える方法」として最も大切なのは,
「ポジティブな想念」を抱く方法ではなく,
「ネガティブな想念」を消す方法なのである。127
心の性質=心の双極性:
表面意識にポジティブな想念を引き起こすと同時に無意識の世界にネガティブな想念が生まれる。
②-c★★★★★結論
結論:
<ネガティブな想念を消す方法>
第一:「無意識なネガティブな想念」を浄化していく技法:「人生の習慣を改める」
自然の偉大な浄化力に委ねる:自然の中に身を浸すこと
言葉の密かな浄化力を活かす
和解の想念の浄化力を用いる135
◎ すべての人と和解する162
◎ 感謝であって,誤ることでも,許すことでもない。170
:摩擦や葛藤,反目や衝突がある人と,心の中で,一人ひとりと和解していく技法160
ネガティブな言葉を使わない
ポジティブな日常言葉を使う144
第二:「人生でのネガティブな体験」を陽転していく技法:「人生の解釈を変える」
★ ★★★★【人生の解釈を変える】
★ この技法の最も大切な目的は、「自分の人生を愛する」ということである。189
★ 「ネガティブな体験」を1つ一つ振り返り,その「意味」を再考し、解釈することによって,それが,決して「ネガティブな体験」ではないことを明確にしていく技法であり、それは、言葉を変えれば
★ 人生の「解釈」を変えるという技法でもある。180
核心:★★★★★書き出し0-0-1
運の強い人間とは「自分は運が強い」と信じている人間だ。190
自分が「幸運」に導かれた体験を思い起こすことである。
なぜなら、実は、誰の人生にも「幸運に導かれた体験」がいくつもあるからである。
例えば,あなたは、人生において、次のように思える体験がないだろうか?
「あの人に巡り会えたことで、人生が拓けた」
「あの出来事が起こったことで,道が拓けた」192
彼らは,人生で与えられた「不運に見える出来事」の中にも、成長の糧を見いだし,歩んだのだろう。その事を通じて、「不運に見える出来事」を「幸運な出来事」に変えていったのだろう。208
第三:「究極でのポジティブな人生観」を体得していく技法:「人生の覚悟を決める」
▼5つの覚悟
1自分の人生は、大いなる何かに導かれている、と信じる
2人生で起こること,すべて、深い意味がある,と考える
3人生に置ける問題、すべて、自分に原因がある、と引き受ける
4大いなる何かが、自分を育てようとしている,と受け止める
5逆境を超える叡智は,すべて、与えられる、と思い定める225
★★★★★あなたは、世界であり,世界はあなたである。〜クリシュナムルティ(インドの思想家)273
人生を肯定する和の思想
▼
根幹:
ゼロ・ポイント・フィールドと繋がる能力
心の世界を変える技法
0-0-2書き出し
★★★★★実は、世の中で「天才」と呼ばれる人々は,この「潜在能力」を、普通の人の何倍も開花させた人々に他ならない。それゆえ、我々も,もし心の中のネガティブな想念を消し,心をポジティブな想念で満たすことが十全にできるならば,同様の才能を開花させる可能性があるのである。117
▼
★ ★★★★「運」が強いことは、究極の資質、究極の力量と言って良いほど、大切なものである。27
★ 一流の世界においては,「技術」や「能力」を超え、やはり「運の強さ」が極めて重要な条件になっていく。30
① この本。コンサルのイメージのある田坂さんが差真の科学的観点から語る運気の磨き方。
冒頭:潜在能力の開花のさせ方から始まり,下記人間関係での運気を磨く方法まで。
こころがふときれいになる一冊。
本書:それは、そもそも、ポジティブな想念とネガティブな想念という分離や対立を超えた「究極のポジティブな想念」を心の中に実現する方法である。19
どうすれば、我々は、心の中からネガティブな想念を消すことができるのか。
どうすれば、我々は、心の中をポジティブな想念で満たすことができるのか。18
◇ 運気の定義
◇ 運気を引き寄せる:この5つの世界にどう対応するか
5つの世界:
第一:個人的な意識の世界
第二:集合的な意識の世界
第三:個人的な無意識の世界
⇒
特に重要。
第四:集合的な無意識の世界
第五:超時空的な無意識の世界101
運気の定義:
1直感が閃くということ
2予感が当たるということ23
3好機をつかむということ
4シンクロニシティが起こるということ
◎ 集合的無意識
人々の心は,深い無意識の世界で,互いに繋がっている。57
◎ 超時空的な無意識 デジャヴ既視感
人間の「表面意識」の世界の奥深くにある「無意識」の世界が、我々の人生における「運気」に影響を与えている。48
5コンステレーションを感じるということ25
コンステレーション:星座
「コンステレーション」を感じるとは,人生で起こる、一見、無関係な出来事や出会いに,何かの「意味」や「物語」を感じ、その意味や物語に従って選択や行動をすると、良い方向に導かれること。25
【良い運気を引き寄せるただ1つの条件】
我々の心の状態が、その心と共鳴するものを「引き寄せる」
引き寄せの法則
★ ★★★★仏教においても、目の前にある世界は,自分の心が現れた者に他ならないということを意味する「三界唯心所言」という言葉が語られている。33
0-0-3書き出し①の後に、
★★★★★「感謝はすべてを癒す」という言葉があるが,その言葉通り、この「感謝」の言葉を用いる技法は,劇的にではないが,静かに、我々の傷ついてしまった人間関係を癒していく。そして,何よりも,我々の心を癒していく。177
「人生の習慣を改める」
「人生の解釈を変える」
「人生の覚悟を決める」
②-a世界の成り立ち★★★★★
◇ ゼロ・ポイント・フィールド仮説
◇ 色即是空、空即是色:宗教とのつながり
現代科学の最先端、量子科学の世界で議論されている。
核心:
宇宙のすべての場所に偏在するエネルギー場のことであるが,この場に,宇宙の過去、現在,未来のすべての情報が記録されているという仮説。76
その場に、宇宙の過去、現在,未来のすべての出来事が「波動」として「ホログラム的な構造」で記録されているという仮説。77
▲
◎ 現代物理学の世界では,過去、現在,未来は同時に存在しているものとされている。79
◎ ゼロ・ポイント・フィールドに記録されている未来は、「可能性の未来」だからである。言葉を返れば,このフィールドに繋がることによって予見される未来は、無数にある未来の可能性の中で,最も起こりそうな未来である。83
◎ 我々の「心」がこの「ゼロ・ポイント・フィールド」と量子レベルで繋がっており、そのため、我々は「ゼロ・ポイント・フィールド」から情報を受け取ることができ,また、この場に情報を送ることができるという仮説でもある。85
◎ 1つの波動は,その波動と「類似の周波数」ものと「共鳴」を起こす。87
まずはネガティブな想念を消すことから始める。
②-b★★★★★
結論:
◎ 子供のように無邪気であること
▲
◎ 邪気=ネガティブな想念がない状態。122
◎ 「無意識を変える方法」として最も大切なのは,
「ポジティブな想念」を抱く方法ではなく,
「ネガティブな想念」を消す方法なのである。127
心の性質=心の双極性:
表面意識にポジティブな想念を引き起こすと同時に無意識の世界にネガティブな想念が生まれる。
②-c★★★★★結論
結論:
<ネガティブな想念を消す方法>
第一:「無意識なネガティブな想念」を浄化していく技法:「人生の習慣を改める」
自然の偉大な浄化力に委ねる:自然の中に身を浸すこと
言葉の密かな浄化力を活かす
和解の想念の浄化力を用いる135
◎ すべての人と和解する162
◎ 感謝であって,誤ることでも,許すことでもない。170
:摩擦や葛藤,反目や衝突がある人と,心の中で,一人ひとりと和解していく技法160
ネガティブな言葉を使わない
ポジティブな日常言葉を使う144
第二:「人生でのネガティブな体験」を陽転していく技法:「人生の解釈を変える」
★ ★★★★【人生の解釈を変える】
★ この技法の最も大切な目的は、「自分の人生を愛する」ということである。189
★ 「ネガティブな体験」を1つ一つ振り返り,その「意味」を再考し、解釈することによって,それが,決して「ネガティブな体験」ではないことを明確にしていく技法であり、それは、言葉を変えれば
★ 人生の「解釈」を変えるという技法でもある。180
核心:★★★★★書き出し0-0-1
運の強い人間とは「自分は運が強い」と信じている人間だ。190
自分が「幸運」に導かれた体験を思い起こすことである。
なぜなら、実は、誰の人生にも「幸運に導かれた体験」がいくつもあるからである。
例えば,あなたは、人生において、次のように思える体験がないだろうか?
「あの人に巡り会えたことで、人生が拓けた」
「あの出来事が起こったことで,道が拓けた」192
彼らは,人生で与えられた「不運に見える出来事」の中にも、成長の糧を見いだし,歩んだのだろう。その事を通じて、「不運に見える出来事」を「幸運な出来事」に変えていったのだろう。208
第三:「究極でのポジティブな人生観」を体得していく技法:「人生の覚悟を決める」
▼5つの覚悟
1自分の人生は、大いなる何かに導かれている、と信じる
2人生で起こること,すべて、深い意味がある,と考える
3人生に置ける問題、すべて、自分に原因がある、と引き受ける
4大いなる何かが、自分を育てようとしている,と受け止める
5逆境を超える叡智は,すべて、与えられる、と思い定める225