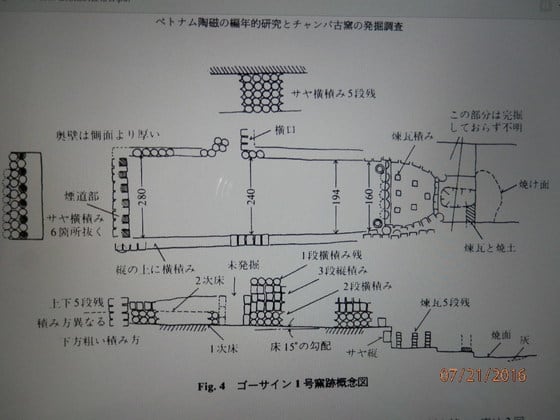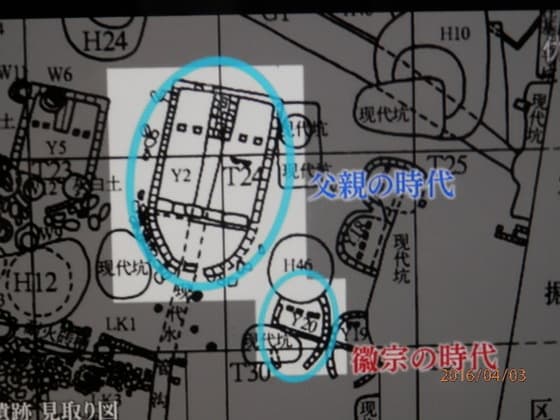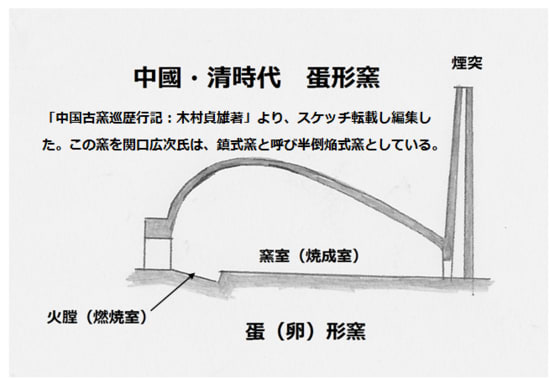<続く>
3.カンボジアの窯構造
3-1.タニ窯
タニ窯については未訪問である。従って情報を得るのは、文献やインターネット検索となる。インターネット検索すると、奈良文化財研究所公開資料(www.nabunken.go.jp/research/cambodia/past.html)と「文化遺産国際協力コンソーシアム」のHPにタニA6号窯の発掘写真が掲載されている。

●所在地
カンボジア王国シェムリアップ州
●窯名称
タニ窯址群A6号窯
●平面プラン
長楕円形
●窯諸元
全長:6.5m
全幅:2.8m
燃焼室長:1.7m
焼成室長:記載なし
全高:記載なし
昇焔壁高:1.4m
●開窯時期
10世紀中葉
●出土陶磁
無釉陶:鉢、甕、四耳壺、広口壺、注口壺
施釉陶:灰釉丸形合子、灰釉筒形合子、灰釉小型盤口瓶
●特記事項
●窯体には天井を支える支柱が数カ所に存在、この特徴はブリラムでも確認されている。
●昇焔壁高さは、ベトナム諸窯に比較し異常と思えるほど高い。
3-2.ソサイ窯
正式な発掘調査は未だ実施されていない様子で、長さ10m前後であろうと云う以外詳細不明である。
<参考文献>
●奈良文化財研究所公開資料
●HP・「文化遺産国際協力コンソーシアム」
●調査報告書:アンコール遺跡群タニ窯址群A6号窯の調査・杉山洋
●論文:アンコール王朝における窯業技術の成立と展開・田畑幸嗣
●調査報告書:アンコール遺跡タニ窯址群第2次調査報告・青柳洋治他
今後は、いよいよタイの窯址の概要を紹介する予定である。
<続く>
3.カンボジアの窯構造
3-1.タニ窯
タニ窯については未訪問である。従って情報を得るのは、文献やインターネット検索となる。インターネット検索すると、奈良文化財研究所公開資料(www.nabunken.go.jp/research/cambodia/past.html)と「文化遺産国際協力コンソーシアム」のHPにタニA6号窯の発掘写真が掲載されている。

(出典:文化遺産国際協力コンソーシアムHP)
以下、出典は調査報告書「アンコール遺跡群タニ窯址群A6号窯の調査:杉山洋」に依る。●所在地
カンボジア王国シェムリアップ州
●窯名称
タニ窯址群A6号窯
●平面プラン
長楕円形
●窯諸元
全長:6.5m
全幅:2.8m
燃焼室長:1.7m
焼成室長:記載なし
全高:記載なし
昇焔壁高:1.4m
●開窯時期
10世紀中葉
●出土陶磁
無釉陶:鉢、甕、四耳壺、広口壺、注口壺
施釉陶:灰釉丸形合子、灰釉筒形合子、灰釉小型盤口瓶
●特記事項
●窯体には天井を支える支柱が数カ所に存在、この特徴はブリラムでも確認されている。
●昇焔壁高さは、ベトナム諸窯に比較し異常と思えるほど高い。
3-2.ソサイ窯
正式な発掘調査は未だ実施されていない様子で、長さ10m前後であろうと云う以外詳細不明である。
<参考文献>
●奈良文化財研究所公開資料
●HP・「文化遺産国際協力コンソーシアム」
●調査報告書:アンコール遺跡群タニ窯址群A6号窯の調査・杉山洋
●論文:アンコール王朝における窯業技術の成立と展開・田畑幸嗣
●調査報告書:アンコール遺跡タニ窯址群第2次調査報告・青柳洋治他
今後は、いよいよタイの窯址の概要を紹介する予定である。
<続く>