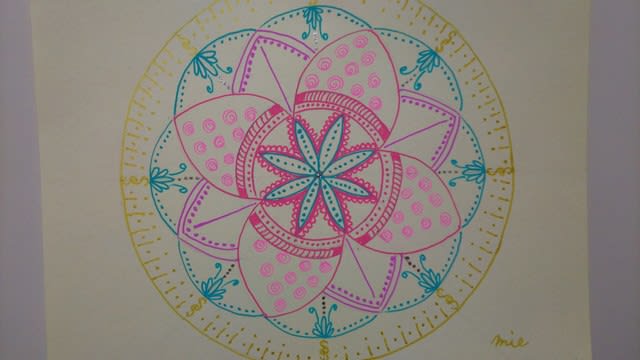茅野市神長官守矢史料館を設計したのは茅野市に生まれた「藤森照信」氏である。
藤森氏は建築史が専門であり、建築士ではなかった。
その彼が初めて設計をしたのがこの建物である。

とても面白い建築をしている。
「見学に来る方が、色々な発見をして行く」と館長が話していた。
屋根からつきぬけている4本の木。
この木の1本には御柱に使用する木を選ぶ時に使用する「薙鎌」が打たれている。


遠近法を利用した階段。
石段のの上に木製の階段があるが、これは電気式の跳ね上げになっている。
普段は上に上がって昇れなくなっている。

昔ながらのガラス板の窓。
光のゆがみが懐かしい。
1枚割れているが、今はこの板硝子が手に入らなくて割れたままになっているらしい。

鍵はこの横棒1本。
部屋の壁や柱を見ていると、平衡感覚がおかしくなる。
いたるところ歪んでいる。
それも故意的に。
1階書庫の扉は扉を重ねると間に隙間ができる。

トイレの窓から外を覗くと黄色い建物がある。
あれも藤森氏が建築した「高過庵(たかすぎあん)」

今日は雨だったので気がついた。
建物に付いている傘立て。

また、外壁に使われている割板はサワラの割り板で木その物の風合いを出している。
史料館を出て、窓から見えた建物に向かう。
藤森氏が私有地に建てたもの。
お茶室である。

低過庵(ひくすぎあん)と高過庵(たかすぎあん)


空飛ぶ泥舟
天気が悪かったので残念であるが、青空の中では空に浮いている船となる。
藤森氏が何を思ってこれらの設計をしたのだろうか。
史料館は見かけは木造のようだが、実際は鉄筋コンクリートである。
私が説明を聞きながら感じたのは、日本の昔からある建物の伝統。
庶民がどんな生活をしていたのかを表現したかったのでないかと思った。
藤森氏は建築史専門である。
日本の家の歴史表現であるのだろうか。
藤森氏については、この本を読んでみようと思っている。
 |
藤森照信の茶室学―日本の極小空間の謎 |
| 藤森 照信 | |
| 六耀社 |