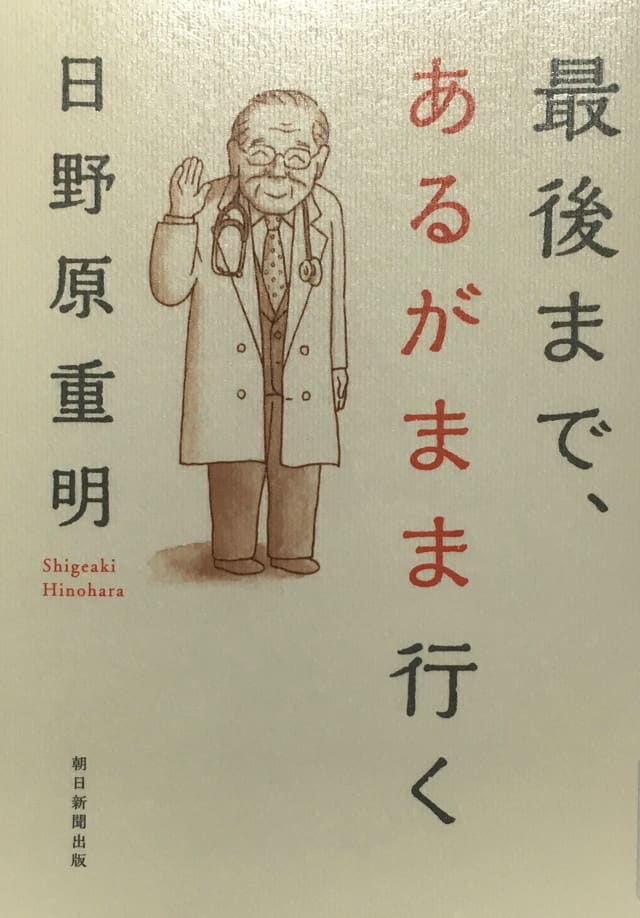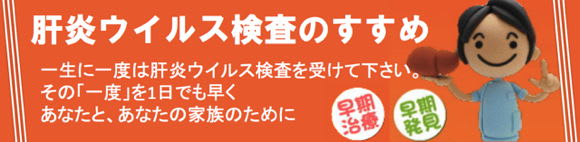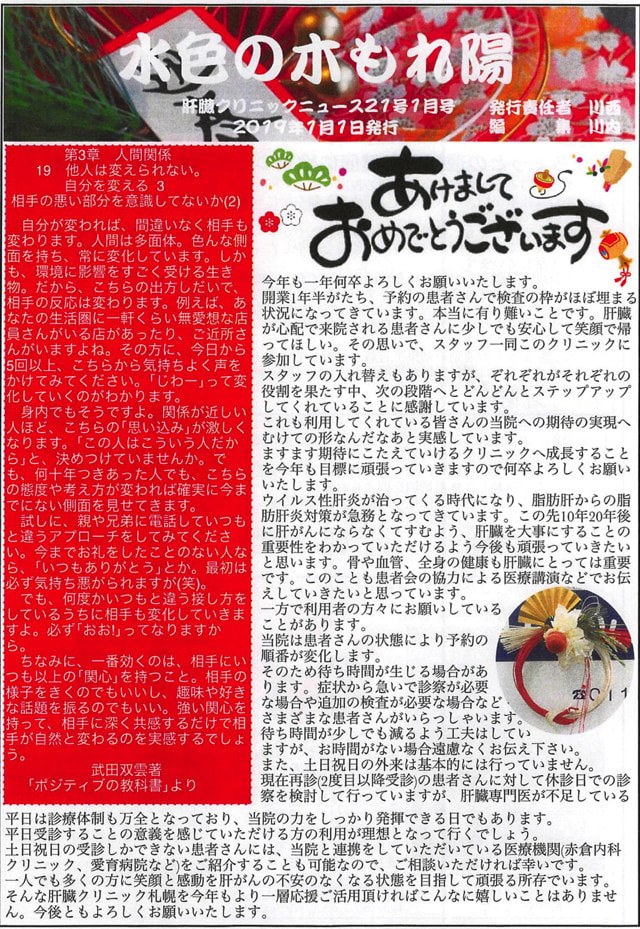以下の文章の写真版です。
待ちに待った薬が製造承認になりました。
ソホスブビル(核酸型NS5Bポリメラーゼ阻害薬)とベルパタスビル(NS5A阻害薬)の合剤のくすりです。C型肝炎ウイルスの肝硬変で脳症や腹水がある非代償期の肝硬変の方でも使える薬です。また、いままで使ってた飲み薬の治療で耐性ウイルスによりウイルスが除去できなかった患者さんにはリバビリンとの併用で24週投与も認められています。リバビリンを使うというハードルがあるのでちょっと悩ましいですが、より排除できる可能性が上がることも確かですね。
1日1回飲めばいい形です。
以下ギリアドの発表を貼付します。
2019年1月8日
<報道関係各位>
ギリアド・サイエンシズ株式会社
「エプクルーサ®配合錠」(ソホスブビル/ベルパタスビル)の日本での製造販売承認を取得
- 日本における非代償性肝硬変を伴う慢性C型肝炎ウイルス感染症の成人患者に対する最初の治療薬 -
ギリアド・サイエンシズ株式会社(以下「ギリアド」)(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:ルーク・ハーマンス)は、本日、非代償性肝硬変を伴うC型肝炎ウイルス感染症の成人患者、および直接作用型抗ウイルス療法(DAA)の前治療歴を有する慢性肝炎又は代償性肝硬変を伴うC型肝炎ウイルス感染症の患者に対する1日1回投与の治療薬「エプクルーサ®配合錠」(以下「エプクルーサ」)(一般名:ソホスブビル/ベルパタスビル配合錠))の日本での製造販売承認を取得しました。
本邦ではこれまで、非代償性肝硬変を伴うC型肝炎ウイルス感染症に対して承認された治療薬はなく、またDAA治療不成功の患者さんに対する治療の選択肢も非常に限られたものでした。エプクルーサの承認取得により、これら難治性の患者さんに対して新たな治療の選択肢を提供することができるようになりました。
「ギリアドは、C型肝炎ウイルスに感染するすべての患者さんが治癒の機会を得られるよう、そして最終的には世界中でこの疾患を撲滅することができるよう、新しいC型肝炎ウイルス治療の開発を続けています。」とギリアドの研究開発部門ヘッド兼Chief Scientific Officerであるジョン・マクハチソン(John McHutchison, M.D.)は述べています。「これまで日本では、非代償性肝硬変を伴うC型肝炎ウイルス感染症の患者さん、または以前のC型肝炎ウイルス治療で治癒しなかった患者さんにとっては、ほとんど、あるいは全くと言っていいほど治療の選択肢がありませんでした。日本の臨床現場でこれらの重要なメディカルニーズにこたえる新たな治療選択肢を提供できることを嬉しく思います。」
今般承認されたエプクルーサは、2015年3月にソバルディ®錠400mgとして承認された核酸型NS5Bポリメラーゼ阻害剤ソホスブビルとNS5A阻害作用を有する新有効成分であるベルパタスビルを含有する新規配合剤です。
エプクルーサは、日本においては、C型肝炎ウイルス感染症患者のウイルス血症の改善を適応としています。非代償性肝硬変を伴うC型肝炎ウイルス感染症の患者は1日1回1錠を12週間、また、以前にDAA治療経験のある慢性肝炎又は代償性肝硬変を伴うC型肝炎ウイルス感染症の患者は1日1回1錠をリバビリンと併用し、24週間経口投与します。
日本におけるエプクルーサの承認は、非代償性肝硬変を伴うC型肝炎ウイルス感染症の日本人患者における第3相臨床試験(試験GS-US-342-4019)のデータに基づいており、この試験では、エプクルーサを12週間投与した結果、92%(47/51例)の患者がSVR12(治療終了後 12週時点のウイルス量が定量下限値未満)を達成しました。SVR12を達成した患者はC型肝炎ウイルス感染症が治癒したとみなされます。また、DAAによる前治療不成功のジェノタイプ1型又は2型のC型肝炎ウイルス感染者を対象とした別の国内第III相試験(GS-US-342-3921試験)においては、エプクルーサとリバビリンを24週間併用投与した結果、97%(58/60例)の患者がSVR12を達成しました。両試験においてエプクルーサは良好な忍容性を示しました。GS-US-342-4019試験で12週間エプクルーサを投与された患者に発現した最も頻度の高かった有害事象は鼻咽頭炎であり、有害事象のためにエプクルーサによる治療を中断した患者はいませんでした。また、GS-US-342-3921試験でエプクルーサとリバビリンを24週間投与された患者に発現した最も頻度の高かった有害事象はウイルス性上気道感染症および貧血症であり、患者の3.3%が有害事象のために投与を中止しました。
ギリアドの代表取締役社長ルーク・ハーマンス(M.D)は、次のように述べています。「大きなアンメット・メディカル・ニーズが残されていた領域である非代償性肝硬変およびDAA治療不成功のC型肝炎ウイルスに感染する患者さんに対して、このたび新たな治療法を提供できることをとても嬉しく思います。また、今回の承認は日本の医療従事者の皆様とともに目指している弊社のC型肝炎撲滅への取り組みが実を結んだものであると自負しております。」
ギリアド・サイエンシズについて
ギリアド・サイエンシズ・インクは、医療ニーズがまだ十分に満たされない分野において、革新的な治療を創出、開発、製品化するバイオファーマ企業です。会社の使命は、生命を脅かす病を抱える世界中の患者さんのために医療を向上させることです。カリフォルニア州フォスターシティに本社を置き、世界35か国以上で事業を行っています。ギリアド・サイエンシズに関する詳細は、www.gilead.comをご覧ください。
将来予想に関する記述
本プレスリリースは、1995年米国民事証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)で定義される「将来予測に関する記述」に該当し、日本国内の医師が非代償性肝硬変とC型肝炎ウイルスに対する抗ウイルス剤治療不成功のC型ウイルス感染患者の治療に、エプクルーサを処方しても有益性が認められない場合があるなどの、いくつかのリスクや不確定要素などの要因を含む場合があります。これらのリスクや不確定要素、その他の要因により、実際の結果が「将来予想に関する記述」と著しく異なったものとなる可能性があります。将来予想に関する記述のみに依拠することはお控えください。これら
3
のリスクやその他のリスクについては、米国証券取引委員会に提出している、2018年9月30日までの四半期のギリアド社四半期報告書(フォーム10-Q)で詳細に説明しています。将来予想に関する記述はすべて、ギリアドが現在入手できる情報に基づいており、ギリアドは将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。
###
Epclusa®とエプクルーサ®は、ギリアド・サイエンシズ社または同社の関連会社の登録商標です。