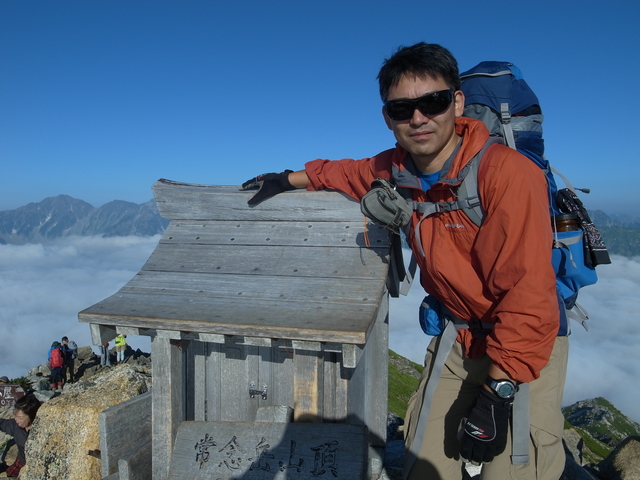お笑いについて、亡くなられた桂枝雀さんが「緊張と緩和論」を提唱した。
有名な話だから、知っている人も多いかもしれない。
まあ、一応、説明しよう。
まず、緊張があって、それが緩和するときに、笑いが起きるという理論である。
たとえば、中学校で全校朝礼があったとする。
べちゃくちゃとお喋りとしている集団があった。
校長先生が、「こらっ、うるさい、お前たち」と怒鳴った。
校長先生の怒りが、全生徒に伝わり、あたりがシーンと静まり返った。
完全な静寂だった。
そのとき、遠くのほうで誰かが「ブーブーブーー」っと大きなオナラをした。
この例で、校長先生が怒るのが緊張で、ブーっとおならするのが緩和である。
もう少し突っ込んで話をしよう。
緊張と緩和は、自律神経と関係している。自律神経には、交感神経と副交感神経がある。
交感神経は、体を活動させるための神経で、人を緊張させ、動く態勢をつくる。
副交感神経は、体を休ませるための神経で、体と気持ちをリラックさせる働きがある。
人は笑うと副交感神経を優位になる。つまり、笑いは、体や気持ちをリラックスさせるのである。
笑いを作るという観点から考えると、まず緊張状態をつくり、そこでボケて、緊張を緩和させる。
これが、笑いの基本である。
もう少し突っ込んで検討すれば、感情はすべて自律神経と関係している。
不安、恐れ、怒り、この辺の感情は、交感神経が関係している。
例えば、女性が夜道を歩いていると、後ろから誰かがつけてくる。
そのとき、不安、恐れという感情が起こる。気が強い女性だと怒りが生じてくることもある。
行動を促す交感神経が優位のときは、逃げるかそれとも戦うかの選択を迫られる。
逆に、副交感神経は、笑ったり、泣いたりする感情に関わっている。
さっきの夜道の例で考えれば、後ろからつけてきたのが、彼氏だったらホッとして笑う。
本物の暴漢だったとして、襲われて、服を脱がされレイプされる直前で、彼氏が助けに来てくれたときは、ホッとして涙が出てくるだろう。
笑うか、泣くかは、緊張と緩和の強さに関わっている。
緊張と緩和の度合いが軽ければ、笑いが起きるし、緊張と緩和の落差が強いと泣いてしまう。
テレビでドッキリをすることがある。ほどよい緊張だと笑いが生じ、強すぎると泣いてしまう。
僕たちの社会には、今、新型コロナが蔓延していて、ちょっと強めの緊張状態にある。
緊張状態は、さっき言ったように、交感神経が優位なので、不安、恐れ、怒りの感情になりやすい。
このように緊張状態が強いと、ハハハと大声で笑いづらい。不謹慎に思われるからである。
でも、僕たちには息抜きが必要だ。リラックスする笑いが、必要なのである。そうじゃないと疲れ切ってしまう。
僕は、それを打破するヒントが、ユーモアにあると思っている。
ユーモアは、人が不条理や不合理、愚かさに直面したとき、それをあたたかく見守り、やさしい気持ちで笑い飛ばすことだ。
ユーモアは、人を傷つけないやさしさと、不条理を笑い飛ばせる強いハートが必要だ。
だから、ユーモアを学ぶことは、やさしさと強さを学ぶことでもある。
人生の不条理にあったときは、ユーモアで自分自身を笑い飛ばしていこう。
僕はバス停のベンチで座って、バスが来るのを待っていました。
向こうから、みすぼらしいオッサンが、トコトコとこっちにやってきました。
オッサンは、髪が一本もない本物のツルッパゲでした。
それで、たくさん席があるのに、わざわざ僕のとなりの席に座りました。
彼は僕の方をチラッと見て、禿げた頭をなでながら、小さい声でつぶやきました。
「あー、もうそろそろ、散髪に行かないと、ダメだなあ」
じゃあ、またね。