合成洗剤の歴史
【合成洗剤以前の合成界面活性剤】
1834年 石けん以外の最初の合成界面活性剤が作られる。
(ドイツのルンゲ)
オリーブ油に濃硫酸を作用させてアルカリで中和。
硫酸化油というもので、 洗浄力はあまりないが、
染料を分散させる性能が優れていた。
トルコ赤染に使用「トルコ赤油」と呼ばれる。
↓
1896年 ヒマシ油の硫酸化油(※1、2、3参照)が作られる。
ロート油ともよばれ現在でも染色に使われる。
*******************************************
 参照→コトバンク
参照→コトバンク
※硫酸化油(りゅうさんかゆ)
1)ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
ロート油ともいう。ひまし油,オリーブ油,綿実油,魚油や大豆油
などに濃硫酸を 35℃以下で作用させ,未反応の硫酸を洗い去
ったのちアルカリで中和したもの。黄色ないし褐色の粘稠な液体。
水に対する溶解度,表面活性,耐硬水性,浸透力,乳化力など
がすぐれているうえに安価なので,農薬,繊維工業,染色工業,
皮革工業,金属工業などで多く使われる。
2)デジタル大辞泉の解説
ヒマシ油などの脂肪油を濃硫酸と反応させ、水酸化ナトリウム
やアンモニアなどのアルカリ性水溶液で中和したもの。
1世紀半ば、オスマン帝国時代の赤色の天然染料、トルコ赤の
染色の助剤として利用されたため、トルコ赤油、ロート油ともいう。
3)日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
19世紀の中ごろに、赤色の天然染料であったトルコ赤(アリザリン)
によるまだら染めを防ぎ、均一な染色を得るために用いられた薬剤。
そのため別名をトルコ赤油あるいはロート油とよばれている。
初めはオリーブ油を硫酸で処理したものが用いられたが、
1875年ごろひまし油の硫酸化油が現れてから主流はそれにかわった。
1928年以降に新しいいくつかの合成界面活性剤が登場するまでは、
せっけんを除いての唯一の界面活性剤として長い間繊維工業で
用いられてきた。現在でも酸性染料の染色助剤として用いられて
おり、このほか農薬の乳化剤、分散剤、あるいは植物を用いた
皮革のなめし助剤に用いられている。[早野茂夫]
********************************************
【合成洗剤の誕生と発展】
≪世界初の合成洗剤≫
・アルキルナフタリンスルホン酸塩
1917年 ドイツで石炭から合成
ナフタリンに濃硫酸を作用させて作られたもの
当時のドイツは第一次大戦(1914~1918)
経済封鎖を受けて食用油脂が非常に不足していた。
↓
油脂に頼らない洗浄剤を開発する必要に迫られていた。
↓
しかし大戦後、再び石けんへ
(アルキルナフタリンスルホン酸塩洗浄力が劣っていたため)
↓
・アルキル硫酸エステル塩(AS)
1928年 ドイツのベーメ社によって開発
天然の動植物油脂から作られた高級アルコール(炭素数
の多いアルコール)に濃硫酸を作用させて作られたもの
↓
・アルキルスルホン酸塩(SAS)
・アルキルベンゼンスルホン酸塩(ABS)
1933年 ドイツのI.G.社によって開発
実用的な合成洗剤の第1号
食用油脂に頼らないものとして石炭や石油から作られた。
↓
1936年 アメリカのナショナルアニリン社がABSの製造をはじめる。
石けんの代替として軍需用に使われた。
↓
1943年 ナショナルアニリン社とモンサント社が
ABSを洗剤として販売。各社も追随。
第二次大戦中にドイツで開発されたビルダー(助剤)の技術を
加えて、第二次大戦後の石油化学の発展に伴い、洗剤と言えば
ABSを指すほどまでに急速に普及した。
1953年 アメリカで合成洗剤の生産量が石けんの生産量を上回る。
戦時中は軍需用に大量に消費されていた石油が、
戦後は安価に使えるようになったため石油化学工業が発展。
【 日本での合成洗剤 】
1933年 ドイツから技術を輸入してASの製造が始まる。
↓
・高級アルコール系中性洗剤「モノゲン」(ABS洗剤)
1937年(昭和12年) 第一号家庭用合成洗剤として発売。
当初はABS洗剤はあまり伸びず、高級アルコール系洗剤が先行。
↓
1959年(昭和34年)頃から、ABSが日本の合成洗剤の中心。
↓
1950年代半ば以後、電気洗濯機の普及に伴い、合成洗剤が急速に普及
↓
1963年(昭和38年)合成洗剤の生産量が石けんの生産量を上回った。
【合成洗剤のソフト化】
≪ 生分解が困難なハード型 ≫
ABSはアルキル基に枝分かれ構造を持っていたため、
極めて分解しにくい物質だった。
↓
1953年頃から、アメリカやイギリスで、下水処理場の水が
泡だって下水処理が困難になるという問題が起こり始めた。
↓
1961年(昭和36年)ごろから日本でも河川の発泡問題が起こり
大きな社会問題となった。
↓
≪ 生分解が困難ではないソフト型 ≫
アルキル基の枝分かれ構造のない直鎖化合物を用いた洗剤
への転換(ソフト化)が進められた。
アメリカでは、1965年に洗剤のソフト化率が95%に達した。
日本でも、1971年(昭和46年)に洗剤のソフト化率が97%に。
現在、日本ではABSは使用されていない。
≪ソフト型洗剤の成分として用いられた界面活性剤≫
・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(LAS)
・アルキル硫酸エステル塩(AS)
・アルファオレフィンスルホン酸塩(AOS)
・ポリオキシエチレンアルキル硫酸塩(AES)
【洗濯用以外の合成洗剤の誕生】
1950年代中頃 日本では高級アルコール系シャンプーが登場。
(当初は粉末状のシャンプー)
↓
1959年(昭和34年)台所用洗剤が発売される。
↓
1960年代 住居用洗剤も発売される。
台所用洗剤も、当初は粉末だったが後に液体洗剤が発売。
当時、回虫が多かったこともあり、食器だけでなく
野菜や果物も洗剤を使って洗う習慣が普及した。
【富栄養化と無リン化】
洗濯用合成洗剤の助剤としてトリポリリン酸塩が使用されていた
ことから、合成洗剤が(※)富栄養化の原因の一つとして問題視
されるようになった。
≪湖沼の富栄養化問題≫
1965年ごろから
北ヨーロッパ、アメリカ、カナダで起こった。
新たな環境問題として、河川・湖沼や海の富栄養化
と合成洗剤との係わり方が注目される。
↓
1969年(昭和44年)日本では、琵琶湖で初めての淡水赤潮が起こる。
↓
1972年(昭和47年)瀬戸内海で赤潮の大発生があり社会問題となった。
↓洗剤メーカーは無リン洗剤の開発に取り組む。
1973年(昭和48年)第一号の無リン洗剤が発売。
↓コストや使い勝手の面から普及しなかった。
******************************************
※富栄養化 参照→ こちら
湖沼や湾などの水域で窒素やリンなどの「栄養塩類」が多くなること。
(有機物によって水が汚れる「有機汚濁」とは異なる)
もともと「富栄養化」というのは、生まれたばかりの湖に、
だんだんに栄養塩類が増えていき、植物が繁殖し湖が沼と
なってやがて消滅していく、という自然現象。
近年問題になっている「富栄養化」は、その原因が生活廃水
や工業排水、農業廃水などの人為的なものであり、かつ急速
に進んでいる点が問題とされている。
「栄養」というのは、植物性プランクトンの成長のための栄養分。
窒素やリンが急速に増えると植物性プランクトンが急速に増えて
生態系のバランスを崩し、見た目にも汚くなって悪臭を発したり、
魚などの他の生物にも影響を与えるため、良いことではない。
窒素やリンは、現在の下水処理では十分に取り除くことができず、
放流されてしまう。台所洗剤やシャンプーに含まれる窒素やリンは、
かつての洗濯用洗剤に含まれていたリンと比べると、量的には
ずっと少なく、ただちに富栄養化を起こすとは言えないが、窒素
やリンを含む洗剤が増えてきているのだということは知っておきたい。
******************************************
≪第1次石油危機(オイルショック)≫
1973年(昭和48年)10月、第4次中東戦争が勃発。
アラブ産油国が原油の生産制限を行ったため、石油価格が暴騰。
↓
≪洗剤パニック≫
このとき日本では、流言飛語に惑わされた人々が洗剤の買い占めに走った。
↓
翌1974年(昭和49年)
粉末合成洗剤の販売量がはじめて大幅に減少。
「省エネ」が流行語にもなったように、
資源を大切にしようという気運が芽生えた。
洗剤メーカーも省資源に対応して小型化洗剤を発売したが、
一時のブームに終わり、また大型洗剤に戻った。
↓
1980年(昭和55年)琵琶湖富栄養化防止条例施行。、
1980年(昭和55年)リン酸塩の替わりにゼオライトを配合した
無リン洗剤が発売された。
↓これは消費者に受け入れられて普及。
1982年(昭和57年)霞ヶ浦富栄養化防止条例が施行。
有リン洗剤の販売・使用の禁止。
現在日本では、家庭用洗剤はほぼ100%無リン化された。
(ただし、業務用洗剤にはリン酸塩を含むものが今でも使用されている)
【洗剤のコンパクト化】
コンパクト化洗剤は、オイルショック後に一度はすたれたが、
1987年(昭和62年)に新しいコンパクト洗剤が発売された。
・持ち運びが楽
・置き場所を取らない
ゆえに人気を呼び、ヒット商品となる。
その後、柔軟仕上げ剤や台所用洗剤もコンパクト化される。
今日では、洗剤の生産量の伸びは、ほぼ飽和状態。
浴用では、それまで固形石けんが根強く支持されていたが、
ボディシャンプーが普及しはじめた。
1990年代以後、浴用石鹸の生産量は減少傾向。
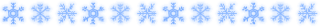

 石鹸百貨HPは→ こちら
石鹸百貨HPは→ こちら
石鹸の基礎知識から使い方まで、石鹸生活の総合情報サイト様です。























