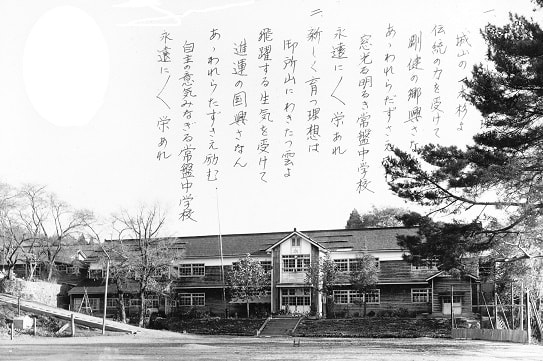去年の9月中旬に背中炙り峠の途中で撮影しました。このトンガリ頭の実を覚えていましたが、名前が出てきません。そのため、投稿しないままになっていました。ところが、尾花沢市の牛房野で、別の話がきっかけでこの木の正体が分かりました。3日前ほど、水辺の保全に関する用事で、牛房野のに出かけました。すると、柴(しば)を束ねる時に使う雑木の話になりました。囲炉裏に焚く(畑沢では「クベル」という。)木は、山で一束ごとに束ねられます。その時、束ねる材料は縄ではなくて、山のしなりやすい雑木が使われます。その雑木は、「ハスダミ」だと言うのです。私が「それは、正式な名前ですか」と尋ねると、「んだ。ハシダミだ」。いつの間にか「ス」が「シ」に変わっています。それでも、私は強い疑いを持っていました。と言うのも、山にしっかりと密着して生活していた地域では、しばしば正式な和名とは別に地域独特の名前が付けられているからです。例えば、カンジキに使う「アブラチャン」は、畑沢では「トリキ」と呼ばれていました。
さて、疑いの心を持ったままの私は、家で調べてみました。いつもの、インターネットでの検索です。「ハシダミ」のキーワードで画像を検索すると、出てきました。その中に見覚えのある画像がありました。今回、投稿している「ツノハシバミ」です。「ハシバミ」の画像もありました。「ハシダミ」ではなくて「ハシバミ」だったようです。やはり、東北では「ズ」と「ダ」の発音はいろんなところで元気です。「ダ」が「バ」を凌駕していました。
正式和名「ツノハシバミ」は、小学校時代の思い出があります。畑沢分校から少しだけ県道を上(かみ)の方へ進むと、山の斜面が道路の右側に接しています。当時、猿のごとく木登りをしていた私たちは、この木の実を見つけました。私たちの中の一人が「こえづ、食えんだ」と教えてくれました。しかし、写真でも分かるように実の表面には細かい毛が生えています。この毛がやっかいもので、手の皮膚にチクチクと刺さります。そこで、砂利道の上に木の実を置いて、靴(通称「短靴」と呼ばれていたゴム製の靴)で木の実を押し付けながら転がしました。猿はここまで知恵が回りません。毛がなくなった実を剥いて食べました。味は全く覚えていません。たいして美味いものではなかったのでしょう。栗、木通、グミなどを食べ慣れている高級な山猿を満足させるものではありませんでした。しかし、一度でも「食べられる」と聞いた以上は、見つけたら最後、決して見逃さないようにしていました。その後、もう一度だけ食べる機会がありましたが、それからずっと見つけることができなくなっていました。久々の再会でした。