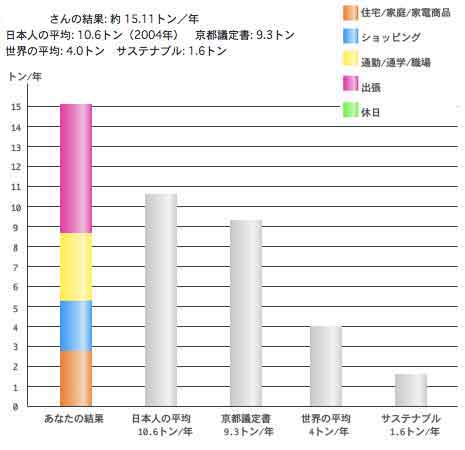先日の取材先で発見したデザインティッシュボックス。
不勉強で、こういうの初めて見ました。
なんでもDUENDEというブランドが作っているモノなんだとか。
そのHPには、
Duende(デュエンデ)は2002年9月にスタートしたコンテンポラリーな家具とインテリアプロダクトを紹介するプロダクトレーベル。毎年ロンドンで開催される世界的に名高い「100% Design」への出展からスタートしました。
ミニマムな中に温かみを感じるようなデザインをコンセプトに商品開発しています。
日本の生活の中から生まれたデザインを世界へ。
海外の生活から生まれたデザインが日本へ。
様々な国籍、様々な素材、様々なカテゴリー、それらうまくコーディネートし、
国境にとらわれずどの国でも親しんで頂けるプロダクト作りを目指します。
というふうに紹介されていました。
で、このティッシュボックスは
横置きが定番のティッシュケースを縦置きにする事で、従来に比べ、より最後までティッシュをスムーズに引き出す事が出来ます。
縦置きのフォルムは、省スペースですっきり見せられ、パウダールーム・デスクトップ等様々なシーンをさり気なく演出できます。底面が広がっているため安定感があり、ティッシュを引く力程度では倒れる事はありません。2006年日本産業デザイン振興会グッドデザイン賞(Gマーク)を受賞。
ということなんだとか。
2006年受賞ということなので最近のプロダクツですが、
日本的な生活からのデザイン発信という志向性が伺えて
なかなか好感度が高い製品だと思います。
わが家でも、食卓などにティッシュボックスが置かれていますが、
どうにも納まりが良くない上に、ぬいぐるみみたいなのに入っていて、
「モロではない」という程度の装飾性のものしかなかった。
どうやってこれ、入手したか聞いたら、結婚式の引き出物でもらったそうで、
HPで値段を調べたら3600円するそうです。
どっかに売っているんでしょうが、
なぜかHPでは通販していないようです。
こういうの困りますね。
せっかくいいなと、情報を見て感じても、
問い合わせしなければいけないとか、お店で探さなければならない
というのは、忙しい現代人には難しい。
すぐその場から、買えるようにすべきですね、
とくにこのようなニッチタイプの商品については。
買いたいなと思っているのですが、そのことをすぐに忘れる(笑)。
トリ頭にはなかなか入手困難なんですよね(笑)。