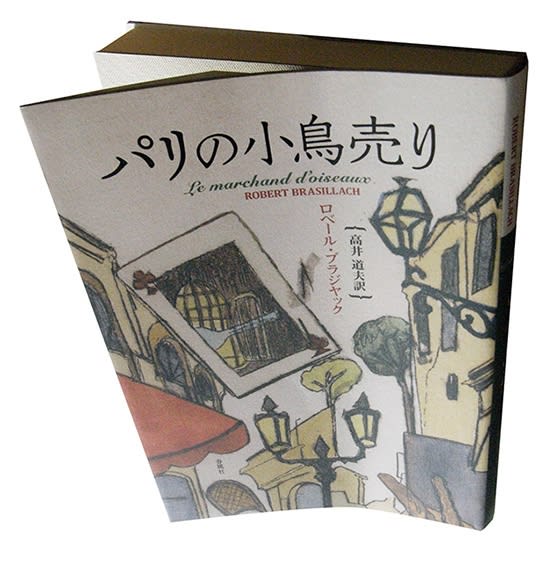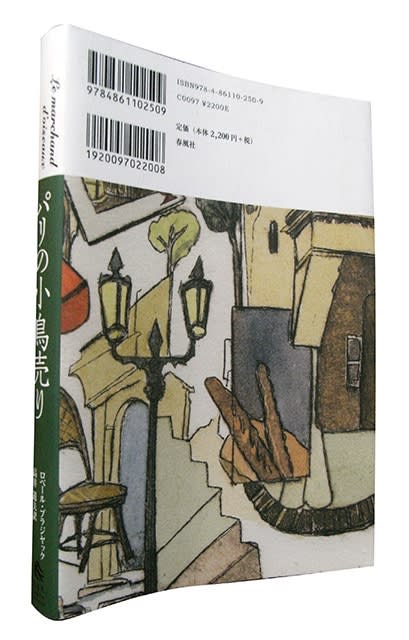ボフミル・フラバル『剃髪式』

石油ランプの丁寧な描写が続く。
ビール醸造所の静かな生活が描かれていく。
穏やかな小説。
と思っていたら、とんでもなかった。
これどこまで本当?
小説に向けてする質問ではないが、はじけすぎて想像が追いつかない。
だんだん馴れてくると、いくらか余裕を持って楽しめるけれど、さらに上をいく出来事が。
150ページほどの薄い本のなか、何度心がざわついたことか。
最後は、これで終わってしまうのか、やっとわかってきたところなのに。
ちょっと心残りなので、もう一度最初から読み直してみる。
幸いなことに、フラバルの本は、まだほかにもあって、容易に手に入りそうだ。
デザインは安藤紫野氏。(2018)

石油ランプの丁寧な描写が続く。
ビール醸造所の静かな生活が描かれていく。
穏やかな小説。
と思っていたら、とんでもなかった。
これどこまで本当?
小説に向けてする質問ではないが、はじけすぎて想像が追いつかない。
だんだん馴れてくると、いくらか余裕を持って楽しめるけれど、さらに上をいく出来事が。
150ページほどの薄い本のなか、何度心がざわついたことか。
最後は、これで終わってしまうのか、やっとわかってきたところなのに。
ちょっと心残りなので、もう一度最初から読み直してみる。
幸いなことに、フラバルの本は、まだほかにもあって、容易に手に入りそうだ。
デザインは安藤紫野氏。(2018)