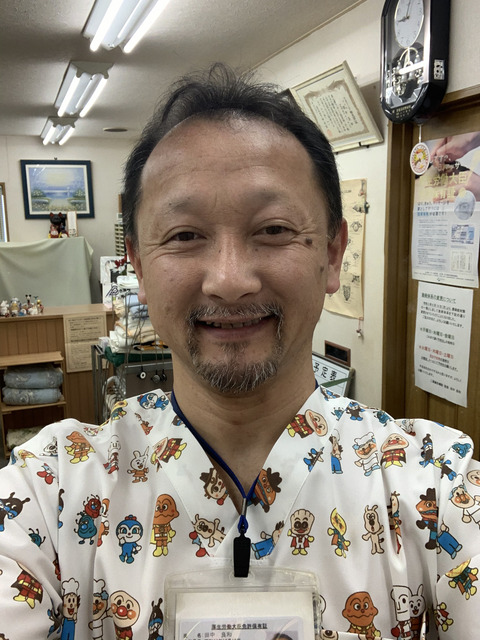本日は二十四節季でいうところの「小満」です。
陽気が増して、万物が成長する「氣」が次第に長じて天地に満ち始めるころです
東洋医学は「氣」や「血」の調整を行うことで、健康に自分の寿命まで長寿を実現する医療だと思います。
「氣」は見えませんが、必ず存在します。
空気は見えませんし、電気は明かりや動力としては「見える」かもしれませんが、電気自体はどなたも見たことがないのではないでしょうか
しかし、そこに確実に存在し、人は特にその恩恵をいただいています。
だから、「氣」というと怪しく思われるのかもしれませんが、存在するのです。
人間の身体も細胞(解糖系やミトコンドリア系)が放出するエネルギーで動いています。これは質量がありません。顕微鏡でも見えません。でも、そこには存在し生理学の常識となっています。
エネルギーは「氣」の一部分ということも言えるでしょう。
としたら人体には「氣」は存在するということです。
鍼灸治療は「氣」「血」を調整する治療方法ですが、やはり、その中でも現代の自然科学や宇宙や地球、天体など大自然の物理学、分子生物学など、昔と比較して圧倒的に、人が客観的に捉えることができる範囲は増加しています。
鍼灸治療も現代の中に息づく医療とするなら、科学的根拠やそれに基ずく医療(EBM)とよく言われておりますが、目に見える部分での鍼灸効果の証明ということも、医療の中に入っていくのであれば必要なのだと思います。
目に見えるものと見えないものの両方から捉える感性が、私が行っているこの仕事、鍼灸治療には必要なのだと感じます。その時々で対応すればいいのですが、どちらへ傾いてもいけないバランス感覚を持つ存在(調和)こそが、場に適応して進化発展し、生き残っていくのかと感じます。
そんなことを感じつつ・・・本に目を通すと
佐藤一斎さんの言葉が目に入ってきました。
月を看るは、清氣を観るなり。円欠晴翳(えんけつせいえい)の間に在らず。
花を看るは、生意を観るなり。紅紫香臭(こうしこうしゅう)の外に存す。
【訳】 月を眺めるのは、清らかな氣を鑑賞するのである。
円くなったり欠けたり、晴れたり翳(かげ)ったりするのを見るのではない。
花を見るのは、生き生きとした花の心を鑑賞するのである。
花びらの紅や紫といった色、香りや匂いの外にこそ見るべきものがある。
『佐藤一斎 一日一言 ~言志四録を読む~』 渡邉五郎三郎 監修より
素敵な、深い言葉です。
そのような感性も大切にしながら、仕事に、日常生活に心豊かに活かしていければ、また違った世界や、新たな発見があるのかもしれませんね。



最後までお読みいただき、ありがとうございます