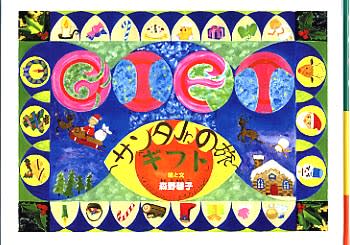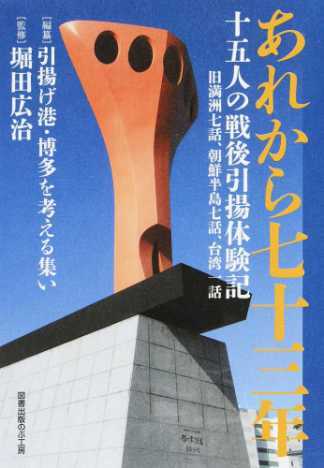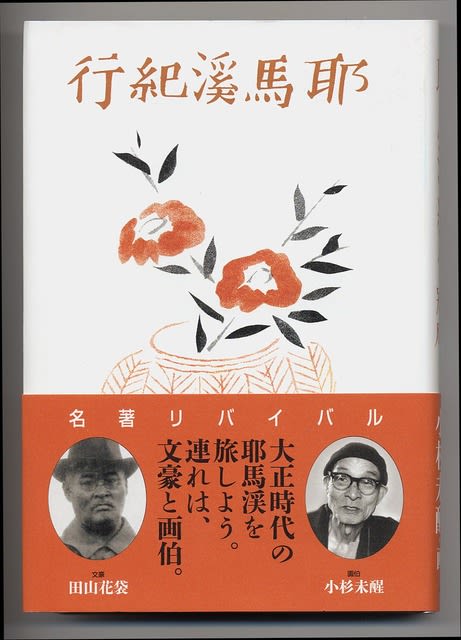◆『笑顔の認知症』 おかげさまで、二刷できました。
おかげさまで、二刷できました。
◆新聞に広告を出稿したので、お問い合わせをいただいています。紀伊國屋書店や丸善・ジュンク堂などのネット書店、アマゾン、実店舗は、地方小出版流通センターを通じて全国供給、きんぶん図書を通じて北部九州供給をしているので、まだ置いていないお店でも、注文いただければ必ず入手できます。書籍コードは、978-4-901346-64-1 本体1400円+消費税。
◆もちろん、のぶ工房へのメール(出て来るページの封筒マークをクリックしてくださいね)やファクシミリ092-524-1666でも受け付けています。送り先と電話とお名前をお忘れなく。コールバックでこちらからお問い合わせすることがございます。この場合は一冊送料180円、2冊以上は送料サービスします。
◆認知症にかかったおじいちゃんやおばあちゃんの事情をお子さまに知らせるためにも役に立ちます。たとえばこんな感じだと。離れて暮らしていても、たまに会いに行くことはあるでしょう。そのときにも、これを知っておけば心の準備になるでしょう。
◆大人だって知っておくべきことがあります。脳に何が起こっているのか、など、いろいろたくさん書いてあります。
◆受診すべきか様子をみるべきかどうか迷ったときにも。まだあまり気にしなくて良いのか、注意深く観察しておいたほうがいいのか、どういうところを観察すべきか、あるいは、一刻も早く受診した方がいいのか。
◆当人が医院に行きたがらないとき、どうしたらいいのでしょう。
◆そして、お医者さんを最大限に活用するかかり方も書いてあります。
◆どんな薬をもらうことになるのか、よく処方される薬についても説明します(そういえば、もらっている薬についてよく聞いてなかった、という場合にも)。
◆あと、何と言っても大事なのは、予防法。この本は、三分の一近くが、予防法と進行防止法です。食べ物、お昼寝、心掛け。どんな病気も生活習慣が関わってくるというのは共通してます。自分の意志でなんとかなるところはなんとかしましょ。最新の情報をどうぞ。
認知症になりたくてなる人なんていないのです。誰にも必要な予防策と心構えを、まずはこの一冊で。