
渡辺哲夫さんの「知覚の呪縛―病理学的考察」(ちくま学芸文庫)を読みました。
************************
<内容(「BOOK」データベースより)>
重篤な分裂病者の言葉に徹底的に耳を傾け、その世界に身を投じ、自らを変容させ、
その変容を論理的に記述、分析、哲学的考察を加えることで、初めて立ち現れてくる分裂病者の世界。
私たちが抱く「分裂病」の一般的イメージを根底より破壊する衝撃の一冊。
<著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)>
渡辺/哲夫
1949年茨城県生まれ。
1973年東北大学医学部卒業。都立松沢病院、東京医科歯科大学務経を経て、現在、正慶会栗田病院副院長。
東京医科歯科大学医学部臨床助教授。医学博士。精神病理学専攻.
************************
この本はとんでもない本です。<劇薬につき取扱注意>の本です。
自分の自我の安定があるときに読まないと、あちらに持って行かれるので要注意。
素人は読まない方がいいと思いますが、気になる人はこっそりと読んでください。
マルケスの「百年の孤独」の中で、無限(夢幻?)に出てくる「語り」を聞いていて、無性にこの本が思い出されたのでした。
→「ガルシア・マルケス「百年の孤独」」(2013-05-23)
・・・・・・・・・
この本は1986年に西田書店から出た本。
田口ランディさんが著作(「モザイク」だったかな?)で紹介した縁で、その後ちくま学芸文庫で2002年に再販。
当時、ランディさん本人から頂いたのです。もう11年前かぁ。
ランディさんの後書き文庫版解説にも、
「四十歳になって、本書『知覚の呪縛』と出会ったときの衝撃は、十五歳のときに(セシュエー『分裂病の少女の手記』から)分裂病の存在を知ったときの衝撃の百倍もあった。メガトン級のショックを受けた」と書かれている。
確かに、「人間」という存在を立体的に見る過程において、自分も同じようなショックを受けたものだ。
当時、自分が学生の時に精神科を回っていろいろ考えていたこと。
その後、10年近く医療現場で働いて考えたこと。
そういうのが色々とリンクした。
学生時代は臨床経験がなかった。逆にいえばそれだけ純粋。
今は臨床経験が豊富で現実を数多く見た。逆にいえばそれだけ事実に縛られることになる。
そういう風に学生時代の「自分」と、今の「自分」とを2枚重ねにしながら、読んだ。
■
この本の主人公Sさんにおいて、Sさんの知覚領域は全て「ワラ」、すなわち偽物でできているとされている。
ただ、Sさん自信もSさん自信により「消去」されてしまっていて、その「ワラ」世界にもいない。
精神科領域で言う「世界没落体験」の渦中にあるSさんの事例。
ただ、Sさんは本当の世界である「オトチ」世界を求め、「オタカラ」という手がかりを求めるために「トグロ巻き」という儀式的な行為を日々続ける。
・・・・
まるでSF世界のようだが、これは実際にある一症例。
■
精神科医の渡辺哲夫先生は、「分裂病」(今では統合失調症という名前に改変された。当時の用語である「分裂病」を使う)という名前で状態を固定化するのを巧みに回避する。
渡辺先生は「分裂病と名付けられた事態」と呼んでいた。
名詞の持つ固定力を恐れたのだろう。
確かに、僕らは「名詞」化された名前で呼ぶことで、それを自分のイメージで勝手に固定化して、その用語に縛られることがある。自分で自分の檻をつくり、その中でひとり勝手に閉じ込められるように。
渡辺先生は、あくまでも流動的な「事態」であるとする。
それは、おそらく自然現象の中で雨や嵐や台風や大地震が来るような、向こうから襲ってきて避けられない「緊急事態」のような状況として、「精神の病」をとらえているからだろう。
「病」は、確かに自分が引き金をひく側面と共に、「あちらから」やってくる側面も持つ。
■
(「知覚の呪縛」より)
=========================
隠された事実などない。一切は露出している。
=========================
どこから見ても精神荒廃状態にあるSの中で、ただ言葉のみがきちんとしていた。
=========================
Sと言う名の自己同一的な個人がいない。
=========================
「世界没落は世界分裂ないし世界二重化なのである。」
=========================
Sさんは知覚できる領域は全て「ワラ」世界として、すべて偽物だ、としている。
彼女にとっての「現実」は、確かに彼女独自でオリジナル。
誰にも共有されえないかもしれない。
ただ、彼女にとってはすべての真実もすべての嘘も「隠された事実などなく、一切は露出している」から、そういう認知世界においては、むしろ全てが「まがいもの」として認知されてしまうようだ。
自分にとってあまりにもショックなことが起きた時、
「こんなはずはない!こんなことが自分に起こるはずがない!こんなのはすべて嘘か夢だ!」
と、あるがままの現実を「受け入れがたい」ことが起こるだろう。
そのあまりにも強く思った「念」は、この世界の認知を全て塗り替えてしまい、固着化し固定化することが起きるのかもしれない。
身近な人の死、別離、天災・・・などが自分の身に起きた時、小さいレベルから大きいレベルまで、内的世界では日常的に密かに起きている現象かもしれない。
「受け入れられないもの」に出会ったとき、たいていはなんとか自我が調整しながら「受け入れがたいものを受け入れる」という矛盾を同居させて生きていくのだけれど、そこで奇妙な形で「受け入れてしまった」ときに、こういう事態が起きるのかもしれない。
こういう事態に陥る危うさを、人間は誰もが持っている。
そして、こういう事例に医療の臨床家が出会うと、途方に暮れる。
私に何ができるのだろうか・・・、と。
ただ、医療では、相手を「他人」として分離していると確かに何も起こらないが、相手のありのままの人生を、「起こりえたわたしの人生の一つ」として「自分」事として共感的な眼差しで愛や思いやりと共に接していると、「何か」が起きることがある。そして、それは「治癒」につながることもある。
臨床家は、ある意味でそういう奇跡が起きやすい場を演出しながら、根気よく奇跡の到来を待ち続ける存在なのかもしれない。砂漠での雨乞いの儀式のように。
楳図かずお先生の「わたしは真悟」という漫画史に残る大傑作漫画の中で、
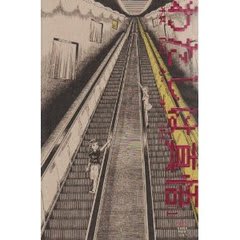
****************
『奇跡は 誰にでも
一度おきる
だが
おきたことには
誰も気がつかない』
****************
という謎めいたメッセージがある。
そんなことをふと思い出した。
*「WA・TA・SI」(2012-03-11)
*「楳図かずお「イアラ」」(2009-01-22)
■
本書の中では、フランツ・カフカの「「掟の門」が引用される。
本書より少し長めに引用してみる。
-----------------------------------
「カフカ短篇集」(岩波文庫)カフカ、池内 紀 (1987/1/16)

-----------------------------------
掟の門前に門番が立っていた。
そこへ田舎から一人の男がやって来て、入れてくれ、と言った。
今はだめだ、と門番は言った。
男は思案した。
今はだめだとしても、あとでならいいのか、とたずねた。
「たぶんな。とにかく今はだめだ」
と、門番は答えた。
掟の門はいつもどおり開いたままだった。
門番が脇へよったので男は中をのぞきこんだ。これをみて門番は笑った。
「そんなに入りたいのなら、おれにかまわず入るがいい。
しかし言っとくが、おれはこのとおりの力持ちだ。
それでもほんの下っぱで、中に入ると部屋ごとに一人ずつ、順ぐりにすごいのがいる。
このおれにしても三番目の番人をみただけで、すくみあがってしまうほどだ」
こんなに厄介だとは思わなかった。
掟の門は誰にも開かれているはずだと男は思った。
しかし、毛皮のマントを身につけた門番の、その大きな尖り鼻と、ひょろひょろはえた黒くて長い蒙古髯をみていると、おとなしく待っている方がよさそうだった。
門番が小さな腰掛けを貸してくれた。門の脇にすわっていてもいいという。
男は腰を下ろして待ち続けた。何年も待ち続けた。
その間、許しを得るためにあれこれ手をつくした。
くどくど懇願して門番にうるさがられた。
ときたまのことだが、門番が訊いてくれた。
故郷のことやほかのことをたずねてくれた。
とはいえ、お偉方がするような気のないやつで、おしまいにはいつも、まだだめだ、と言うのだった。
たずさえてきたいろいろな品を、男は門番につぎつぎと贈り物にした。
そのつど門番は平然と受けとって、こう言った。
「おまえの気がすむようにもらっておく。何かしのこしたことがあるなどと思わないようにだな。しかし、ただそれだけのことだ」
永い年月のあいだ、男はずっとこの門番を眺めてきた。
ほかの番人のことは忘れてしまった。
ひとりこの門番が掟の門の立ち入りを阻んでいると思えてならない。
彼は身の不運を嘆いた。
はじめの数年は、はげしく声を荒らげて、のちにはぶつぶつとひとりごとのように呟きながら。
そのうち、子供っぽくなった。
永らく門番をみつめてきたので、毛皮の襟にとまったノミにもすぐに気がつく。
するとノミにまで、おねがいだ、この人の気持をどうにかしてくれ、などとたのんだりした。
そのうち視力が弱ってきた。
あたりが暗くなったのか、それとも目のせいなのかわからない。
いまや暗闇のなかに燦然と、掟の戸口を通してきらめくものがみえる。
いのちが尽きかけていた。
死のまぎわに、これまでのあらゆることが凝結して一つの問いとなった。
これまでついぞ口にしたことのない問いだった。
からだの硬直がはじまっていた。もう起き上がれない。
すっかりちぢんでしまった男の上に、大男の門番がかがみこんだ。
「欲の深いやつだ」
と、門番は言った。
「まだ何が知りたいのだ」
「誰もが掟を求めているというのに―」
と、男は言った。
「この永い年月のあいだ、どうして私以外の誰ひとり、中に入れてくれといって来なかったのです?」
いのちの火が消えかけていた。うすれていく意識を呼びもどすかのように門番がどなった。
「ほかの誰ひとり、ここには入れない。この門は、おまえひとりのためのものだった。
さあ、もうおれは行く。ここを閉めるぞ」
-----------------------------------
→
この寓話で、「門」「門番」「中」「掟」というものの象徴(めたふぁー)が何なのか、自分なりに考えてみると、イマジネーションを刺激されると思う。
ある意味で、「門の中」はそれぞれにとっての「魂」の内奥の世界であって、自分の「魂」に触れるためにアクセスする鍵は「自分」しか持っていない。
それは、本来他人がどうこう言う問題ではない。スピリチュアルだとかパワースポットとかは、単なる名詞でしかない。「魂」の内奥(神や仏は、本当はそこにいる)へ近付くには強力な「門番」がいて、その開かずの「門」を開けるには強い自我が必要で、強い自我を持つ人にしかその門は開けられない。
ただ、ふとした拍子に「魂の内奥」に否応なく、ダイレクトに触れさせられる人がいる。適切な時を司る「門番」を無視して強行突破するような「事態」とも言えるので、それ相応のリスクを負う。
・・・・・
そういうことを暗示(めたふぁー)しているように、カフカの短編は読めた。(それぞれが自由に解釈すればいいと思う。小説に固定化した意味はない。)
■
(「知覚の呪縛」より)
=========================
Sにおいて「私」と「私の肉体」の区別がついていない。
「私」とSの諸器官または排泄物の区別がついていない。
Sにおいては自我と肉体は端的に同じなのだ。
=========================
「私」は肉体自我ではない。
他人の欲望も私自身の欲望も私の肉体にしか向かい得ない。
自我は誰の欲望対象にもなり得ない。
=========================
ところが、Sは肉体自我になってしまっている。
肉体自我の出現の条件は、現在と言う時の切断面に磔にされていること、つまり自我が時空的な構えをとりえないこと、また他人が消去されているために自我が育つための他所、乳幼児にとっての母親の顔、まなざし、あるいは鏡像に相当するものが与えられていないこと、などが考えられる。
ともかく、他人と歴史という鏡がない以上、Sの自我は自力で自我にならなければならない。
これは不可能なことである。
せいぜいのところ、物として存在する肉体の助けを借りて、自立を試みることができるだけであろう。
=========================
肉体自我を舞台にして、肉体は自我を隠すものではなく、逆に自我を露呈せしめるものとなる。
=========================
→
最終的には「自我」「わたし」というものが何なのか、どういう成立をするのか、という洞察になっていきます。
やはり、自分も生涯のテーマとして考えている「「わたし」とは何か?」というテーマに行きつく。これは、宗教も哲学も医学もスピリチュアルも・・・隠れたテーマとして常に潜んでいるテーマだと自分は昔から思っています。
Sさんは、<皮膚で囲まれた肉体の中が「私」である>とは思っていない。
「私の呼吸」も「私」なら、「私」は気体となり宇宙の果てまで拡散する。
「私の排泄物」も「私」なら、「私」は「汚く臭い」ものとしてこの世界にさらされ続けることになる。
この複雑なプロセスの中で、Sさんの「私」はできあがり、そこを基点として「私」の「世界観」は作られ行く。
その結果、Sさんの現実はすべて偽物の「ワラ」世界に包まれてしまうことになり、本当の世界である「オトチ」世界を求め続けて生きているのだ。
それは、ある意味ではプラトンの「イデア」(理想の世界)を求めているようだ。
この世にあるおかしなことや倒錯したことを「これが現実だから仕方がないか・・」と受け入れている私たちが、本当に正気なのか。
現実に対する暴力的な線引きをすること事態が、健常者と病者という境界を作りだしているのかもしれない。
この本は、渡辺先生の存在を経て、小さい「奇跡」を通過しながら、終わる。
それは読んだ人に小さな希望を感じさせ、終わるのです。
■
僕らは、3.11という大地震により、日本が沈没してしまうかもしれないという「世界没落体験」を共有したはずだ。
だからこそ、そういう「世界没落体験」を一身に引き受けたSさんのような世界から、学ぶことがあるのだと思う。
「病」や「死」は、忌み嫌うものでも見ないふりをするものでもなく、自然からのメッセージとして真摯に耳を傾ける必要がある。僕らをよりよく成長させるための、学びでもあり啓示でもあるのだ、と思う。
・・・・・・・
最後にある、田口ランディさんの後書き解説がとてもよかった。
(「知覚の呪縛」の解説より。By.田口ランディ)
=========================
Sさんにとっては世界がまるご没落してしまったのだ。
彼女を分裂病者という病名で呼ばれるような状態に追い込むほどに、世界の側が変容した、という認識なのである。
=========================
(自殺されたお兄さんのことを語る)
兄は否応もなくあるがままだったのだと思った。
隠す事ができないから、あんなにも支離滅裂だったんのだ。
=========================
兄の世界を変えようとするのではなく、私自身が兄の世界の中で変容することを始めたのなら、事態は変わっていたのだろうか?
=========================
=========================
「私をSの世界の中に投げ入れ、Sによる呪縛に身をまかせ、私自身を禁止された当人と化してしまうこと、私自身を言わば、Sの言葉が刻みこまれる石板の如くすること、私を変質してしまった素材としてその変質の実感を言葉にもたらすこと、これが私の債務に他ならない。」(P99)
私はここに「聴く」ということの恐るべき可能性が語られていると思う。
「聴く」とは、「聴くこと」によって否応もなく変容した自己のありようから言葉を紡ぎだす行為であり、そのとき私と言う自我はいったん消去される。
たぶん、このような自我の消去を通して、“誰でもない私”になった瞬間にこそ、わたしの内部に覚醒と変容が起こりうるのだろう。
=========================
たぶん、個々の人生において事故のように世界は没落する可能性を持つのだ。
誰の上にも起こり得ることとして世界は崩壊する。
広島に落ちた原爆のように、チェルノブイリの原発事故のように、阪神淡路大震災のように、テロの襲撃を受けたように、世界は崩壊する。
・・・・・・
あるときSさんの人生にとってとてつもない大惨事が生じ、世界は崩壊したのだ。その理由を「なぜ?」とSさん個人に問うてもあまり意味はないように思う。
崩壊は起こった。それだけだ。
=========================
=========================
情報量だけが爆発的に増えているけれど、情報は歴史ではない。
情報化を正面から否定するものではないけれど、あまりに急激な情報の氾濫は、経験を寸断し、「きちんとしたゲシュタルトをもって歩き話す“ヒト”」である他者との遭遇から、私を阻害しているように思う。
=========================
現代社会は、インターネットもTwitterもFacebookも含め、あまりにも情報が膨大になり、「何が本当か分からない」時代だろう。
「情報」をやり取りするだけで、会ったこともない人を「こういう人だ」と偏見で決めつけて判断する。
「情報」をやり取りするだけで、行ったこともない自然を体験した気になる。
僕らは、「情報」に支配されるのではなく、「情報」は参照メモ程度に引き出しにしまっておきながら、自分の五感や第六感を総動員しながら体験することをもっと大切にすべきなのだろうと思う。
それこそが、生きること。
その生きる過程で、「受け入れがたい」現実を回避する安全弁として、否応なく「病」として発病する人もいるだろう。
そういう人たちにも、「偏見」という情報に自分が振り回されるのではなく、「起こりえた「私」の人生の一つ」として相手を全身で受け止め、共感的に思いやりと共に見守ることができるのなら、この世界はもっと万人が住みやすい世界に「変容」していくのだ、と思う。奇跡は、起きる。
そういう「変容」への秘密の鍵を、全員が持っていると、思う。
-----------------------
楳図かずお「わたしは真悟」
-----------------------
『奇跡は 誰にでも
一度おきる
だが
おきたことには
誰も気がつかない』
-----------------------
************************
<内容(「BOOK」データベースより)>
重篤な分裂病者の言葉に徹底的に耳を傾け、その世界に身を投じ、自らを変容させ、
その変容を論理的に記述、分析、哲学的考察を加えることで、初めて立ち現れてくる分裂病者の世界。
私たちが抱く「分裂病」の一般的イメージを根底より破壊する衝撃の一冊。
<著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)>
渡辺/哲夫
1949年茨城県生まれ。
1973年東北大学医学部卒業。都立松沢病院、東京医科歯科大学務経を経て、現在、正慶会栗田病院副院長。
東京医科歯科大学医学部臨床助教授。医学博士。精神病理学専攻.
************************
この本はとんでもない本です。<劇薬につき取扱注意>の本です。
自分の自我の安定があるときに読まないと、あちらに持って行かれるので要注意。
素人は読まない方がいいと思いますが、気になる人はこっそりと読んでください。
マルケスの「百年の孤独」の中で、無限(夢幻?)に出てくる「語り」を聞いていて、無性にこの本が思い出されたのでした。
→「ガルシア・マルケス「百年の孤独」」(2013-05-23)
・・・・・・・・・
この本は1986年に西田書店から出た本。
田口ランディさんが著作(「モザイク」だったかな?)で紹介した縁で、その後ちくま学芸文庫で2002年に再販。
当時、ランディさん本人から頂いたのです。もう11年前かぁ。
ランディさんの後書き文庫版解説にも、
「四十歳になって、本書『知覚の呪縛』と出会ったときの衝撃は、十五歳のときに(セシュエー『分裂病の少女の手記』から)分裂病の存在を知ったときの衝撃の百倍もあった。メガトン級のショックを受けた」と書かれている。
確かに、「人間」という存在を立体的に見る過程において、自分も同じようなショックを受けたものだ。
当時、自分が学生の時に精神科を回っていろいろ考えていたこと。
その後、10年近く医療現場で働いて考えたこと。
そういうのが色々とリンクした。
学生時代は臨床経験がなかった。逆にいえばそれだけ純粋。
今は臨床経験が豊富で現実を数多く見た。逆にいえばそれだけ事実に縛られることになる。
そういう風に学生時代の「自分」と、今の「自分」とを2枚重ねにしながら、読んだ。
■
この本の主人公Sさんにおいて、Sさんの知覚領域は全て「ワラ」、すなわち偽物でできているとされている。
ただ、Sさん自信もSさん自信により「消去」されてしまっていて、その「ワラ」世界にもいない。
精神科領域で言う「世界没落体験」の渦中にあるSさんの事例。
ただ、Sさんは本当の世界である「オトチ」世界を求め、「オタカラ」という手がかりを求めるために「トグロ巻き」という儀式的な行為を日々続ける。
・・・・
まるでSF世界のようだが、これは実際にある一症例。
■
精神科医の渡辺哲夫先生は、「分裂病」(今では統合失調症という名前に改変された。当時の用語である「分裂病」を使う)という名前で状態を固定化するのを巧みに回避する。
渡辺先生は「分裂病と名付けられた事態」と呼んでいた。
名詞の持つ固定力を恐れたのだろう。
確かに、僕らは「名詞」化された名前で呼ぶことで、それを自分のイメージで勝手に固定化して、その用語に縛られることがある。自分で自分の檻をつくり、その中でひとり勝手に閉じ込められるように。
渡辺先生は、あくまでも流動的な「事態」であるとする。
それは、おそらく自然現象の中で雨や嵐や台風や大地震が来るような、向こうから襲ってきて避けられない「緊急事態」のような状況として、「精神の病」をとらえているからだろう。
「病」は、確かに自分が引き金をひく側面と共に、「あちらから」やってくる側面も持つ。
■
(「知覚の呪縛」より)
=========================
隠された事実などない。一切は露出している。
=========================
どこから見ても精神荒廃状態にあるSの中で、ただ言葉のみがきちんとしていた。
=========================
Sと言う名の自己同一的な個人がいない。
=========================
「世界没落は世界分裂ないし世界二重化なのである。」
=========================
Sさんは知覚できる領域は全て「ワラ」世界として、すべて偽物だ、としている。
彼女にとっての「現実」は、確かに彼女独自でオリジナル。
誰にも共有されえないかもしれない。
ただ、彼女にとってはすべての真実もすべての嘘も「隠された事実などなく、一切は露出している」から、そういう認知世界においては、むしろ全てが「まがいもの」として認知されてしまうようだ。
自分にとってあまりにもショックなことが起きた時、
「こんなはずはない!こんなことが自分に起こるはずがない!こんなのはすべて嘘か夢だ!」
と、あるがままの現実を「受け入れがたい」ことが起こるだろう。
そのあまりにも強く思った「念」は、この世界の認知を全て塗り替えてしまい、固着化し固定化することが起きるのかもしれない。
身近な人の死、別離、天災・・・などが自分の身に起きた時、小さいレベルから大きいレベルまで、内的世界では日常的に密かに起きている現象かもしれない。
「受け入れられないもの」に出会ったとき、たいていはなんとか自我が調整しながら「受け入れがたいものを受け入れる」という矛盾を同居させて生きていくのだけれど、そこで奇妙な形で「受け入れてしまった」ときに、こういう事態が起きるのかもしれない。
こういう事態に陥る危うさを、人間は誰もが持っている。
そして、こういう事例に医療の臨床家が出会うと、途方に暮れる。
私に何ができるのだろうか・・・、と。
ただ、医療では、相手を「他人」として分離していると確かに何も起こらないが、相手のありのままの人生を、「起こりえたわたしの人生の一つ」として「自分」事として共感的な眼差しで愛や思いやりと共に接していると、「何か」が起きることがある。そして、それは「治癒」につながることもある。
臨床家は、ある意味でそういう奇跡が起きやすい場を演出しながら、根気よく奇跡の到来を待ち続ける存在なのかもしれない。砂漠での雨乞いの儀式のように。
楳図かずお先生の「わたしは真悟」という漫画史に残る大傑作漫画の中で、
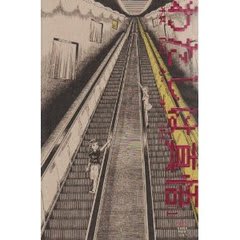
****************
『奇跡は 誰にでも
一度おきる
だが
おきたことには
誰も気がつかない』
****************
という謎めいたメッセージがある。
そんなことをふと思い出した。
*「WA・TA・SI」(2012-03-11)
*「楳図かずお「イアラ」」(2009-01-22)
■
本書の中では、フランツ・カフカの「「掟の門」が引用される。
本書より少し長めに引用してみる。
-----------------------------------
「カフカ短篇集」(岩波文庫)カフカ、池内 紀 (1987/1/16)

-----------------------------------
掟の門前に門番が立っていた。
そこへ田舎から一人の男がやって来て、入れてくれ、と言った。
今はだめだ、と門番は言った。
男は思案した。
今はだめだとしても、あとでならいいのか、とたずねた。
「たぶんな。とにかく今はだめだ」
と、門番は答えた。
掟の門はいつもどおり開いたままだった。
門番が脇へよったので男は中をのぞきこんだ。これをみて門番は笑った。
「そんなに入りたいのなら、おれにかまわず入るがいい。
しかし言っとくが、おれはこのとおりの力持ちだ。
それでもほんの下っぱで、中に入ると部屋ごとに一人ずつ、順ぐりにすごいのがいる。
このおれにしても三番目の番人をみただけで、すくみあがってしまうほどだ」
こんなに厄介だとは思わなかった。
掟の門は誰にも開かれているはずだと男は思った。
しかし、毛皮のマントを身につけた門番の、その大きな尖り鼻と、ひょろひょろはえた黒くて長い蒙古髯をみていると、おとなしく待っている方がよさそうだった。
門番が小さな腰掛けを貸してくれた。門の脇にすわっていてもいいという。
男は腰を下ろして待ち続けた。何年も待ち続けた。
その間、許しを得るためにあれこれ手をつくした。
くどくど懇願して門番にうるさがられた。
ときたまのことだが、門番が訊いてくれた。
故郷のことやほかのことをたずねてくれた。
とはいえ、お偉方がするような気のないやつで、おしまいにはいつも、まだだめだ、と言うのだった。
たずさえてきたいろいろな品を、男は門番につぎつぎと贈り物にした。
そのつど門番は平然と受けとって、こう言った。
「おまえの気がすむようにもらっておく。何かしのこしたことがあるなどと思わないようにだな。しかし、ただそれだけのことだ」
永い年月のあいだ、男はずっとこの門番を眺めてきた。
ほかの番人のことは忘れてしまった。
ひとりこの門番が掟の門の立ち入りを阻んでいると思えてならない。
彼は身の不運を嘆いた。
はじめの数年は、はげしく声を荒らげて、のちにはぶつぶつとひとりごとのように呟きながら。
そのうち、子供っぽくなった。
永らく門番をみつめてきたので、毛皮の襟にとまったノミにもすぐに気がつく。
するとノミにまで、おねがいだ、この人の気持をどうにかしてくれ、などとたのんだりした。
そのうち視力が弱ってきた。
あたりが暗くなったのか、それとも目のせいなのかわからない。
いまや暗闇のなかに燦然と、掟の戸口を通してきらめくものがみえる。
いのちが尽きかけていた。
死のまぎわに、これまでのあらゆることが凝結して一つの問いとなった。
これまでついぞ口にしたことのない問いだった。
からだの硬直がはじまっていた。もう起き上がれない。
すっかりちぢんでしまった男の上に、大男の門番がかがみこんだ。
「欲の深いやつだ」
と、門番は言った。
「まだ何が知りたいのだ」
「誰もが掟を求めているというのに―」
と、男は言った。
「この永い年月のあいだ、どうして私以外の誰ひとり、中に入れてくれといって来なかったのです?」
いのちの火が消えかけていた。うすれていく意識を呼びもどすかのように門番がどなった。
「ほかの誰ひとり、ここには入れない。この門は、おまえひとりのためのものだった。
さあ、もうおれは行く。ここを閉めるぞ」
-----------------------------------
→
この寓話で、「門」「門番」「中」「掟」というものの象徴(めたふぁー)が何なのか、自分なりに考えてみると、イマジネーションを刺激されると思う。
ある意味で、「門の中」はそれぞれにとっての「魂」の内奥の世界であって、自分の「魂」に触れるためにアクセスする鍵は「自分」しか持っていない。
それは、本来他人がどうこう言う問題ではない。スピリチュアルだとかパワースポットとかは、単なる名詞でしかない。「魂」の内奥(神や仏は、本当はそこにいる)へ近付くには強力な「門番」がいて、その開かずの「門」を開けるには強い自我が必要で、強い自我を持つ人にしかその門は開けられない。
ただ、ふとした拍子に「魂の内奥」に否応なく、ダイレクトに触れさせられる人がいる。適切な時を司る「門番」を無視して強行突破するような「事態」とも言えるので、それ相応のリスクを負う。
・・・・・
そういうことを暗示(めたふぁー)しているように、カフカの短編は読めた。(それぞれが自由に解釈すればいいと思う。小説に固定化した意味はない。)
■
(「知覚の呪縛」より)
=========================
Sにおいて「私」と「私の肉体」の区別がついていない。
「私」とSの諸器官または排泄物の区別がついていない。
Sにおいては自我と肉体は端的に同じなのだ。
=========================
「私」は肉体自我ではない。
他人の欲望も私自身の欲望も私の肉体にしか向かい得ない。
自我は誰の欲望対象にもなり得ない。
=========================
ところが、Sは肉体自我になってしまっている。
肉体自我の出現の条件は、現在と言う時の切断面に磔にされていること、つまり自我が時空的な構えをとりえないこと、また他人が消去されているために自我が育つための他所、乳幼児にとっての母親の顔、まなざし、あるいは鏡像に相当するものが与えられていないこと、などが考えられる。
ともかく、他人と歴史という鏡がない以上、Sの自我は自力で自我にならなければならない。
これは不可能なことである。
せいぜいのところ、物として存在する肉体の助けを借りて、自立を試みることができるだけであろう。
=========================
肉体自我を舞台にして、肉体は自我を隠すものではなく、逆に自我を露呈せしめるものとなる。
=========================
→
最終的には「自我」「わたし」というものが何なのか、どういう成立をするのか、という洞察になっていきます。
やはり、自分も生涯のテーマとして考えている「「わたし」とは何か?」というテーマに行きつく。これは、宗教も哲学も医学もスピリチュアルも・・・隠れたテーマとして常に潜んでいるテーマだと自分は昔から思っています。
Sさんは、<皮膚で囲まれた肉体の中が「私」である>とは思っていない。
「私の呼吸」も「私」なら、「私」は気体となり宇宙の果てまで拡散する。
「私の排泄物」も「私」なら、「私」は「汚く臭い」ものとしてこの世界にさらされ続けることになる。
この複雑なプロセスの中で、Sさんの「私」はできあがり、そこを基点として「私」の「世界観」は作られ行く。
その結果、Sさんの現実はすべて偽物の「ワラ」世界に包まれてしまうことになり、本当の世界である「オトチ」世界を求め続けて生きているのだ。
それは、ある意味ではプラトンの「イデア」(理想の世界)を求めているようだ。
この世にあるおかしなことや倒錯したことを「これが現実だから仕方がないか・・」と受け入れている私たちが、本当に正気なのか。
現実に対する暴力的な線引きをすること事態が、健常者と病者という境界を作りだしているのかもしれない。
この本は、渡辺先生の存在を経て、小さい「奇跡」を通過しながら、終わる。
それは読んだ人に小さな希望を感じさせ、終わるのです。
■
僕らは、3.11という大地震により、日本が沈没してしまうかもしれないという「世界没落体験」を共有したはずだ。
だからこそ、そういう「世界没落体験」を一身に引き受けたSさんのような世界から、学ぶことがあるのだと思う。
「病」や「死」は、忌み嫌うものでも見ないふりをするものでもなく、自然からのメッセージとして真摯に耳を傾ける必要がある。僕らをよりよく成長させるための、学びでもあり啓示でもあるのだ、と思う。
・・・・・・・
最後にある、田口ランディさんの後書き解説がとてもよかった。
(「知覚の呪縛」の解説より。By.田口ランディ)
=========================
Sさんにとっては世界がまるご没落してしまったのだ。
彼女を分裂病者という病名で呼ばれるような状態に追い込むほどに、世界の側が変容した、という認識なのである。
=========================
(自殺されたお兄さんのことを語る)
兄は否応もなくあるがままだったのだと思った。
隠す事ができないから、あんなにも支離滅裂だったんのだ。
=========================
兄の世界を変えようとするのではなく、私自身が兄の世界の中で変容することを始めたのなら、事態は変わっていたのだろうか?
=========================
=========================
「私をSの世界の中に投げ入れ、Sによる呪縛に身をまかせ、私自身を禁止された当人と化してしまうこと、私自身を言わば、Sの言葉が刻みこまれる石板の如くすること、私を変質してしまった素材としてその変質の実感を言葉にもたらすこと、これが私の債務に他ならない。」(P99)
私はここに「聴く」ということの恐るべき可能性が語られていると思う。
「聴く」とは、「聴くこと」によって否応もなく変容した自己のありようから言葉を紡ぎだす行為であり、そのとき私と言う自我はいったん消去される。
たぶん、このような自我の消去を通して、“誰でもない私”になった瞬間にこそ、わたしの内部に覚醒と変容が起こりうるのだろう。
=========================
たぶん、個々の人生において事故のように世界は没落する可能性を持つのだ。
誰の上にも起こり得ることとして世界は崩壊する。
広島に落ちた原爆のように、チェルノブイリの原発事故のように、阪神淡路大震災のように、テロの襲撃を受けたように、世界は崩壊する。
・・・・・・
あるときSさんの人生にとってとてつもない大惨事が生じ、世界は崩壊したのだ。その理由を「なぜ?」とSさん個人に問うてもあまり意味はないように思う。
崩壊は起こった。それだけだ。
=========================
=========================
情報量だけが爆発的に増えているけれど、情報は歴史ではない。
情報化を正面から否定するものではないけれど、あまりに急激な情報の氾濫は、経験を寸断し、「きちんとしたゲシュタルトをもって歩き話す“ヒト”」である他者との遭遇から、私を阻害しているように思う。
=========================
現代社会は、インターネットもTwitterもFacebookも含め、あまりにも情報が膨大になり、「何が本当か分からない」時代だろう。
「情報」をやり取りするだけで、会ったこともない人を「こういう人だ」と偏見で決めつけて判断する。
「情報」をやり取りするだけで、行ったこともない自然を体験した気になる。
僕らは、「情報」に支配されるのではなく、「情報」は参照メモ程度に引き出しにしまっておきながら、自分の五感や第六感を総動員しながら体験することをもっと大切にすべきなのだろうと思う。
それこそが、生きること。
その生きる過程で、「受け入れがたい」現実を回避する安全弁として、否応なく「病」として発病する人もいるだろう。
そういう人たちにも、「偏見」という情報に自分が振り回されるのではなく、「起こりえた「私」の人生の一つ」として相手を全身で受け止め、共感的に思いやりと共に見守ることができるのなら、この世界はもっと万人が住みやすい世界に「変容」していくのだ、と思う。奇跡は、起きる。
そういう「変容」への秘密の鍵を、全員が持っていると、思う。
-----------------------
楳図かずお「わたしは真悟」
-----------------------
『奇跡は 誰にでも
一度おきる
だが
おきたことには
誰も気がつかない』
-----------------------









