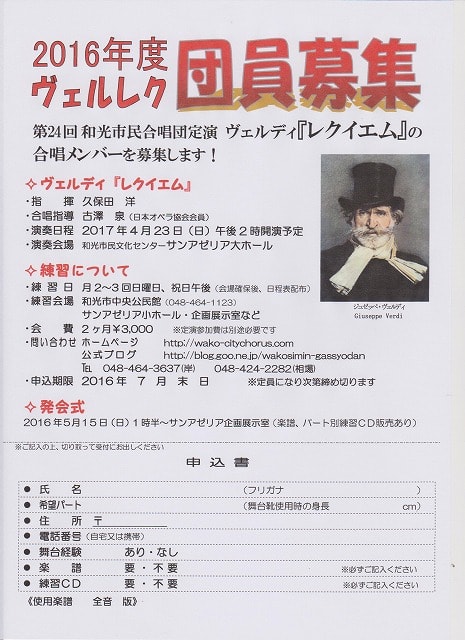和光市民文化センター企画展示室での全体練習は
若手指導者テノール「佐藤圭」さんのご指導で
ヴェルディレクイエム 「NO.Ⅱ Dies iræ」をじっくり勉強しました。
発声については
 あばら骨が常に脇の方に広がった感じを崩さず歌うこと。
あばら骨が常に脇の方に広がった感じを崩さず歌うこと。
 明るい声で前向きに発声すること。
明るい声で前向きに発声すること。
NO.Ⅱ Dies iræ・・・9つの曲がこの章を構成し、レクイエムの中心となる部分で「最後の審判」の恐ろしい光景を描く。
①怒りの日
ダヴィドとシヴィッラの予言の通り
この世が灰と帰すべきその日こそ怒りの日である。
すべてをおごそかに正すために審判者が来給うとき
人々のおそれはいかばかりであろうか。
 最初のテーマは男声から始まり、2パートに分かれた3声が続きます。音があやふやになりがちなので
最初のテーマは男声から始まり、2パートに分かれた3声が続きます。音があやふやになりがちなので
しっかり音を確認して三連符など歌うように!
 常に母音は長く歌う。
常に母音は長く歌う。
 ppの時、子音を立ててはっきり歌う。
ppの時、子音を立ててはっきり歌う。
 80小節「quantus tremor est」のestはしっかり母音e発音、sは多くは言わない。
80小節「quantus tremor est」のestはしっかり母音e発音、sは多くは言わない。
 82小節「quando」のandoをしっかりしゃべる。
82小節「quando」のandoをしっかりしゃべる。
 88小節「discus surus」cusをクスとしっかり発音。
88小節「discus surus」cusをクスとしっかり発音。
 131小節女声の「sonum」132小節テノールの「sonum」八分音符にポルタメントかけない。
131小節女声の「sonum」132小節テノールの「sonum」八分音符にポルタメントかけない。
 177小節からの表現記号「特別に静かにちょっとくぐもった声でとても悲しく」を守って!
177小節からの表現記号「特別に静かにちょっとくぐもった声でとても悲しく」を守って!
 p52入りの音注意。
p52入りの音注意。
 p66のユニゾン音注意!
p66のユニゾン音注意!
78ページまで全体練習済ませましたので欠席の方は練習しておいてください。
 次回は7月3日(日)1時半から中央公民館視聴覚室で女声練習、佐藤先生。
次回は7月3日(日)1時半から中央公民館視聴覚室で女声練習、佐藤先生。
 7月18日(月・祝)1時半から男声パート練習は同じく公民館、佐藤先生。
7月18日(月・祝)1時半から男声パート練習は同じく公民館、佐藤先生。
今日は冷たい雨の一日になりましたね
11日(土)男声練習、12日(日)女声練習と続きました。
 11日の男声練習は、テナー4人、ベース8人が参加しました。
11日の男声練習は、テナー4人、ベース8人が参加しました。

 12日の女声練習は古澤先生の指導で行われました。
12日の女声練習は古澤先生の指導で行われました。 87小節からのリズム厳しく。
87小節からのリズム厳しく。 130、134小節のアクセントはたたくのではなく、一音ずつを回転させる感じ。
130、134小節のアクセントはたたくのではなく、一音ずつを回転させる感じ。 139小節しっかり切る。
139小節しっかり切る。 177小節からのドイツ語表情記号「特別に静かにくぐもった感じでとても悲しく」Pが4つ、小さいだけでなく悲しい感情表現を。
177小節からのドイツ語表情記号「特別に静かにくぐもった感じでとても悲しく」Pが4つ、小さいだけでなく悲しい感情表現を。 191小節「Dies irœ」は子音を立てて、決してはずんで歌わない。
191小節「Dies irœ」は子音を立てて、決してはずんで歌わない。 P60からの「salvame」リズム厳しく、子音立てて、前向きに。
P60からの「salvame」リズム厳しく、子音立てて、前向きに。 367小節、ソプラノのドからソへの音の変化を歌う時同じポジションで音を替える、体や口の形などを変えない。
367小節、ソプラノのドからソへの音の変化を歌う時同じポジションで音を替える、体や口の形などを変えない。 374小節はアルトⅡパート、ソプラノⅡパート、375小節はアルトⅠパート、ソプラノⅠパートが歌う。
374小節はアルトⅡパート、ソプラノⅡパート、375小節はアルトⅠパート、ソプラノⅠパートが歌う。  次回は6月19日(日)1時半からサンアゼリア企画展示室で佐藤圭先生による全体練習を行います。
次回は6月19日(日)1時半からサンアゼリア企画展示室で佐藤圭先生による全体練習を行います。
5月15日の発会式から約一か月、
古澤先生からはこの曲を歌うための発声指導が熱心に行われています。
各パートの第Ⅰ第Ⅱコーラス分けも順調に進み、ほぼ全員のパートが決まりました。
そして1番「REQUIEM」も音取りは済み、2番「Dies iræ」に進みました。
お休みされているメンバーは1番の音取りは済ませておいてください。
第一曲について先生からの注意点
 第一曲にはPPPが多く表記されていますが、体は必ずフォルテの体で歌ってください。
第一曲にはPPPが多く表記されていますが、体は必ずフォルテの体で歌ってください。
 ReqiemのRは小節より前で出し、母音Eが小節頭にくるように!
ReqiemのRは小節より前で出し、母音Eが小節頭にくるように!
 12小節、ソプラノ「dona」のnaを出すときにdoのままの口の形、縦に長く、決してAの母音を開いて歌わない。
12小節、ソプラノ「dona」のnaを出すときにdoのままの口の形、縦に長く、決してAの母音を開いて歌わない。
 18小節、luxは1拍で必ず切る。
18小節、luxは1拍で必ず切る。
 21小節からの16分音符をリズムしっかり刻む。
21小節からの16分音符をリズムしっかり刻む。
 言葉の母音変化で口をぱくぱく動かさない、例えば「luceat eis」ウエアエイと母音は変化するが口はウの口。
言葉の母音変化で口をぱくぱく動かさない、例えば「luceat eis」ウエアエイと母音は変化するが口はウの口。
 28小節からのバス。ただ大声で歌うのではなく、声を回転させ、前への動きを持って歌う。
28小節からのバス。ただ大声で歌うのではなく、声を回転させ、前への動きを持って歌う。
 28小節からはNO.2ですが主題が出てくるパートはしっかり主題を歌う。そしてフォルテからピアニッシモへの変化しっかり。
28小節からはNO.2ですが主題が出てくるパートはしっかり主題を歌う。そしてフォルテからピアニッシモへの変化しっかり。
 「Jerusalem」はジェルーサレム。
「Jerusalem」はジェルーサレム。

 96小節のsonは八分音符、短く切る。
96小節のsonは八分音符、短く切る。

 97小節からのリズムは各パート同じに!
97小節からのリズムは各パート同じに!

 108小節の二分音符は伸びないで!
108小節の二分音符は伸びないで!

 pppは言葉をはっきりしゃべる、子音が重要。
pppは言葉をはっきりしゃべる、子音が重要。
 次回は6月11日(土)午後1時半から、中央公民館視聴覚室で佐藤圭先生による男声練習
次回は6月11日(土)午後1時半から、中央公民館視聴覚室で佐藤圭先生による男声練習
 6月12日(日)午後1時半から、中央公民館視聴覚室で古澤泉先生による女声練習
6月12日(日)午後1時半から、中央公民館視聴覚室で古澤泉先生による女声練習