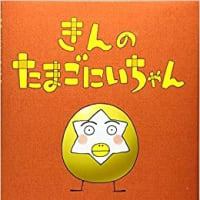《ファンタジーと統合教育》
『いまファンタジーにできること』を読んでいます。
ル=グウィンの最新刊、のようです。
アーシュラ・K・ル=グウィン、1929年生まれの82歳。
石牟礼道子さんは1927年生まれ。
北村小夜さんは1925年生まれ。
20代から今日まで、私がもっとも影響を受けている人たちは、いま八十代という年齢なのかーと、不思議な感じがしました。
「一生おなじ歌を 歌い続けるのは」という詩を思い出します。
さて。
仕事のことや運動のことを離れて楽しもうと思って開いた本でしたが、めくるページめくるページに、「子どもたちが、共にある、ことが 希望」だと声が聞こえます。
文学の世界でのファンタジーの位置と、学校の世界での「統合教育」の位置は、とても似ています。
たとえば。
…いつもの「ワニなつ翻訳」。
《「統合教育・保育の多くの場で当たり前に見られる障害の垣根を超える能力は、わたしには素晴らしい力に思えるが、専門家たちにとっては、未熟な子どもだから、深い意味では何もわかっていないと見えるらしい。
子どもたちが、言葉を話さない重度の障害児とふつうにコミュニケーションできるとき、彼らの考えでは、「障害の改善や発達、成長とは関係のない子どもの慣れ合いでしかない」、となる。
そこでまた、あの呪文が始まる。
素人的、逃避的、何もできないままでいいのか。いるだけでいいのか。
一言でいえば、幼稚で「子どもっぽい」、ということだ。
…彼らは大人だと思われたい気持ちがとても強かったので、「統合教育」に対する見下しという遺産を残してしまった。
それは、今日でも疑問視されることがまれだ。》
話が跳びました。少し戻します。
この本を開くとすぐに、ファンタジーの前提とされていることへの疑問が示されています。
その第一が、「登場人物たちは白人」であることへの疑問です。
こう書かれています。
「この問題について、私は装丁部と何度も喧嘩し、たいていの場合、負けました。だけど、考えてほしいんです。『売れる』とか『売れない』とかいうのは、そう予言したために実現する種類の予言ではないでしょうか。
もし黒人の子ども、ヒスパニックや(東洋、西洋両方の)インディアンの子どもがファンタジーの本を買わないとしたら、それは表紙に自分たちが描かれていないせいではないでしょうか。
わたしはこの国と英国の、肌の色の濃い少年少女から胸が切なくなる手紙を受け取りました。それらの手紙には、《ゲド戦記》のゲドをはじめとする多島海の人々が白人ではないと知って、自分も文学やファンタジーの世界の一員だと初めて感じたと書かれていました。ご一考に値することではありませんか」(P9)
◇ ◇ ◇
「自分も…世界の一員だと初めて感じた」
「自分も…世界の一員だと初めて感じた」
つい、最近、どこかで聞いた言葉でした。
たしかに、どこかで聞いた言葉でした。
そう、10月の名古屋での学習会で聞いた、折田涼さんの言葉でした。
会場係だったので、メモをとることができなかったのですが、あの日、一番心に残った言葉でした。
折田君が5年生になったとき、ようやく学校の先生が、医療的ケアの「研修」に参加してくれるようになりました。そのとき、折田君は、ようやく自分も先生のクラスの一員になれたように感じたのでした。
みんなと同じ、ただのひとりの子どもでいるのに「足りなかったもの」を取り戻したように感じたのでした。
そのときのメモがないので、これは私が受け取った言葉です。
「障害」や「病気」をただちに治してあげること、が「できない」とき、子どもにしてあげられることは、障害がこの子につきつけている、障害と感じる自覚の中身を問うことだと思うのです。
この社会では、障害故に、失い、欠けている、と植え付けられる恐れから、子どもを自由にすること。
すでに間違って植えつけられた恐れを、ほどくことのできる生活と仲間と出会うこと。
関係と日常と笑いと悲しみ。退屈も楽しみも、寂しさもうれしさも取り戻せる人生を、生きられる場を、居場所を、この社会に、その子の真ん中から奪わないこと。
だから、必死で守る。
この子がさびしくないように。
この子の存在がさびしがらないように。
さびしいのは、障害があるから、じゃない。
病気が治らないからじゃない。
さびしいのは、なかまがいないから。
ともだちがいないから。
こどもとして、同じに、出会う人がいないから。
◇
5年生の折田君の取り戻したもの。
「取り戻す」?
失ったのはいつ?
失ったのは「障害」のせいだったか?
障害が治ったら、取り戻せるものか?
障害が治っても、取り戻せないものがある。
障害をもって確かに生きた時間。
生きた自分。
その子の中で、命がけでがんばって生きた子どもの時間。
治ることで、その時間は、なければよかったものになってしまうとしたら。
もしかしたら一生の中で一番がんばって生きた時間。
その時間を生きた子ども。
その子を、もし治ったときには、「その子」を捨ててしまう、忘れてしまう。
そういう生き方。
今の障害のある姿を否定すること。
乗り越えるべき、あらざるべき姿。
それを、子どもの将来の幸せと、間違ってきた。
(まとまらないので、自分のためのメモとして、ここにおきます。)
※
ワニなつ翻訳の原文はこちら↓↓↓
【ファンタジー文学の多くがもっている年齢層の垣根を越える能力は、私にはすばらしい力に思えるが、魔法使い嫌いたちにとっては、情けない弱点である。
ある小説が十歳の子どもにも読めるとすると、彼らの考えでは、大人の小説としては欠陥があるに違いないということになるのだ。
そこでまた、あの呪文が始まる。原始的、逃避的、単純素朴・・・ひと言でいえば、「子どもっぽい」ということだ。
…モダニストたちは、大人だと思われたい気持ちがとても強かったので、児童文学に対する見下しという遺産を残してしまった。それは今日でも疑問視されることがまれだ。】
『いまファンタジーにできること』
アーシュラ・K・ル=グウィン 河出書房新社
最新の画像もっと見る
最近の「誰かのまなざしを通して人をみること」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- ようこそ就園・就学相談会へ(498)
- 就学相談・いろはカルタ(60)
- 手をかすように知恵をかすこと(29)
- 0点でも高校へ(393)
- 手をかりるように知恵をかりること(60)
- 8才の子ども(161)
- 普通学級の介助の専門性(54)
- 医療的ケアと普通学級(90)
- ホームN通信(103)
- 石川憲彦(36)
- 特別支援教育からの転校・転籍(48)
- 分けられること(67)
- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)
- 膨大な量の観察学習(32)
- ≪通級≫を考えるために(15)
- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)
- この子がさびしくないように(86)
- こだわりの溶ける時間(58)
- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)
- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)
- 感情の流れをともに生きる(15)
- 自分を支える自分(15)
- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)
- 受けとめられ体験について(29)
- 関係の自立(28)
- 星になったhide(25)
- トム・キッドウッド(8)
- Halの冒険(56)
- 金曜日は「ものがたり」♪(15)
- 定員内入学拒否という差別(97)
- Niiといっしょ(23)
- フルインクル(45)
- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)
- ワニペディア(14)
- 新しい能力(28)
- みっけ(6)
- ワニなつ(351)
- 本のノート(59)
バックナンバー
人気記事