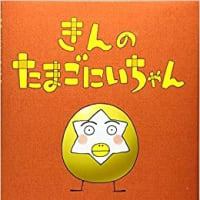私たちの社会がためらうことなく受け入れる子どもたちとは誰か(その3)
人は「向かい合うもの」に応じて、意識の仕方が変わる。
「向かい合うもの」が「かけがえのない大切な子ども」であれば、
ときに命をかけても守りたいという気持ちがうまれる。
けれど、「向かい合うもの」が「誰からも大切にされない不幸な子ども」であれば、
「その子は生まれてこない方がよかったんじゃないか」という考えが現れる。
◇
出生前診断の話題を見かけるとき、いつも強烈な違和感が生じる。
その引っ掛かりの正体がいま分かった。
ダウン症とか二分脊椎とか、調べられる障害児を見つけて中絶する、
ことをどう考えるか?という問いに、
すり替えるから、違うと感じたのだ。
問いは、まず、ここにいるこの子と、私はどう生きるかだ。
生まれくるすべての子どもに、祝福と希望を。
それが答えだ。
問いはまた、私たちの社会がためらうことなく受け入れる子どもたちとは誰か。
生まれくるすべての子どもに、安全と安心を。
それが答えだ。
私が出会ってきたダウン症のごう君やよっちゃんやたか君やちーちゃんや…、
私が向かい合う彼らのなかに、「かわいそうな子ども」「不幸な子ども」は一人もいなかった。
どの子も、家族や友だちに愛され、自分の人生を生きている。
生まれる前から、「誰からも大切にされない子ども」など、いない。
生まれる前から、「誰からも大切にされない子ども」を診断したり、発見できる技術などない。
ただ、生まれてきた子どもをみて、「大切にしない大人」「捨てる大人」がいるのはこの社会の現実。
子どもに障害があるという理由で、入園を断る保育園や、普通学級から追い出そうとする学校の先生は数限りなくいる。
療育センターや教育委員会の先生は、「障害児」が普通学級に行くといじめられ、自己肯定感が育たないと言う。
つまり専門家といわれる人は、「6歳の子どもたちが、障害のある子どもと友だちになれるはずがない、大切に思うはずがない」と信じている。
「かわいそう」とか「不幸」だというなら、そういう誤解を信じたまま生きている人たちだろう。
そのことを問うことなく、「発見の技術」の話をしても仕方ない。
出生前診断の話は、普通学級で共に育つことが大事にされる社会かどうかによってまったく違ってくる。
最新の画像もっと見る
最近の「誰かのまなざしを通して人をみること」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- ようこそ就園・就学相談会へ(495)
- 就学相談・いろはカルタ(60)
- 手をかすように知恵をかすこと(29)
- 0点でも高校へ(393)
- 手をかりるように知恵をかりること(60)
- 8才の子ども(161)
- 普通学級の介助の専門性(54)
- 医療的ケアと普通学級(90)
- ホームN通信(103)
- 石川憲彦(36)
- 特別支援教育からの転校・転籍(48)
- 分けられること(67)
- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)
- 膨大な量の観察学習(32)
- ≪通級≫を考えるために(15)
- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)
- この子がさびしくないように(86)
- こだわりの溶ける時間(58)
- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)
- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)
- 感情の流れをともに生きる(15)
- 自分を支える自分(15)
- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)
- 受けとめられ体験について(29)
- 関係の自立(28)
- 星になったhide(25)
- トム・キッドウッド(8)
- Halの冒険(56)
- 金曜日は「ものがたり」♪(15)
- 定員内入学拒否という差別(97)
- Niiといっしょ(23)
- フルインクル(45)
- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)
- ワニペディア(14)
- 新しい能力(28)
- みっけ(6)
- ワニなつ(351)
- 本のノート(59)
バックナンバー
人気記事