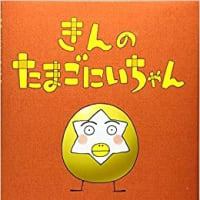わたしは無条件に子どもの側にたつ (aiさんへ)
これを書くべきかどうか、ずいぶん悩みました。
「会」のなかでは通じる言葉であっても、
会を離れると、形を変えてしまう言葉もあります。
本当は、みんなのいる場所で、
子どものことを聞くのでないと、
本当のところ、よく分からないこと、
見えないことが多すぎるのです。
でも、今回の一連のコメントは、
全国連の会報で読んでいた記事と、
先日の交流会で見かけた親子と重なりました。
たったいま苦しい思いをしていることと、
その中で、この会のことを信頼してくださる
気持ちも伝わってきます。
そうであるなら、もし、aiさんがこの会にいたら、
私(たち)が、普通に話しあうことの中身を、
やはりお伝えしておかなければ、と思います。
もしコメントの内容を会で聞いたとしたら、
私が気になる部分を先に記します。
◇ ◇ ◇
「子どもが教室に入れない日が増えてきた…」
「子どもたちも介助の先生任せ。
先生が来ないと、○は、教室に一人置き去りにされている…」
「不安な○は、介助の先生にべったり。
少し騒ぐと、すぐ取り出されているようです。
そうしないでくださいと訴えました。
○が、出たいというのですから。
と、困った顔をしていましたが、
一応、解ってはくれました。」
「特別支援教室の隣りの部屋。
段ボールで作られたパーテーションと呼ばれる衝立の中が、
特学の頃からの、逃れの場所。
最近の○は、ずっとそこから動けなくなっているようでした。
案の状、○は、その中で、何もせずに、
ただごろりと寝転がっていました。」
「介助の先生は、何にもせず、
ただ黙って時の過ぎるのをじっと待っているだけ。
全てを察した私は、
もう言葉を発する気力もありませんでした。」
「私は、○の学校生活が、どんなものかを知り、
胸が痛くなりました。
どんな形であれ、○は、みんなの一員なんだから。
そうだろうか?
それで安心していていいのだろうか?
やっぱり、○は、特学の時と変わらない毎日を
送っているのではないか。」
◇ ◇ ◇
子どもの置かれた状況が、
実際のところはよく分からないまま、
でも、これらの言葉に、
わたしは息苦しい感じを覚えます。
それは、学校の対応の悪さに対してではありません。
学校の対応が褒められたものでないのは明らかですが、
それはひとまず脇に置きます。
学校なんてどこも最初はそんなものだという自覚から
始めるしかないと思うからです。
(このあたりの中身を
きちんと伝えなければならないのですが、
これもかなり難しいので、後回しにします。)
まず、私がひっかかるのは、
ここに書かれているのは、
すべて「親の視線」だということです。
そして、「学校」「担任」「介助」
そして「クラスの子ども」たちへの嘆きだけが、
伝わってきてしまい、
その分、子どもの姿がぼやけてしまうのです。
「6年生」というのは、
年齢的にも、中学に上がる前という点でも、
また受験する子どもがいたり、
少し「大人」になったり、
いろんな意味で「不安定」な学年でもあります。
受け入れのいい学校であっても、
6年生と、中学3年生のときに、
不登校になる「障害児」は少なくありません。
「障害」のせいではなく、
誰かが悪いわけでもないこともあります。
なにより、○君自身も6年生という
大人になりつつある時期ですよね。
彼がこころの中で、何を感じ、
どんな葛藤を抱えているか。
もしかしたら、自分のことで、
どれほど母親を苦しめているか。
そんなことを考えていても少しもおかしくはありません。
本当のところはわかりません。
でも、そんなふうに子どもの気持ちを考えていたら、
「案の状、○は、その中で、何もせずに、
ただごろりと寝転がっていました。」
とは違う言葉になると思うのです。
しかも、「特学の頃からの、逃れの場所」であるなら、
「普通学級」や「介助」のせいだけではないですよね。
小学校に入ってからずっと、
学校の中に、自分の安心できる居場所がなかったときに、
彼が、いつも何かを考えていた場所、ということですよね。
Naoちゃんが、6年生の1学期、一ヶ月くらい、
毎日、教室に入らず廊下で仰向けになっていた、
という話を思い出しました。(※1)
担任や介助に理解がないのが本当だとしても、
5年生まで特殊学級で生活してきたこともまた、
彼の一部です。
子ども自身が「普通学級」という場所に慣れること、
「みんなと一緒に普通学級の生活」を暮らすこと、
「ふつうの授業と言う生活」を暮らすことを、
5年間、知らないままで大きくなったのです。
6歳から11歳の、その5年間は、
子どもにとってかけがえのない大事な5年間です。
入学のときに、普通学級に入れることができなかったことを
責めているのではありません。
親が一人で、教育委員会と闘うことが、
どれほど大変なことかを、知らない訳ではありません。
でも、それは私の「親への理解」です。
子どもからみた場合には、
自分を特殊学級に入れたのは、やはり「親」であり、
そして、5年間をそこで生活したことは、
彼の大事な人生の一部なのです。
分けることが差別であり、
誰もが安心して普通学級にいられるのが
当たり前のことであったとしても、
それでも、やはり6年生で普通学級に戻ったからといって、
その5年間は、すぐに取り戻せるものではないと思うのです。
そこのところから、子どもの側の苦労から、
生活のひとつひとつの場面を見て、
感じてあげるところからしか始まらない、と
私は思うのです。
そして、親の目から見て不満だらけの
学校生活の報告の中にも、
せいいっぱい考え、がんばって生きている
子どもたちの姿が垣間見えます。
だから、誰かに分かってもらうためではなく、
ただ、子どもの気持ちを大事にしたいその気持ちを、
伝え続けてください。
相手が、理解することよりも、
伝え続けることが大事なこともあると思うのです。
「帰り際、いつも○を気にかけてくれている女の子が、
悲しそうな顔で私を見つめました。」
女の子は、先生たちの彼への扱いを「悲しん」でいるのか、
それとも、お母さんの全身に満ちた「怒りと悲しみ」を
心配しているのか、
その場にいない私には分かりませんが…。
(※1)
子どもの置かれた状況は違いすぎるし、
文章も長くなりすぎるとは思うのですが、
ナオちゃんのことを書いたものを、
ここに置きたいと思います。
◇ ◇ ◇
≪HalとNaoちゃんの待ち時間≫(4)
≪先生が親に、いちいち伝えないことの意味≫
◇ ◇ ◇
『私が一番びっくりしたのは、
Naoが1ヶ月もの間そんな状態だったにもかかわらず、
よく担任が私に何も言わなかった…ということです。
「こんな状態なんですけど、お母さん、どうしましょう?」
とか、
「最近、落ち着かないんですけど、家ではどうですか?」
とか、
なにか言われても仕方がない状況だったのに、
担任は私に何も言わなかった!
「どうしましょう?」と聞かれても、どうしようもない。
「家ではどうですか?」と聞かれても、
家では何ら変わりはない。
…私に何を相談されても答えようがなかった。
よくぞ、よくぞ担任は私に何も言わなかった!
そして、よくぞ1ヶ月もの長い間、
廊下で天井を見上げたままのNaoを
見守り続けてくれた!(>_<)』
◇ ◇ ◇
この部分は、さらりと書かれていますが、
何度読んでも、幾重にもすごいことが書かれています。
1ヶ月の間、見守り続けた先生。
「ほっとき続けた」ともいいます。
これはかなり難度の高い技です。
なぜなら、先生の立場では、Naoちゃんとの関係だけでなく、
他の子どもの目や、廊下を通る先生たちの目など、
外部の目も意識しなければなりません。
それに、「親」になんと言えばいいのかも
考えなければなりません。
子どもが1ヶ月の間、廊下に倒れている状態、
それは「授業を受けていない状態」でもあります。
一歩すれ違えば、
「どうして授業を受けさせないで放っておくんですか」
「この子もちゃんと見て下さい」と抗議されかねない光景です。
「ほっといていいのか」という『幻聴』が、
先生の耳には何度も聞こえたことでしょう。
だから、1ヶ月の間Naoちゃんの行動を
そのまま見守ることもすごいことですが、
それ以上にすごいのは、
やはり『親にあえて伝えないこと』だと、私も思います。
そして、そのすごいことができたのは、
先生の個性だけでなく、
お母さんが「そのこと」をきちんと先生に伝えることが
できていたからだと思うのです。
もちろん、「そのこと」を迷いながらも
「受けとめる」ことのできる先生は、本当に見事だと思います。
(だからこの部分は、「親の当事者研究」や
「先生の当事者研究」としても面白いし、
あるいは「親と教師のコミュニケーションの研究」
としても面白い話です。)
先生からすれば、お母さんに伝えるまでもなく、
「今のNaoちゃんの状態は、今はこうとしかいられない
心持ちなんだろう。気力も身体も…」と
思うしかなかったでしょう。
そうした見守り方は、親も了解している範囲であり、
わざわざ報告するまでもない、
いや、報告すれば、親も揺れるだろう。
それにまた、先生にしても、
その話をどう切り出すかも難しい話です。
多分、先生も自信があって
「待って」いたわけではないでしょう。
そうであれば、いったん話題にすれば、
「どうしましょう」「このままでいいんでしょうか」という言葉が
自然と口をついてでるでしょう。
それは、親にすれば「責められている」と感じられる言葉です。
結局のところ、揺れても迷っても、こうして見守る以外に術はない。
だとしたら、時季がくるまで待つしかない。
そういう対応をしてほしいと、親に言われてきたのだから、
これでいいんだと、先生も揺れながら
自分に言い聞かせたのだろうと思います。
みんなと一緒に学校生活を送りたい。
でも、すべてみんなと同じ行動ができるわけではない。
みんなと同じように勉強させてほしいとか、
みんなに追いつくことを目指しているわけではない
勉強ができなくもて、いつもみんなと同じ集団行動を
とることができなくも、たとえ、できないことがいくつあっても、
同じ年の子どもであることには間違いない。
本人も迷いなくそう信じている。
その気持ちを大事にしてあげてほしい。
そういった思いを、親が先生にちゃんと伝えてあること。
それが一ヶ月の「待ち時間」を、
成り立たせることができた理由だと思います。
そうした大人の受けとめる気持ちと
「待ち時間」の覚悟に見守られて、
Naoちゃんは、「自分だけの持ち時間」を十二分に使って、
自分の答を出すことができたのです。
子どもが、自分だけの持ち時間を十分に受けとめられて、
自分の人生を考える時間を持てるのは、
ほんとうに幸せなことだと思います。
コメント一覧

ai

かいとママ

ai

ishizaki

ai
最新の画像もっと見る
最近の「誰かのまなざしを通して人をみること」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- ようこそ就園・就学相談会へ(499)
- 就学相談・いろはカルタ(60)
- 手をかすように知恵をかすこと(29)
- 0点でも高校へ(393)
- 手をかりるように知恵をかりること(60)
- 8才の子ども(161)
- 普通学級の介助の専門性(54)
- 医療的ケアと普通学級(90)
- ホームN通信(103)
- 石川憲彦(36)
- 特別支援教育からの転校・転籍(48)
- 分けられること(67)
- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)
- 膨大な量の観察学習(32)
- ≪通級≫を考えるために(15)
- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)
- この子がさびしくないように(86)
- こだわりの溶ける時間(58)
- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)
- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)
- 感情の流れをともに生きる(15)
- 自分を支える自分(15)
- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)
- 受けとめられ体験について(29)
- 関係の自立(28)
- 星になったhide(25)
- トム・キッドウッド(8)
- Halの冒険(56)
- 金曜日は「ものがたり」♪(15)
- 定員内入学拒否という差別(97)
- Niiといっしょ(23)
- フルインクル(45)
- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)
- ワニペディア(14)
- 新しい能力(28)
- みっけ(6)
- ワニなつ(351)
- 本のノート(59)
バックナンバー
人気記事