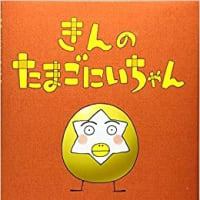いろんなこと、ちゃんと書こうとすると、
あちこち飛んでしまうし、
一つのことを言うのに、
何人もの子どもや親のことを話さないと、
言いたいことが伝わらない…。
そんな中で、前回、思い切って本音の部分を書いたので、
急いで、いくつか付け加えます。
《PS1:普通学級に関する相談のこと》
「ここは、普通学級に行っている親たちの相談室ですよ」
と言われたことについて。
言葉のアヤは別にして、私も同じことを言っています。
就学相談会でも最初にこう言います。
「今日の相談会は、普通学級に行くための話です。
特別支援学級や特別支援学校について知りたい方は、
教育委員会や教育研究所へ行ってください。
そこで、とても丁寧に教えてくれます。
でも、そこでは「普通学級」のことについては、
教えてくれません。
だから、自分たちで相談会を開いています。」
高校の相談会も同じです。
ここは普通高校に入るための話をします。
高等部へ入る相談は、
教育委員会の方へどうぞ、と。
もちろん、体罰や虐待のことなら話は別です。
でも、特別支援学級の教育のこと。
交流の中身のこと。
通級の中身のこと。
そうした相談を引き受けることはできません。
なぜなら、そこを「よいところ」にすることが、
どういうことなのか、
私にはまったく分からないからです。
そこでの待遇をどんなに親の希望通りにしたとしても、
子どもにとって、そこがいいところだとは、
私には思えないからです。
だから、自分が相談できないことは、
できないと、はっきりと言います。
《PS2:普通学級に入ることの難しさ》
それはどこも同じ。
千葉でも東京でも、
普通学級をあきらめる人はたくさんいます。
それでも、やっぱり、地方で、一人で、
「普通学級」を貫くこと、
教育委員会や学校と闘うことの難しさは、
どこでも同じ、とは言えないですね。
私たちの会の周辺では、
特殊学級から普通学級に戻るのに、
親だけでは何カ月かかってもだめだったものが、
1年以上話しあってだめだったものが、
会と連名で申し入れたとたん、
一週間とか、3日で、「普通学級に決まりました」と
返事がきます。
でも、そうした、難しさ、困難はあるとしても、
「特殊学級に行かない」ことはできると、
私は思っているのです。
奈良の明花ちゃんがそうでしたね。
彼女の場合、特殊学級すら断られ、
養護学校の通知が届いたということですが…。
でも、彼女は中学校に行けなくでも、
「養護学校には行かない」ということを、
自分で選び、家にいながら闘ったのでした。
康司もそうでした。
小学校の校門の前で2000日、
闘い続けたのでした。
ところで、私はたぶん、9月19日、
○くんを見かけていると思います(^^)v
彼は、学校の先生がいちばん嫌がるというか、
てこずるタイプの子どもですよね(>_<)
もし、こっちの会にいても…、
小中学校は大丈夫でしょうが、
高校は……、現役合格が厳しいタイプというか…。
Hideとか、Junくんとか、Akiraくんを
思い浮かべした。
この子たちは、高校に入るまでに、
それぞれ3年、3年、5年かかりました(>_<)
そう、3年も5年も、学校に行けずに、
がんばる親子がいたからこそ、いまがあり、
彼らに「自信」をもらって、
私がこうして書いていることができます。
「0点でも高校へ」の子どもたちが、
再来年にはたぶん100人に届きます(o|o)
「100人の、0点でも高校へ」
そういう集会をやるのが、いまの一番の楽しみです。
たぶん、○君が中2か中3の時に、
その集会を開くことになります。
きっとそうなります。
そのときは、集会に来てくださいね。
ゲストとして招待するから
交通費の心配もしなくて大丈夫ですよ(^_^)v$$
もちろん、その地で、高校に入れる気配はないでしょう。
子どもにとって高校に入れることが、一番肝心なことです。
それこそが大事なことだと思います。
でも、やっぱり、それでもやっぱり、
勝つことより、大事なことがあると私は思うのです
たとえ、高校生になれなくても、
この子を高校に入れてほしい、
この子は高校に行きたいんだから、
この子は高校生になって当たり前なんだからと、
言い続けることは、
高校に入ることと同じくらい大切なことだと思います。
それは、分かる気のない人たちに
分かってもらうためではありません。
誰かに分かってもらうためではなく、
ただ、わたしは、わたしたちは、
自分の気持ちに正直に、
子どもの思いに正直に、生きたいと願うだけです。
(※1)
「一人」では難しい。
でも、aiさんは、その地でも、
ここでも、一人ではないですよね。
思いを受けとめてくれる「親友」のことを
書かれていましたよね。
「○君は、幸せだね。こんなお母さんを持って」
言ってくれた人のことを書かれていましたよね。
なにより、
「○は、そんな私を心配して、
いつもより早く目覚め、
ずっとそばに寄り添っていました」
という子どもがそばにいて、
一人なわけがないですよね。
小学校なんか行けなくたって、
高校に入れなくたって、
生きているだけで。
☆ ☆ ☆
康司と一緒に「0点でも高校へ」の運動を始めた雄介は、
6年挑戦して、高校には入れませんでした。
でも、私にとって、
障害児の高校進学の道を、高校に入ることで開いた康司と、
高校に入れないまま、校門の前で6年訴え続けた雄介と。
そして長谷川さん、佐野さんの二人のお母さんの
子どもたちへのまなざしと笑顔は、
私にとって、何よりの生きる支えに、今もなっています。
毎年、9月11日には、康司に会いに行きます。
その日は、康司のお母さんの誕生日でもあります。
子どもが死んで何年たっても、10年が過ぎても、
命日と誕生日は、変わることがないんですね。
9月11日、
今では、この日は、新聞でもテレビでも、
アメリカの同時多発テロを思い出す日になっています。
そして、私は毎年思うのです。
この子たちにとって、
この社会は、毎日、「同時多発テロ」に
脅かされているような社会じゃないのかと。
先日の就学相談会の前日にも、
就学相談会の行われた街のどこかで、
特別支援学校に通う7歳の女の子が母親に命を奪われ、
母親も自ら命を絶ちました。
すみません。
話が予定外の方向にきています。
でも、私のなかに、
こうして、「伝える」ことの怖さがいつもあります。
妹の子どものHalは、もうすぐ小学校卒業です。
小学校2年生から不登校です。
私は、いまのHalの姿を、成長を、
尊敬をもって見守っていると同時に、
ふと、思うことがあるのです。
4年前、私が妹に、「不登校になったからって、
絶対に特殊学級籍に入れちゃだめだよ」と言わなかったら、
私がいなかったら、Halは、
そのころから「楽しく、遊びに行っていた」教室で、
大好きな先生と、数人の友だちと、
「毎日、学校に通って、楽しい学校生活を過ごす」という道が、
もしかしたらあったのではなかったかと。
特殊学級にも、小夜さんのように日本一優しい先生はいます。
子どもと付き合うのが大好きな先生がいます。
もしかしたらHalにも、そういう出会いと、
ただ、「楽しく学校に通える毎日」が、あったのではないかと。
私がいなかったら、妹は、学校に言われるまま、
子どもが喜んでいく場所ならと、
選んだかもしれません。
そう思った後に、
でも、やっぱり、それはむり、
と一人で思うのです。
わたしにはやっぱり、
何度、Halの2年生のときに戻っても、
やっぱり、HalはHalだから、
いまのままで、だいじょうぶ。
いまのままのHalで、
いまままでのままのHalとお母さんのままで、
いけばいい。
そう言うしかできません。
時々、自信がなくなったときに、
こうして何度も、
「後悔するふり」をすることになったとしても。
そして、こういう時に、
小学校1年から中3まで不登校だった、
えりちゃんが出てきてくれて、うなずいてくれます。
えりちゃんに出会ったのは、中1のとき。
適応教室の場所でした。
そこで3年間、つきあいました。
その後、私の勤めていた定時制高校にきて、
そこで4年間、つきあいました。
高校の時は、彼女が9年間不登校だったと
気づく先生はいなかっただろうと思います。
ほぼ4年間、皆勤だったと思います。
ふだん、忘れているけれど、
康司や雄介や、Halやえりちゃんの、
子どもたちが堂々とたくましく生きている姿に、
励まされ、支えられているんだと、
こういう時に思い出します。
延々と話が止まらなくなるので、
この辺で終わりにして、出かけてなくは…。
何が言いたかったのか、
読み返さないで、このまま入れます。
たぶん、子どもたちが助けてくれて、
大事なことだけは、遠く、台風被害で
リンゴが落ちてしまった県にまで届くことを信じて(o|o)
(※1)この文も長すぎるので、
思い出した文章は、次に入れます(・_・;)
コメント一覧

yo

ai
最新の画像もっと見る
最近の「誰かのまなざしを通して人をみること」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- ようこそ就園・就学相談会へ(498)
- 就学相談・いろはカルタ(60)
- 手をかすように知恵をかすこと(29)
- 0点でも高校へ(393)
- 手をかりるように知恵をかりること(60)
- 8才の子ども(161)
- 普通学級の介助の専門性(54)
- 医療的ケアと普通学級(90)
- ホームN通信(103)
- 石川憲彦(36)
- 特別支援教育からの転校・転籍(48)
- 分けられること(67)
- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)
- 膨大な量の観察学習(32)
- ≪通級≫を考えるために(15)
- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)
- この子がさびしくないように(86)
- こだわりの溶ける時間(58)
- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)
- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)
- 感情の流れをともに生きる(15)
- 自分を支える自分(15)
- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)
- 受けとめられ体験について(29)
- 関係の自立(28)
- 星になったhide(25)
- トム・キッドウッド(8)
- Halの冒険(56)
- 金曜日は「ものがたり」♪(15)
- 定員内入学拒否という差別(97)
- Niiといっしょ(23)
- フルインクル(45)
- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)
- ワニペディア(14)
- 新しい能力(28)
- みっけ(6)
- ワニなつ(351)
- 本のノート(59)
バックナンバー
人気記事