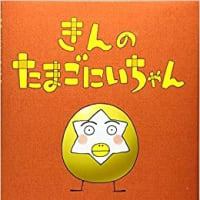オウムのアレックス(2)
ペッパーバーグ博士は、
アレックスに社会モデルの状況をつくってあげました。
一対一で教えるのではなく、
二対一、人間ふたり対鳥一羽で教えたのです。
アレックスに直接教えるのではなく、もう一人の人に教えたのです。
そのあいだアレックスは止まり木に止まって見物していました。
それまでこんなことをした人は誰もいませんでした。
博士はまた、オウムがとても興味をもつものを教材に使いました。
動物も人間も、自分にとって興味のあるものや、
重要なものに注意をはらいます。
たとえば食べ物がどこで手に入るかは、とても重要なことです。
学ぶためにも、注意をはらわなければなりません。
野生のオウムは青い三角などどうでもいいのだから、
そんなものに興味をもつわけがありません。
ペッパーバーグ博士は、アレックスに「青い色」を学ばせたいときには、
パリパリしたすてきな樹皮に「青い色」を塗りました。
そして、アレックスと研究助手を一緒に座らせて、
助手に「何色?」と尋ねるのです。
正しく答えたら、助手はパリパリの樹皮で遊ばせてもらえました。
間違えると、遊ばせてはもらえません。
アレックスは見ているだけでした。
ペッパーバーグ博士はこの技法を、
「手本・競争相手方式」と呼びました。
アレックスにとって助手は、まねをする「お手本」であり、
パリパリの樹皮で遊ぶための「競争相手」でもあった。
博士は、アレックスと助手に、「教えた」のではなく、
「欲しいものを手に入れる」競争をさせたのでした。
このモデル理論を使ったことが大きな突破口になりました。
アレックスはたくさんのことを学びました。
アレックスは「何色?」という質問に、
「青」とか「赤」とかちゃんと答えます。
「どんな形?」とたずねると、
「角・四つ」とか「角・三つ」というように答えます。
アレックスにとって色と形は、
それまで教えられてきた対象物についてだけでなく、
どんなものにもあてはめることのできる抽象的なカテゴリーでした。
しかも、アレックスは自分から質問するようになりました(・・?
ある日、鏡に映った自分の姿を見て、
アレックスは博士に聞きました。
「何色?」
博士は答えました。
「灰色よ。あなたは灰色のオウムよ」
アレックスは、自分の体の色について六回尋ねて、
そして「灰色」をカテゴリーとして覚えました。
そう、自分以外に、「灰色」のものを見つけたり、
それが「灰色でない」ことを言えるようになったのです。
『動物感覚』の著者グランディンさんは、
これを「奇跡としか言いようがない」と書いています。
アレックスは、
「質問の仕方」を教わったことは一度もなかったのです。
アレックスは、
「自分の力」で、「自発的」にたずねたのです。
これは「大事件」です。
(つづく)
最新の画像もっと見る
最近の「膨大な量の観察学習」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- ようこそ就園・就学相談会へ(494)
- 就学相談・いろはカルタ(60)
- 手をかすように知恵をかすこと(29)
- 0点でも高校へ(393)
- 手をかりるように知恵をかりること(60)
- 8才の子ども(161)
- 普通学級の介助の専門性(54)
- 医療的ケアと普通学級(90)
- ホームN通信(103)
- 石川憲彦(36)
- 特別支援教育からの転校・転籍(48)
- 分けられること(67)
- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)
- 膨大な量の観察学習(32)
- ≪通級≫を考えるために(15)
- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)
- この子がさびしくないように(86)
- こだわりの溶ける時間(58)
- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)
- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)
- 感情の流れをともに生きる(15)
- 自分を支える自分(15)
- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)
- 受けとめられ体験について(29)
- 関係の自立(28)
- 星になったhide(25)
- トム・キッドウッド(8)
- Halの冒険(56)
- 金曜日は「ものがたり」♪(15)
- 定員内入学拒否という差別(97)
- Niiといっしょ(23)
- フルインクル(45)
- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)
- ワニペディア(14)
- 新しい能力(28)
- みっけ(6)
- ワニなつ(351)
- 本のノート(59)
バックナンバー
人気記事