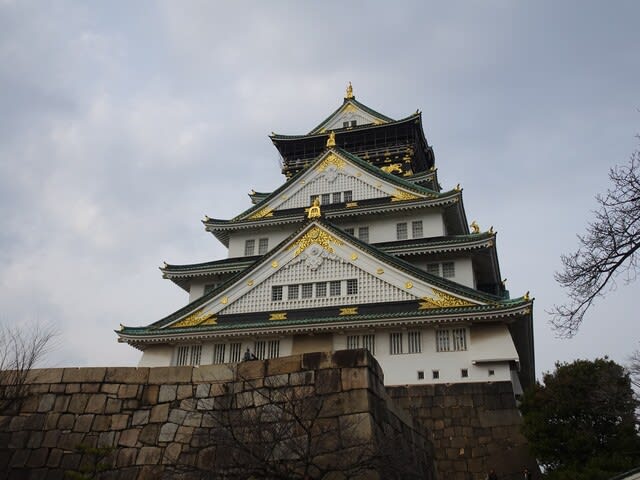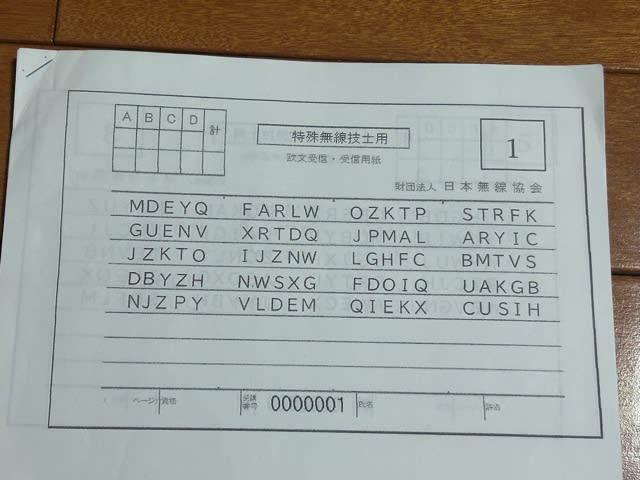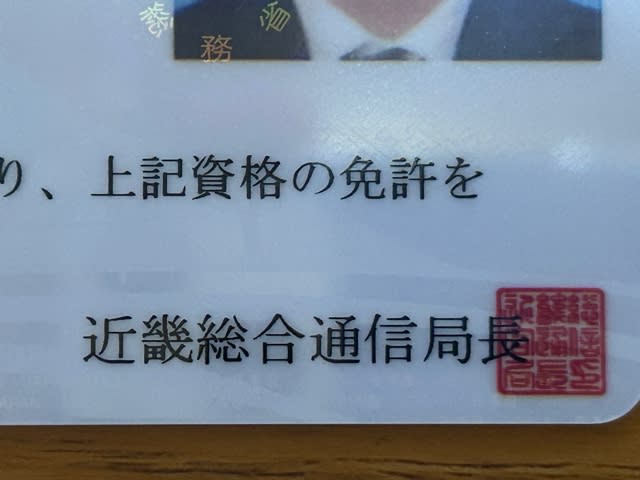2020年3月21日

朝早くホテルをチェックアウトして、京都駅からバスに乗り
京都を代表するお寺を目指します。


法観寺(ほうかんじ)(八坂塔)

(京都市東山区八坂鳥居前下河原町東入ル)
八坂塔として知られる臨済宗建仁寺派の寺院です。
歴史の古さは京都でも屈指で、聖徳太子によって建立されたとも伝えられています。
八坂塔は、永享12年(1440)に足利義教によって再建されたものです。他の伽藍は
応仁の乱で全て焼失してしまいました。
産寧坂から清水坂の方へ歩いていくと見えてきました。
清水寺(きよみずでら)

(京都市東山区清水一丁目294)
北法相宗の総本山(一寺一宗)です。清水寺の開創は宝亀9(778年)。観音様の霊場として
古くから庶民に開かれ幅広い層からら親しまれてきました。音羽山の中腹に広がる13万㎡の境内
に30以上の堂塔伽藍が建ち並びます。創建以来、10度を超える大火災にあいそのたびに堂塔を焼失
しましたが、篤い信仰によって何度も再建されました。現在の伽藍はそのほとんど徳川家光の寄進
により寛永10(1633)年に再建されたものです。
平成6(1994)年にはユネスコ世界文化遺産「古都京都の文化財」のひとつとして登録されました。

仁王門

桜が咲いていました。

奥 三十塔 手前 経堂

世界遺産登録を示す説明版

本堂の舞台

本堂

阿弥陀堂

地主神社 (今回は未訪問)

奥之院

奥之院から見た本堂

子安塔

子安塔近くにある展望スポットからみた 三十塔・経堂・本堂

本堂から張り出した「舞台」の高さは約13メートル。これは4階建てのビルに相当します。
本堂は音羽山の急峻な崖に建築されています。これは「懸造り(かけづくり)」と呼ばれる
日本古来の伝統工法で、格子状に組まれた木材同士が支え合い建築が困難な崖などでも耐震
性の高い構造をつくり上げることを可能にしています。
舞台を支えているのは、床下に建てられた18本もの柱です。樹齢400年余の欅が使われて
おり、大きいもので長さ約12メートル、周囲約2メートルの柱が整然と並んでいます。
その縦横には何本もの貫が通されています。木材同士をたくみに接合するこの構造は「継ぎ手」
と呼ばれ、釘を1本も使用していません。現在の舞台は1633年に再建されたものです。

音羽の瀧
寺名の由来となった瀧です。こんこんと流れ出る清水は古来「金色水」「延命水」と呼ばれ
清めの水として尊ばれてきました。3筋に分かれて落ちる清水を柄杓に汲み、六根清浄、所願成就
を祈願する人達が多く訪れています。
清水寺を後にして、歩いて次の寺院へ。
私事ですが高校時代は弓道部に所属していました。そんな弓道に関係する寺院に行きました。

三十三間堂(さんじゅうさんげんどう)
天台宗妙法院の飛び地境内にある仏堂です。建物の正式名称は蓮華王院本堂(れんげおういんほんどう)。
元は後白河法皇が長寛2(1165)年自身の離宮内に創建した仏堂で、蓮華王院の名称は千手観音の別称
「蓮華王」に由来します。現在の堂は文永3(1266)年に再建されたものです。
三十三間堂の名称は、本堂が間面記法で「三十三間四面」となることに由来し、柱間が33あるのは本堂の
内陣(母屋・身舎)であり、建物外部から見える柱間は35あります。
また、33は観音菩薩に縁のある数字で、法華経等に観音菩薩が33種の姿に変じて衆生を救うと説かれて
います。
※「間」(けん)は長さの単位ではなく、社寺建築の柱間の数を表す建築用語だそうです

中央に安置されている千手観音座像の圧倒的存在感と、お顔が1001体ごとに違う
千手観音立像がとても印象的と言いますか、時間があればずっと眺めていられそうです。



南側から北側を見た様子
本堂西側の軒下(長さ約121m)を南から北に矢を射通す弓術の競技で、安土桃山時代に行われ始め
江戸時代前期に各藩の弓術家により盛んに行われ、京の名物行事となりました。縁の北端に的を置き
縁の南端から軒天井に当たらぬよう矢を射抜き、その本数を競いました。
現在は「楊枝のお加持」(1月中旬)に本堂西側の射程60mの特設射場で矢を射る「三十三間堂大的全国大会」
が行われ、大会参加者のうち新成人女性が振袖袴姿で行射する場面は、ニュースで取り上げられます。
射程60mは弓道競技の「遠的」にあたります。私は射程28mの「近的」しかやったことがありません。
バスに乗り、再び京都駅へ


さらば京都駅 また来る日まで。JRに乗り稲荷駅へ
伏見稲荷大社

(京都市伏見区深草薮之内町68)


楼門

本殿


千本鳥居

奥社奉拝所 (奥之院)
この先、稲荷山の上の方にもお社がありますが、この後の予定があるため引き返しました。

京阪電鉄 伏見稲荷神社駅前にあった 麺好坊 蓮(現在閉店)でラーメンを食べました。
わざわざ京都に行ってラーメンを食べる第二弾(笑)


チャーシューがたくさん載ってて嬉しかったんですけど、もう食べれないんですね…。
京阪電車に乗って、藤森駅で下車


都(みやこ)エコロジーセンター
(京都府京都市伏見区深草池ノ内町13)

地球規模での環境問題から、京都ならではのエコロジーの知恵を学べる展示や
図書コーナーや屋上にはビオトープがあります。
建物全体がエコな展示となっており、太陽光発電、雨水利用、地中熱利用、高断熱外壁など
省エネルギー、自然素材の活用など様々な工夫を見学することができます。



ここは寺院じゃないですけど、と言うツッコミがありそうですが、こちらは時間調整の為に
立ち寄りました。
と、言うのも、高速バス乗り場に近かったのです。


高速深草 バス停
大阪~東京間を走る グラン昼急行号に乗車
(※ 2023年10月28日に豊田東JCT~御殿場JCT間は東名高速から新東名高速を走行する経路に変更されました)

西日本ジェイアールバスの車両でした。

浜名湖サービスエリアで休憩
(※ 現在は、大阪~東京間を走る高速バスは停車しません)

浜名湖

東名静岡 で下車 (東名高速・静岡ICにあるバス停)
(※ 現在は、大阪~東京間を走る高速バスは停車しません)
静岡インターチェンジ近くのバス停から静岡駅前行きのバスに乗車

静岡駅前から、妻の実家近くのバス停へ。
何も言わずに、妻の実家に八つ橋を手土産に訪問。
義父母が大変びっくりしていましたが、私の突然の訪問を喜んでくれました。
2020年3月22日

義父母に富士山静岡空港まで送っていただき、新千歳行きのANA便に搭乗

富士山はこの日は照れ屋さんでした(姿見えず)

新千歳空港に到着
高校時代を思い出して京都のお寺を巡って、静岡(妻の実家)に立ち寄るという突飛な旅でした。
4年経つと、お店が無くなっていたり、高速バスの経路も変わっちゃうんですね…。
最新情報ではない記事となってしましました。
おわり