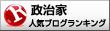「ツチ」とは「物を小さくする・小さい物が集まる」というのが語源。
ツチの解き方
「ツチ」の「ツ」とは、「集まる・散る」というプラス・マイナス、正反の両思想を表す。
「チ」とは、「微粒子・エネルギー」というイミ。
それで「ツチ」とは、「物を小さくする・小さいものが集まる」という正反2つのイミを持っている言霊(日本語)である。
「ツチの百面相」を次に示す。
ツチというイミは
①つち(土)
②つち(地)
③つち(槌)
④つち(鎚)
⑤つじ(辻)
⑥・・・・
として日本人の生活のなかで使っていますが、本来の「ツチ」という日本語(やまとことば)の語源を探求すれば、次のような解釈が得られます。
日本語では「ツチ」は(小さいものが集まる・ちいさくする)というイミですから、
例①のつち(土)は、微小のものが集まったもの。大きいものは小石まじりとか、石まじりのツチともいう。死ぬことを「ツチに帰る」というのは、語源どおり「微小のものに」になるという国語で、決して漢字の「土」になるという思想ではない。
やはり「土をツチ」と我々は日本ヨミするから、そのとおり「ツチになる」と苗代仮名の「土」で書く国語表記で考えたい。
例②のつち(地)をツチというのも亦同じ。微小のものが集まる、「マイナスでちらす」というイミ。大地とか地球というものは、微小のものが集まって出来たと今日の科学を説いている。
太古日本人は日本語の記号を自然物に求めたから、今日の科学思想で「大地とか地球をツチ」と教えなければ寧ろオカシイ。
例③④のつち(槌・鎚)はコマカクするというので、ツチ(槌・鎚)という。大黒様のツチ、一寸法師が鬼からもらった「ツチ」などは、小さいものから大きなものが次から次へと出てくるというイミのツチの百面相であった。これらの物語の土台となったものは「ツチ」という言霊の中にそのモトがあり、振るほどに様々なものが現れるというイミ。時にはマイナスで大きなものを細かくするものを「ツチ」という。大ヅチ、小ヅチを作って、その用を足す。
例⑤のつじ(辻)は「三ッ辻・四ッ辻」などとて、道路の交差点をいう。国語では「ヂはチ」の元の形で「音のイミ」を更に強化する。ツヂもツジも同じで、人や物の寄ったり散ったりする所のイミで使うコトバ。
ツチの解き方
「ツチ」の「ツ」とは、「集まる・散る」というプラス・マイナス、正反の両思想を表す。
「チ」とは、「微粒子・エネルギー」というイミ。
それで「ツチ」とは、「物を小さくする・小さいものが集まる」という正反2つのイミを持っている言霊(日本語)である。
「ツチの百面相」を次に示す。
ツチというイミは
①つち(土)
②つち(地)
③つち(槌)
④つち(鎚)
⑤つじ(辻)
⑥・・・・
として日本人の生活のなかで使っていますが、本来の「ツチ」という日本語(やまとことば)の語源を探求すれば、次のような解釈が得られます。
日本語では「ツチ」は(小さいものが集まる・ちいさくする)というイミですから、
例①のつち(土)は、微小のものが集まったもの。大きいものは小石まじりとか、石まじりのツチともいう。死ぬことを「ツチに帰る」というのは、語源どおり「微小のものに」になるという国語で、決して漢字の「土」になるという思想ではない。
やはり「土をツチ」と我々は日本ヨミするから、そのとおり「ツチになる」と苗代仮名の「土」で書く国語表記で考えたい。
例②のつち(地)をツチというのも亦同じ。微小のものが集まる、「マイナスでちらす」というイミ。大地とか地球というものは、微小のものが集まって出来たと今日の科学を説いている。
太古日本人は日本語の記号を自然物に求めたから、今日の科学思想で「大地とか地球をツチ」と教えなければ寧ろオカシイ。
例③④のつち(槌・鎚)はコマカクするというので、ツチ(槌・鎚)という。大黒様のツチ、一寸法師が鬼からもらった「ツチ」などは、小さいものから大きなものが次から次へと出てくるというイミのツチの百面相であった。これらの物語の土台となったものは「ツチ」という言霊の中にそのモトがあり、振るほどに様々なものが現れるというイミ。時にはマイナスで大きなものを細かくするものを「ツチ」という。大ヅチ、小ヅチを作って、その用を足す。
例⑤のつじ(辻)は「三ッ辻・四ッ辻」などとて、道路の交差点をいう。国語では「ヂはチ」の元の形で「音のイミ」を更に強化する。ツヂもツジも同じで、人や物の寄ったり散ったりする所のイミで使うコトバ。