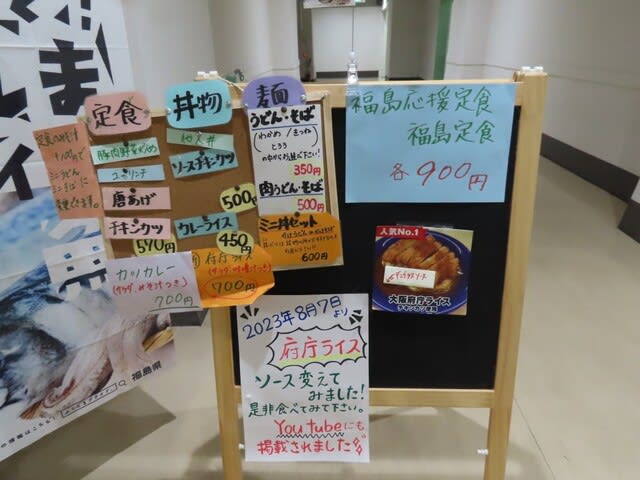大阪城公園の中にある「大阪城天守閣」を見に行って来ました。
下調べを何もしないで行きましたが、新大阪からJR大阪城公園駅でおり、青屋門から何とか入る事が出来ました。
(旅先で目的地までの道が分からない時はまわりの方に遠慮しいしいお尋ねをしています。今回大阪では何回もお尋ねをしたのですがどなたも本当に親切に丁寧に道順を教えてくれました。有難い事です。)

青屋門から何とか入ると見えてきた景色がこれです。
黒い壁に金色、奇麗でした。
「ウィキペディア(Wikipedia)」によると、「天守は1931年(昭和6年)に鉄骨鉄筋コンクリート (SRC) 構造で、徳川時代に再建された天守台石垣の上に資料の乏しい豊臣時代の天守閣を想像し大坂夏の陣図屏風絵などを参考に模擬復興された創作物」とあります。
「豊臣の黒い城、徳川の白い城」と言われますが、松本城は豊臣の黒い城の代表的な一つになります。
今回、大学生時代の繋がりで大阪に行き、大阪城天守閣をこの目で見る事ができた事はありがたい事でした。
以下、大阪城天守閣の金色が映える画像を紹介させていただきます。



天守閣の鯱です。