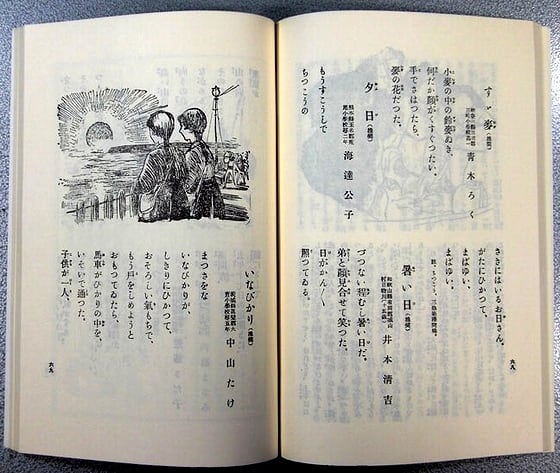今年もすでに300件を超えるブログ記事を投稿したが、その中でも忘れることのできない記事の一つが、5月21日の「はこべら」だ。
平成29年(2017)に他界された規工川佑輔先生の奥様から先生の最後の歌集が送られてきた。この「はこべら」という歌集のタイトルは先生の遺作となった次の歌から採られたことが奥様のあとがきに書かれていた。
「県道を渡れる脚を持たざれば春野にはこべら踏むこともなし」
先生の最晩年は自らの足で歩くことはできなくなっていた。先生のご自宅近くの県道を渡ると田園地帯が広がっている。その畦道には春になると七草のひとつ「はこべら(ハコベ)」が咲き乱れ、少年時代はおそらくその畦道が遊び場だったのだろう。しかし、今の自分はその畦道に踏み入れることもできない。そんな身の上を、自虐的なニュアンスを込めて歌われたものと思う。
この歌を読みながら、僕は少女詩人・海達公子が幼い頃に詠んだ一つの詩を思い出した。それは「すみれ」と題する可愛らしい詩だった。
「あしもとのすみれ ふまんでよかつた」
海達公子を愛し、生涯をかけて顕彰し続けた規工川先生は、最後の最後まで公子のことを忘れることはなかったに違いない。はこべらの歌を詠まれた時も、公子のこの詩が念頭にあったのかもしれない。
その他、次の一編が心をとらえた。
「天才詩人の祭りとぞ言ひ赤き幟幾本も立てり春の雨の中」
毎年3月の彼女の命日の前後に荒尾市では「海達公子まつり」が行われる。この歌はある年の「海達公子まつり」の日、会場に立てられた幾本もの赤い幟が春雨にうたれている情景を詠まれたもの。この歌も公子の辞世の句といわれる次の二句を連想させて感慨深い。
「巡礼の 御詠歌つゞく 菜種畠」
「春雨に 石碑を刻む 音寂し」
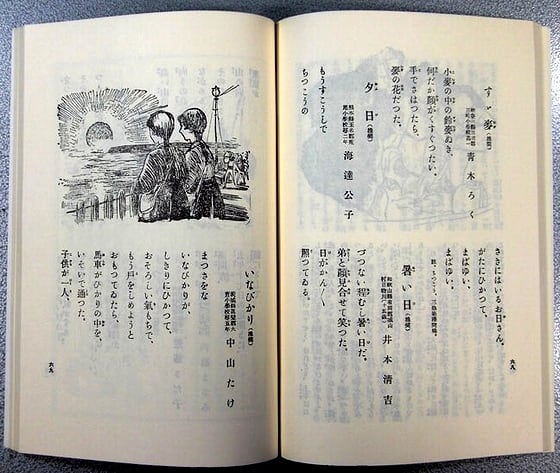
平成29年(2017)に他界された規工川佑輔先生の奥様から先生の最後の歌集が送られてきた。この「はこべら」という歌集のタイトルは先生の遺作となった次の歌から採られたことが奥様のあとがきに書かれていた。
「県道を渡れる脚を持たざれば春野にはこべら踏むこともなし」
先生の最晩年は自らの足で歩くことはできなくなっていた。先生のご自宅近くの県道を渡ると田園地帯が広がっている。その畦道には春になると七草のひとつ「はこべら(ハコベ)」が咲き乱れ、少年時代はおそらくその畦道が遊び場だったのだろう。しかし、今の自分はその畦道に踏み入れることもできない。そんな身の上を、自虐的なニュアンスを込めて歌われたものと思う。
この歌を読みながら、僕は少女詩人・海達公子が幼い頃に詠んだ一つの詩を思い出した。それは「すみれ」と題する可愛らしい詩だった。
「あしもとのすみれ ふまんでよかつた」
海達公子を愛し、生涯をかけて顕彰し続けた規工川先生は、最後の最後まで公子のことを忘れることはなかったに違いない。はこべらの歌を詠まれた時も、公子のこの詩が念頭にあったのかもしれない。
その他、次の一編が心をとらえた。
「天才詩人の祭りとぞ言ひ赤き幟幾本も立てり春の雨の中」
毎年3月の彼女の命日の前後に荒尾市では「海達公子まつり」が行われる。この歌はある年の「海達公子まつり」の日、会場に立てられた幾本もの赤い幟が春雨にうたれている情景を詠まれたもの。この歌も公子の辞世の句といわれる次の二句を連想させて感慨深い。
「巡礼の 御詠歌つゞく 菜種畠」
「春雨に 石碑を刻む 音寂し」