 ザ・わらべのあやのちゃんのお母さんから面白いビデオを何点かご提供いただいた。そのうちの一つは4年前になるが、2007年12月24日に行われた、祇園橋のたもとにあるポケットパーク(熊本市細工町5丁目)の「おてもやん像」除幕式の時の映像だ。当時、小学5年生(10歳)と4年生(9歳)だったザ・わらべの3人が「おてもやん像」の前で可愛い踊りを披露している。若干心もとないところもあるが、基本はすでに身に付けているようだ。これと最近の映像とを比較して見ると、この4年間の彼女たちの成長と踊りの上達ぶりがとてもよくわかって面白い。
ザ・わらべのあやのちゃんのお母さんから面白いビデオを何点かご提供いただいた。そのうちの一つは4年前になるが、2007年12月24日に行われた、祇園橋のたもとにあるポケットパーク(熊本市細工町5丁目)の「おてもやん像」除幕式の時の映像だ。当時、小学5年生(10歳)と4年生(9歳)だったザ・わらべの3人が「おてもやん像」の前で可愛い踊りを披露している。若干心もとないところもあるが、基本はすでに身に付けているようだ。これと最近の映像とを比較して見ると、この4年間の彼女たちの成長と踊りの上達ぶりがとてもよくわかって面白い。昨年11月の「秋のくまもとお城まつり」における踊り












 先日用事があって植木町へ行った。昨年末、3年にわたって放送されたドラマ「坂の上の雲」が完結したが、このドラマで、柄本明演じる乃木将軍が生涯のトラウマになったという向坂を久しぶりに回ってみることにした。200名の熊本鎮台歩兵第14連隊を率いて薩軍と戦った乃木少佐は、向坂における戦闘で連隊旗を持っていた河原林雄太少尉が戦死したため連隊旗を奪われるという屈辱を味わう。乃木は何度も自殺を図ったが、児玉源太郎に諌められた時の話はドラマの中でも語られていた。明治10年(1877)2月22日、官軍と薩軍が最初の戦闘を行った地点が植木天満宮周辺で、標識のみが西南戦争の名残をとどめる。旧豊前街道を少し南へ下ると河原林少尉が戦死した地点の標識と記念碑がある。おそらくほとんどの人が気付かずに通り過ぎてしまうだろう。135年前の出来事である。
先日用事があって植木町へ行った。昨年末、3年にわたって放送されたドラマ「坂の上の雲」が完結したが、このドラマで、柄本明演じる乃木将軍が生涯のトラウマになったという向坂を久しぶりに回ってみることにした。200名の熊本鎮台歩兵第14連隊を率いて薩軍と戦った乃木少佐は、向坂における戦闘で連隊旗を持っていた河原林雄太少尉が戦死したため連隊旗を奪われるという屈辱を味わう。乃木は何度も自殺を図ったが、児玉源太郎に諌められた時の話はドラマの中でも語られていた。明治10年(1877)2月22日、官軍と薩軍が最初の戦闘を行った地点が植木天満宮周辺で、標識のみが西南戦争の名残をとどめる。旧豊前街道を少し南へ下ると河原林少尉が戦死した地点の標識と記念碑がある。おそらくほとんどの人が気付かずに通り過ぎてしまうだろう。135年前の出来事である。

 熊本県、熊本市、熊本大が中国・上海市に共同開設した「熊本上海事務所」の開所式が11日、蒲島郁夫知事、幸山政史市長、谷口功学長を始め、県の経済界からも多数が出席して現地で行なわれました。夜には市内のホテルでレセプションが行われ、熊本の伝統芸能を代表して少女舞踊団ザ・わらべが出演、華麗な舞を披露しました。今回はメンバーのうち、くるみちゃんが高校入試直前のため参加できませんでしたが、かえちゃんとあやのちゃんの中2コンビが立派に舞台を務め、出席者の大きな拍手を浴びていました。
熊本県、熊本市、熊本大が中国・上海市に共同開設した「熊本上海事務所」の開所式が11日、蒲島郁夫知事、幸山政史市長、谷口功学長を始め、県の経済界からも多数が出席して現地で行なわれました。夜には市内のホテルでレセプションが行われ、熊本の伝統芸能を代表して少女舞踊団ザ・わらべが出演、華麗な舞を披露しました。今回はメンバーのうち、くるみちゃんが高校入試直前のため参加できませんでしたが、かえちゃんとあやのちゃんの中2コンビが立派に舞台を務め、出席者の大きな拍手を浴びていました。 NHKお昼のバラエティ番組「ひるブラ」は昨日と今日は熊本。昨日の水前寺公園に続いて今日は熊本城の城下町、新町と古町界隈だったのだが、始まった途端に緊急地震速報が入った。何ぶんにも生放送。有田雅明アナとリポーターの夏川純が、スタジオにいるコメンテーターの細川茂樹に洗馬橋を紹介しようとしたその時だった。何度か中断があり、再び予定のプログラムに戻ったが、多分合わせて5分ほどのカットされた内容は何だったのだろう。地震速報が最優先だからしかたないとはいえ、見ていた僕もイマイチ気分が乗らず、残念な放送となってしまった。せっかくの全国放送だったからまたいつか機会があればいいが。
NHKお昼のバラエティ番組「ひるブラ」は昨日と今日は熊本。昨日の水前寺公園に続いて今日は熊本城の城下町、新町と古町界隈だったのだが、始まった途端に緊急地震速報が入った。何ぶんにも生放送。有田雅明アナとリポーターの夏川純が、スタジオにいるコメンテーターの細川茂樹に洗馬橋を紹介しようとしたその時だった。何度か中断があり、再び予定のプログラムに戻ったが、多分合わせて5分ほどのカットされた内容は何だったのだろう。地震速報が最優先だからしかたないとはいえ、見ていた僕もイマイチ気分が乗らず、残念な放送となってしまった。せっかくの全国放送だったからまたいつか機会があればいいが。
 今年のNHK大河ドラマ「平清盛」の映像について、兵庫県の井戸敏三知事が「鮮やかさがなく、薄汚れた画面ではチャンネルを回す気にはならない」と酷評したことが論議を呼んでいる。兵庫県は大輪田泊や福原京など、平家ゆかりの観光スポットがあるため、大河ドラマを観光振興の目玉にしようとした目算が外れかねないということのようだ。初回の視聴率が意外と低かったこともあって黙ってはいられなかったのだろう。実は熊本も五家荘や五木村に平家落人伝説があり、このドラマで観光振興を図ろうとしていると聞いているので他人事ではないのだが。しかし何と言ってもまだ1回放送しただけだし、第一、視聴率が低かったのはそれが理由じゃないと思う。国民的人気のある坂本龍馬を描いた「龍馬伝」ですら期待したほどの視聴率は取れなかった。ハッキリ言って平清盛は日本人にはあまり人気がない。これからよっぽどのテコ入れをしない限り、高視聴率は望めないだろう。一方のNHKの言いぐさもふるっている。「リアルさを追求した映像表現・・・」だそうな。プログレッシブカメラやメーキャップも含め、薄汚くすることがリアルだとでも言うのだろうか。「お前はその時代を見たんか!?」とツッコミたくなる。まぁ、今後どう展開しようとあまり興味はないのでどうでもいいのだが。市川雷蔵様の平清盛をまた見たくなった。
今年のNHK大河ドラマ「平清盛」の映像について、兵庫県の井戸敏三知事が「鮮やかさがなく、薄汚れた画面ではチャンネルを回す気にはならない」と酷評したことが論議を呼んでいる。兵庫県は大輪田泊や福原京など、平家ゆかりの観光スポットがあるため、大河ドラマを観光振興の目玉にしようとした目算が外れかねないということのようだ。初回の視聴率が意外と低かったこともあって黙ってはいられなかったのだろう。実は熊本も五家荘や五木村に平家落人伝説があり、このドラマで観光振興を図ろうとしていると聞いているので他人事ではないのだが。しかし何と言ってもまだ1回放送しただけだし、第一、視聴率が低かったのはそれが理由じゃないと思う。国民的人気のある坂本龍馬を描いた「龍馬伝」ですら期待したほどの視聴率は取れなかった。ハッキリ言って平清盛は日本人にはあまり人気がない。これからよっぽどのテコ入れをしない限り、高視聴率は望めないだろう。一方のNHKの言いぐさもふるっている。「リアルさを追求した映像表現・・・」だそうな。プログレッシブカメラやメーキャップも含め、薄汚くすることがリアルだとでも言うのだろうか。「お前はその時代を見たんか!?」とツッコミたくなる。まぁ、今後どう展開しようとあまり興味はないのでどうでもいいのだが。市川雷蔵様の平清盛をまた見たくなった。



 元日に見逃したBSプレミアムのドキュメンタリードラマ「開拓者たち」の第1回目(再放送)と第2回目を観る。話には聞いていたが、やっぱり映像で見るとその事実の重さに胸が痛くなる。歴史に名を残した英雄たちを描くドラマもいいが、僕はやっぱりこんな名もない人たちが辿った運命を描いたドラマの方がリアリティがあって好きだ。80年代の初め、僕は那須高原には仕事で毎日のように登り、あちこち巡ったが千振地区には行ったことがない。今はそれが残念でならない。僕の職場の同僚だった女の子が千振地区の隣の地区の酪農家に嫁に行った。元気でいるだろうか。ドラマを見ていて急に気になりだした。このドラマには満島ひかりを始め、石田卓也、徳永えりら、僕が今期待している若手が何人も出演しているのも楽しみだ。彼らが中高年までを演じるこのドラマは彼らにとっていい経験になるだろう。
元日に見逃したBSプレミアムのドキュメンタリードラマ「開拓者たち」の第1回目(再放送)と第2回目を観る。話には聞いていたが、やっぱり映像で見るとその事実の重さに胸が痛くなる。歴史に名を残した英雄たちを描くドラマもいいが、僕はやっぱりこんな名もない人たちが辿った運命を描いたドラマの方がリアリティがあって好きだ。80年代の初め、僕は那須高原には仕事で毎日のように登り、あちこち巡ったが千振地区には行ったことがない。今はそれが残念でならない。僕の職場の同僚だった女の子が千振地区の隣の地区の酪農家に嫁に行った。元気でいるだろうか。ドラマを見ていて急に気になりだした。このドラマには満島ひかりを始め、石田卓也、徳永えりら、僕が今期待している若手が何人も出演しているのも楽しみだ。彼らが中高年までを演じるこのドラマは彼らにとっていい経験になるだろう。
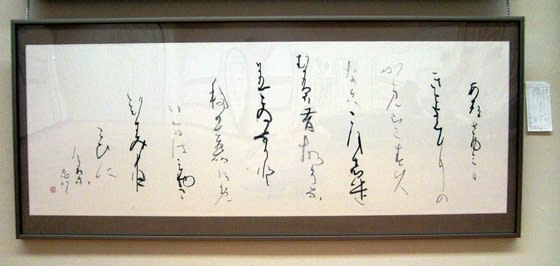

 毎年正月になると、とても気になる年賀状が何枚かある。そのうちの1枚が酒井恭次先生の年賀状だ。酒井先生は僕がブリヂストン在職時、ずっとお世話になった方で、横浜工場の産業医を永年務めておられたお医者さんである。今年91歳になられる。先生からの年賀状を拝見すると「あゝまだご健在だったか!」とホッと胸をなでおろす。入社してすぐに新入社員研修を受けたのが横浜工場だったので、その時からお世話になり始め、もう42年が過ぎた。僕が横浜にいたのはその新入社員研修の半年間だけだったが、その後も仕事の上で先生との関係は続いた。最も濃密な関係だったのは僕が本社の労働安全衛生部門にいた時だった。その頃すでにブリヂストンにとどまらず、産業医学の面で幅広く活躍されていた酒井先生には、高齢化が進んでいた社員の健康管理施策を策定するにあたり、いろいろ教えを請うことが多かった。そして夜になると必ず横浜の街に連れて行っていただき、何軒も飲み歩いたものだ。僕が退職してからはほとんど年賀状のやりとりだけになったが、必ず近況が書き添えてあった。その書き添えられる言葉が、ここ数年、戦時中の話が多くなった。今年の年賀状にも「昭和17年10月、西部16部隊に入隊した・・・」と書き添えられていた。西部16部隊とはかつて熊本にあった日本帝国陸軍の部隊である。先生はおそらく、僕のことを考えてできるだけ共通の話題になるように、熊本にいた頃の話を書かれたのかもしれない。そんな心配りをされる姿を想像したら、年賀状だけでなくもっとまめにお便りをしなければ、と反省した一日だった。
毎年正月になると、とても気になる年賀状が何枚かある。そのうちの1枚が酒井恭次先生の年賀状だ。酒井先生は僕がブリヂストン在職時、ずっとお世話になった方で、横浜工場の産業医を永年務めておられたお医者さんである。今年91歳になられる。先生からの年賀状を拝見すると「あゝまだご健在だったか!」とホッと胸をなでおろす。入社してすぐに新入社員研修を受けたのが横浜工場だったので、その時からお世話になり始め、もう42年が過ぎた。僕が横浜にいたのはその新入社員研修の半年間だけだったが、その後も仕事の上で先生との関係は続いた。最も濃密な関係だったのは僕が本社の労働安全衛生部門にいた時だった。その頃すでにブリヂストンにとどまらず、産業医学の面で幅広く活躍されていた酒井先生には、高齢化が進んでいた社員の健康管理施策を策定するにあたり、いろいろ教えを請うことが多かった。そして夜になると必ず横浜の街に連れて行っていただき、何軒も飲み歩いたものだ。僕が退職してからはほとんど年賀状のやりとりだけになったが、必ず近況が書き添えてあった。その書き添えられる言葉が、ここ数年、戦時中の話が多くなった。今年の年賀状にも「昭和17年10月、西部16部隊に入隊した・・・」と書き添えられていた。西部16部隊とはかつて熊本にあった日本帝国陸軍の部隊である。先生はおそらく、僕のことを考えてできるだけ共通の話題になるように、熊本にいた頃の話を書かれたのかもしれない。そんな心配りをされる姿を想像したら、年賀状だけでなくもっとまめにお便りをしなければ、と反省した一日だった。
