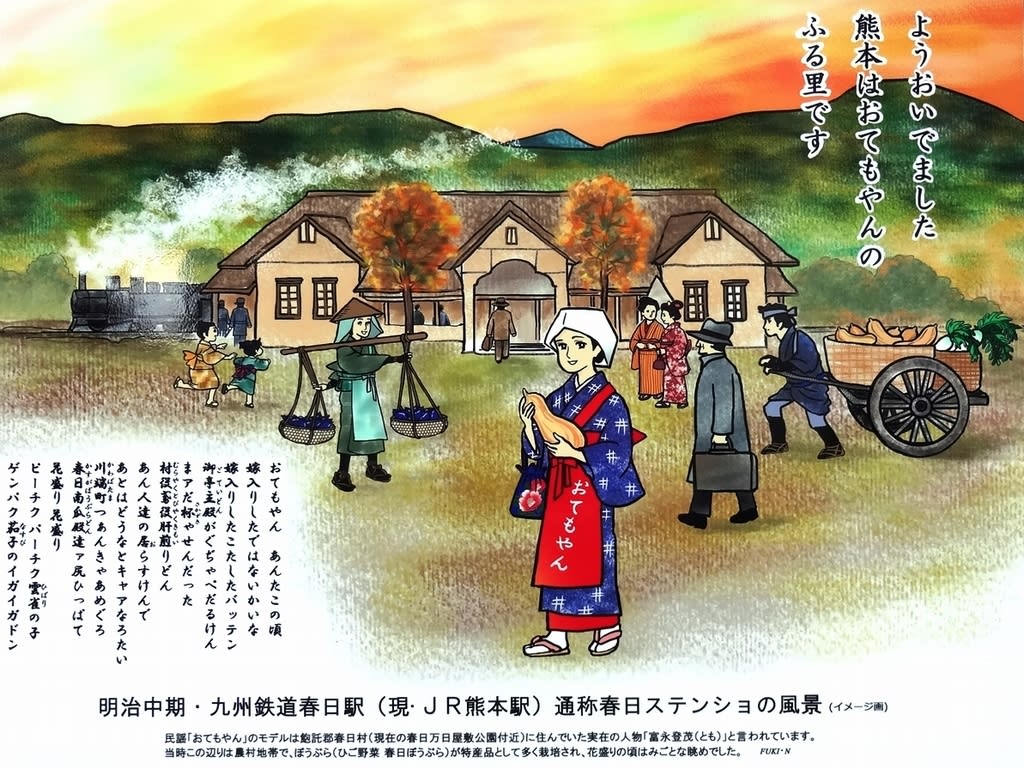花菖蒲が見ごろの季節となった。毎年、高瀬裏川の花菖蒲を見に行くのだが今年はまだ行っていない。この時期になると、僕は必ず読み返したくなる文章がある。それは若山牧水の「水郷めぐり」という紀行文だ。旅を愛し、酒を愛した若山牧水の短歌や俳句は日本各地で歌碑を見かけるが、彼の紀行文も捨てがたい。茨城県から千葉県に広がる水郷はかつて文人墨客たちを魅了した。この牧水の「水郷めぐり」の中でも後半の「あやめ踊り」が出てくるくだりを記してみた。「あやめ踊り」で踊られる曲が「潮来音頭」や「潮来甚句」である。
豊津に帰った頃雨も滋(しげ)く風も加わった。鳥居の下から舟を雇って潮来へ向う、苫(とま)をかけて帆あげた舟は快い速度で広い浦、狭い河を走ってゆくのだ。ずっと狭い所になるとさっさっと真菰(まこも)の中を押分けて進むのである。真みどりなのは真菰、やや黒味を帯びたのは蒲(かば)だそうである。行々子(よしきり)の声がそこからもここからも湧く。船頭の茂作爺は酒好きで話好きである。潮来の今昔を説いて頻りに今の衰微を嘆く。
川から堀らしい所へ入っていよいよ真菰の茂みの深くなった頃、ある石垣の蔭に舟は停まった。茂作爺の呼ぶ声につれて若い女が傘を持って迎えに来た。そこはM――屋という引手茶屋であった。二階からはそれこそ眼の届く限り青みを帯びた水と草との連りで、その上をほのかに暮近い雨が閉ざしている。薄い靄の漂っておる遠方に一つの丘が見ゆる。そこが今朝詣でて来た香取の宮であるそうな。
何とも言えぬ静かな心地になって酒をふくむ。軽やかに飛び交しておる燕にまじっておりおり低く黒い鳥が飛ぶ。行々子であるらしい。庭ききの堀をばちょうど田植過ぎの田に用いるらしい水車を積んだ小舟がいくつも通る。我らの部屋の三味の音に暫く棹を留めて行くのもある。どっさりと何か青草を積込んで行くのもある。
それらも見えず、全く闇になった頃名物のあやめ踊りが始まった。十人ばかりの女が真っ赤な揃いの着物を着て踊るのであるが、これはまたその名にそぐわぬ勇敢無双の踊りであった。一緒になって踊り狂うた茂作爺は、それでも独り舟に寝に行った。
翌朝、雨いよいよ降る。
【霞が浦即興】
わが宿の灯影さしたる沼尻の葭の繁みに風さわぐ見ゆ
沼とざす眞闇ゆ蟲のまひ寄りて集ふ宿屋の灯に遠く居る
をみなたち群れて物洗ふ水際に鹿島の宮の鳥居古りたり
鹿島香取宮の鳥居は湖越しの水にひたりて相向ひたり
苫蔭にひそみつゝ見る雨の日の浪逆(なさか)の浦はかき煙らへり
雨けぶる浦をはるけみひとつゆくこれの小舟に寄る浪聞ゆ
※3年ほど前に掲載した記事を再編集し、再掲しました。

 福岡県みやま市の大江に唯一残る幸若舞が今日まで生き延びてきたのは、明治末期に文学者で芸能史家でもある高野辰之が大江を訪れたことが与って力があったという。今年1月の大江天満神社における奉納舞でもそんな説明があった。
福岡県みやま市の大江に唯一残る幸若舞が今日まで生き延びてきたのは、明治末期に文学者で芸能史家でもある高野辰之が大江を訪れたことが与って力があったという。今年1月の大江天満神社における奉納舞でもそんな説明があった。













 僕は1976年の5月に熊本から防府へ転勤となった。当時、防府工場はまだ建設中で、工場立ち上げ要員と、先行して建設された材料工程の要員合わせて50名にも満たなかったと記憶している。それでも市民に早くなじんでもらうためには地域の行事には積極的に参加しようというのが工場長の方針だった。防府市では毎年8月に「防府おどり総おどり大会」という大きなイベントが行なわれる。この「総おどり」に参加することになり、僕が推進事務局を仰せつかった。そして「総おどり」の前夜祭として防府市公会堂で行われる「職場対抗のど自慢大会」にも出場しようということになった。各企業から3名づつが歌って総合点で優劣を競うわけだが、何せまだ少人数の職場。なんとか無理をお願いして二人は選んだのだが、みんな尻込みしてあと一人がどうしても見つからない。今さら出場をキャンセルするわけにもいかず、僕自身が出場せざるを得ない羽目となった。それでも前日のリハーサルまでは、どうせ素人の大会と高をくくっていた。ところがいざ会場の防府市公会堂の舞台に上がると、収容人員1800名のホールが当日は満員になりますよという司会者の説明にブルった。しかもである。いざリハーサルが始まるとほかの会社の出場者の歌の上手さにビックリ。まるでプロの歌手なみだ。ますます自信喪失。案の定、翌日の本番ではホールを埋めた大観衆の前で緊張しまくって散々な出来だった。
僕は1976年の5月に熊本から防府へ転勤となった。当時、防府工場はまだ建設中で、工場立ち上げ要員と、先行して建設された材料工程の要員合わせて50名にも満たなかったと記憶している。それでも市民に早くなじんでもらうためには地域の行事には積極的に参加しようというのが工場長の方針だった。防府市では毎年8月に「防府おどり総おどり大会」という大きなイベントが行なわれる。この「総おどり」に参加することになり、僕が推進事務局を仰せつかった。そして「総おどり」の前夜祭として防府市公会堂で行われる「職場対抗のど自慢大会」にも出場しようということになった。各企業から3名づつが歌って総合点で優劣を競うわけだが、何せまだ少人数の職場。なんとか無理をお願いして二人は選んだのだが、みんな尻込みしてあと一人がどうしても見つからない。今さら出場をキャンセルするわけにもいかず、僕自身が出場せざるを得ない羽目となった。それでも前日のリハーサルまでは、どうせ素人の大会と高をくくっていた。ところがいざ会場の防府市公会堂の舞台に上がると、収容人員1800名のホールが当日は満員になりますよという司会者の説明にブルった。しかもである。いざリハーサルが始まるとほかの会社の出場者の歌の上手さにビックリ。まるでプロの歌手なみだ。ますます自信喪失。案の定、翌日の本番ではホールを埋めた大観衆の前で緊張しまくって散々な出来だった。




 こと。その時は、彼が病で先立ってからあまり時が経っていなかったので、ひょっとしたら彼がここに呼んだのではないかと不思議な縁を感じたものだ。そのM君と高校の同級生で親友だったのが清原憲一さん。RKKのアナウンサーとしての活躍ぶりは知っていたし、母黌のプールにも時々顔を出し、水球部の後輩たちによく差し入れをしてくれていたのも知っていた。そのわらべと清原さんが同じ舞台に立っている。思わず、元気な頃のM君の顔が浮かんできて、なにか熱いものがこみ上げてきた。
こと。その時は、彼が病で先立ってからあまり時が経っていなかったので、ひょっとしたら彼がここに呼んだのではないかと不思議な縁を感じたものだ。そのM君と高校の同級生で親友だったのが清原憲一さん。RKKのアナウンサーとしての活躍ぶりは知っていたし、母黌のプールにも時々顔を出し、水球部の後輩たちによく差し入れをしてくれていたのも知っていた。そのわらべと清原さんが同じ舞台に立っている。思わず、元気な頃のM君の顔が浮かんできて、なにか熱いものがこみ上げてきた。











 花菖蒲が見ごろの季節となった。毎年、高瀬裏川の花菖蒲を見に行くのだが今年はまだ行っていない。この時期になると、僕は必ず読み返したくなる文章がある。それは若山牧水の「水郷めぐり」という紀行文だ。旅を愛し、酒を愛した若山牧水の短歌や俳句は日本各地で歌碑を見かけるが、彼の紀行文も捨てがたい。茨城県から千葉県に広がる水郷はかつて文人墨客たちを魅了した。この牧水の「水郷めぐり」の中でも後半の「あやめ踊り」が出てくるくだりを記してみた。「あやめ踊り」で踊られる曲が「潮来音頭」や「潮来甚句」である。
花菖蒲が見ごろの季節となった。毎年、高瀬裏川の花菖蒲を見に行くのだが今年はまだ行っていない。この時期になると、僕は必ず読み返したくなる文章がある。それは若山牧水の「水郷めぐり」という紀行文だ。旅を愛し、酒を愛した若山牧水の短歌や俳句は日本各地で歌碑を見かけるが、彼の紀行文も捨てがたい。茨城県から千葉県に広がる水郷はかつて文人墨客たちを魅了した。この牧水の「水郷めぐり」の中でも後半の「あやめ踊り」が出てくるくだりを記してみた。「あやめ踊り」で踊られる曲が「潮来音頭」や「潮来甚句」である。