東京渋谷区の岸記念体育会館が老朽化により取り壊されるという。僕が大学に入った1964年、つまり東京オリンピックの年に出来たから55年の歴史に幕を下ろすわけだ。学生時代、ここで行われていた日本水泳連盟学生委員会の会議に出席したこともある。当時委員長だった「フジヤマのトビウオ」こと古橋広之進さんに初めてお会いしたのもここだった。懐かしいスポットがまた一つ消える。岸記念体育会館といえば、その名を冠する岸清一さんは、現在放送中の大河ドラマ「いだてん」にも登場している。
学生時代、渋谷は通学の乗換駅でもあり、一つの拠点にしていた。暮には東横百貨店(現在の東急百貨店東横店)の配送センターでアルバイトもした。近くの児童会館で昼飯を食べるのがおきまりとなっていたが、その児童会館も今はないらしい。渋谷駅のハチ公前は当時も待ち合わせのスポットとして有名だったが、今や世界的観光スポットとなったスクランブル交差点はまだなかった。スクランブル化したのは1973年か1974年だったと思う。余談だが、その5年ほど前に熊本市の子飼交差点が日本で初めてスクランブル化している。よく映画を見に行った渋谷パンテオンも今はない。東横線のホームから公開中の映画の立看板を見るのが楽しみだったがそのホームも地下に潜ったらしい。仲間とたむろした道玄坂周辺の喫茶店や食堂もほとんどなくなっているだろう。令和の時代になり、昭和はまた一つ遠くなりにけりである。

岸記念体育会館

渋谷東急文化会館の映画館「渋谷パンテオン」
学生時代、渋谷は通学の乗換駅でもあり、一つの拠点にしていた。暮には東横百貨店(現在の東急百貨店東横店)の配送センターでアルバイトもした。近くの児童会館で昼飯を食べるのがおきまりとなっていたが、その児童会館も今はないらしい。渋谷駅のハチ公前は当時も待ち合わせのスポットとして有名だったが、今や世界的観光スポットとなったスクランブル交差点はまだなかった。スクランブル化したのは1973年か1974年だったと思う。余談だが、その5年ほど前に熊本市の子飼交差点が日本で初めてスクランブル化している。よく映画を見に行った渋谷パンテオンも今はない。東横線のホームから公開中の映画の立看板を見るのが楽しみだったがそのホームも地下に潜ったらしい。仲間とたむろした道玄坂周辺の喫茶店や食堂もほとんどなくなっているだろう。令和の時代になり、昭和はまた一つ遠くなりにけりである。

岸記念体育会館

渋谷東急文化会館の映画館「渋谷パンテオン」





















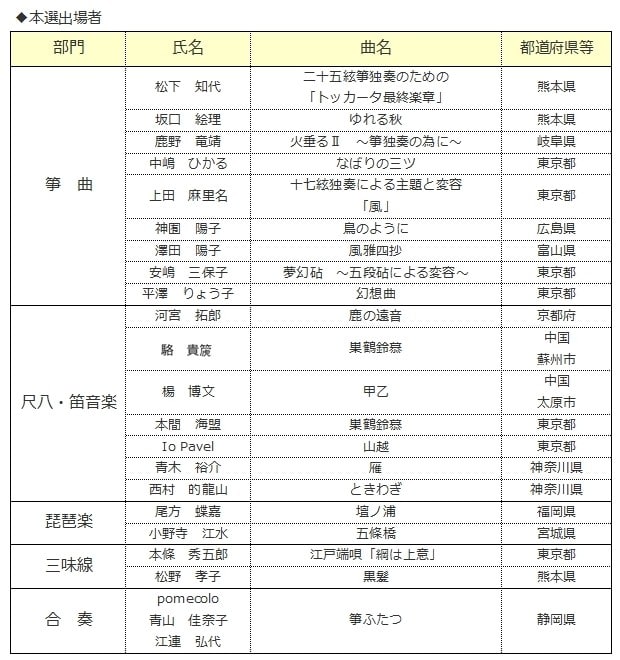



 先日、このブログに11年前に投稿した記事にアクセスがあった。カナダの女性歌手、ゲイル・ガーネットが歌って1964年の大ヒットとなった「We'll Sing In The Sunshine」についての記事だった。投稿したこともすっかり忘れていたので、今また注目していただいたことがありがたかった。動画を再生しながら、この、僕が大学1年で東京オリンピックがあった年のことが懐かしく思い出された。当時、他にはどんな曲を好んで聴いていたのだろうと考えてみた。この年、ビートルズが日本の音楽界に登場した。最初の頃、気になる存在ではあったがハマるということはなかった。それより魅力的な音楽がたくさんあった。そんな中から、今日は、ゲイル・ガーネットの歌も含め、3曲選んでみた。
先日、このブログに11年前に投稿した記事にアクセスがあった。カナダの女性歌手、ゲイル・ガーネットが歌って1964年の大ヒットとなった「We'll Sing In The Sunshine」についての記事だった。投稿したこともすっかり忘れていたので、今また注目していただいたことがありがたかった。動画を再生しながら、この、僕が大学1年で東京オリンピックがあった年のことが懐かしく思い出された。当時、他にはどんな曲を好んで聴いていたのだろうと考えてみた。この年、ビートルズが日本の音楽界に登場した。最初の頃、気になる存在ではあったがハマるということはなかった。それより魅力的な音楽がたくさんあった。そんな中から、今日は、ゲイル・ガーネットの歌も含め、3曲選んでみた。



