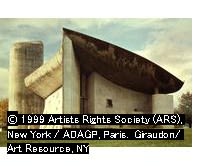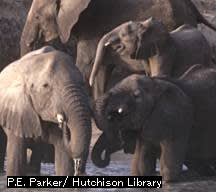アリストテレスの論理学の基本は、現代でも基本的な推論方法とのひとつとされている「三段論法」です。
アリストテレスの論理学の基本は、現代でも基本的な推論方法とのひとつとされている「三段論法」です。
三段論法は、2つの前提を結びつけて、そこから新しい結論を引き出すのですが、そこでの「前提」や「結論」になるのが「命題」です。
この命題の表し方において、アリストテレスは大きな貢献をしました。「命題のアルファベット表記」です。
(p46より引用) 命題のタイプを区別するために、名辞をアルファベットで表わしたが、これはアリストテレス自身が始めたやり方だということは、強調しておく必要がある。・・・この表記の画期的なところはむしろ、命題を「動物」とか「死ぬもの」とかいった具体的な内容にとらわれずに抽象化できるようにしたことにある。それによって、個々の具体的な命題ではなく、命題のタイプを考えることができるようになったということである。
そのように見ると、名辞のアルファベット表記は、たんなる演算上の技術的な革新よりももっと根本的な、「形式論理学」の成立そのものを可能にする工夫であったと言えるであろう。抽象化することなしに形式化することはできないからである。
また、アリストテレスの方法論の特徴として「データ重視」の姿勢が挙げられます。
(p35より引用) 彼がプラトンやアカデメイアの人々の考察法に対して自分の方法論を意識的に対比するとき、彼らの方法は「議論による」やり方として批判される。それと対比されるのは「自然本来のあり方に即した」考察法であるが、その表現が意味しているのは、観察によってえられるデータを重視するやり方である。アリストテレスが議論を軽視しているとはけっして言えないが、データを無視するような議論は無効であると考えるのである。
アリストテレスのデータ重視は、自然学の研究に限ったものではありませんでした。
政治学的な研究においてもその考察方法は用いられています。
(p36より引用) ・・・アリストテレスがデータを収集する場合には、そのデータによって、自然世界に関する事実や理論を確証する場合と、さまざまな問題について考える手がかりをえようとする場合との、少なくとも二つの場合が区別されなければならない。前者には経験主義と呼ばれる立場との共通性が認められるが、後者のうちには経験主義という言葉で片づけられないものが含まれている。
本書の最後の章で、著者はアリストテレスと現代との関わりについて触れています。
そこでの「科学論とアリストテレス」のくだりは、先にこのBlogでも紹介した「科学論入門」での佐々木力氏の見解に通じるところがあります。
(p200より引用) 古代ギリシアでは、技術が未開発であっただけでなく、知のために知を求めることに重要性をおく考えが特徴的であり、それは、アリストテレスに典型的にあらわれている。科学の進歩という観点から見ても、知的欲求に技術の進歩がかみ合ったところに現代の科学の成果があるので、技術偏重になって基礎的な研究を軽視する傾向は、科学にとっても大きな不安材料である。・・・アリストテレスが強調した、生まれつきの知的欲求を、もっと自覚する必要があろう。
 |
アリストテレス入門 価格:¥ 735(税込) 発売日:2001-07 |